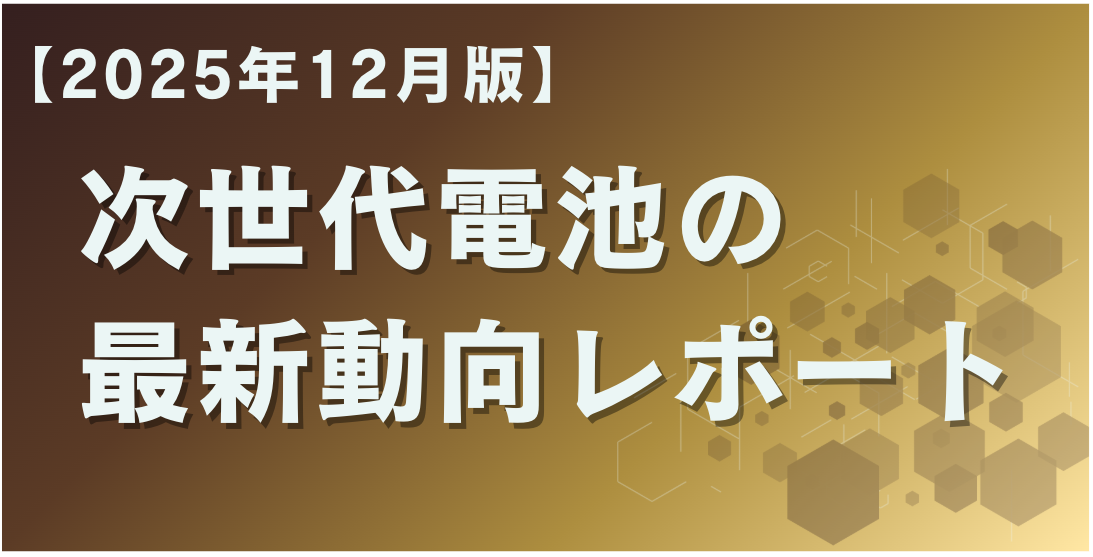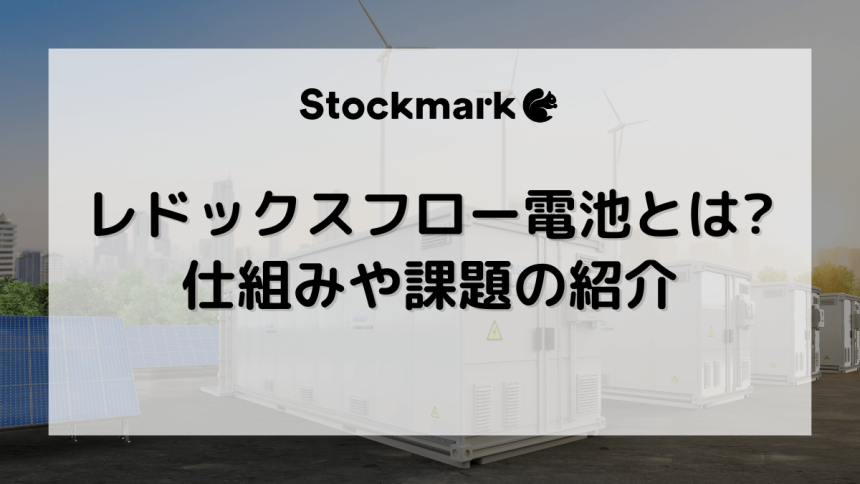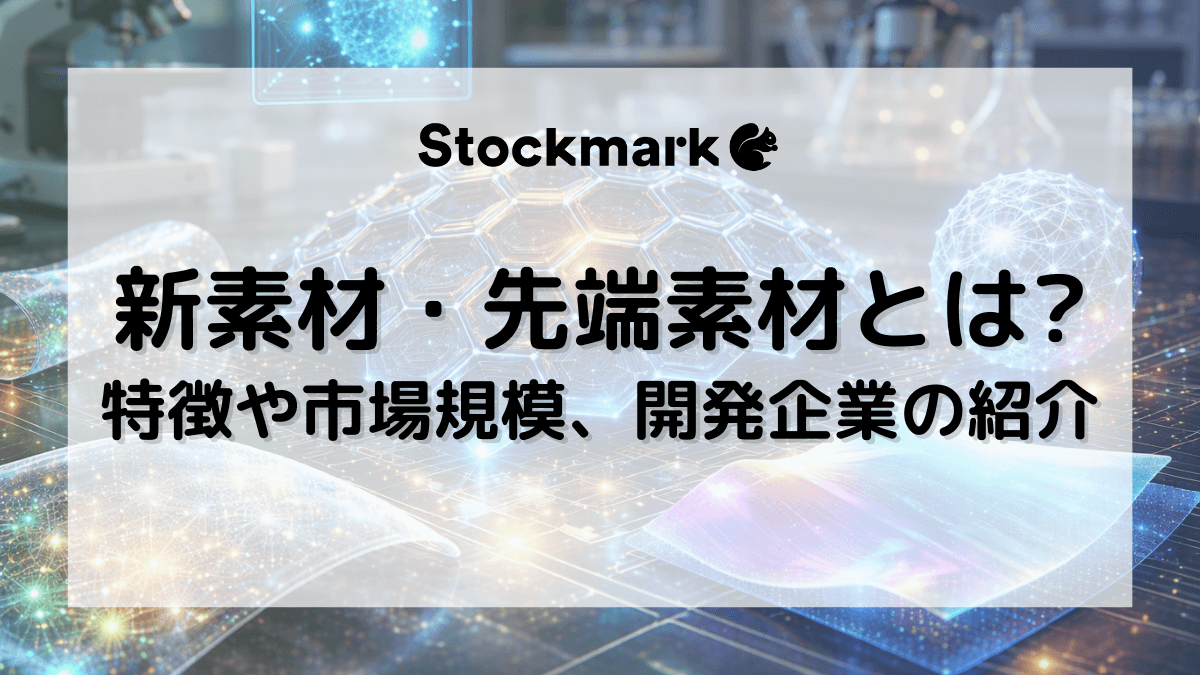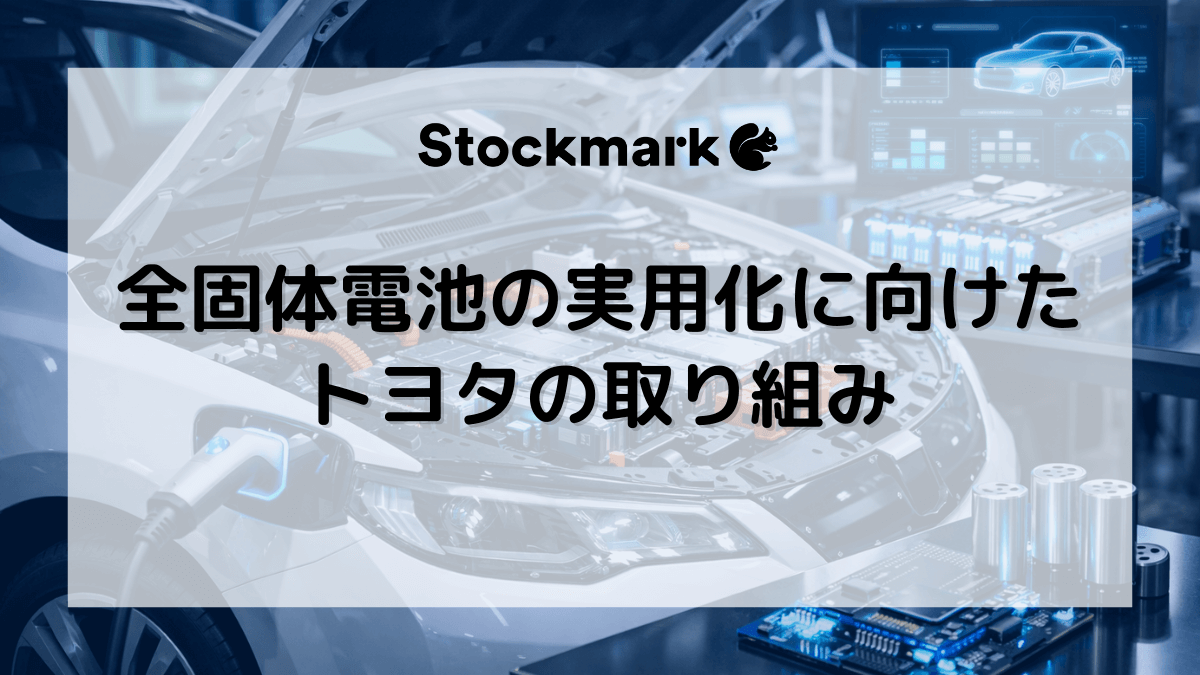再生可能エネルギーの普及が進む中で、電力の安定供給を支える蓄電技術の重要性が高まっている。その中でも注目されているのが、長寿命・高安全性・大容量対応という特長を備えた次世代電池の「レドックスフロー電池」だ。
レドックスフロー電池は、正負の電解液を外部タンクに蓄え、必要なときに化学反応によって充放電を行う蓄電システムであり、大規模な電力貯蔵に適している。しかし、エネルギー密度の低さや導入コスト、標準化の遅れといった課題も残る。
本記事では、レドックスフロー電池の基本構造、市場規模、メリットとデメリット、導入企業の取り組み、将来性について詳しく解説したい。レドックスフロー電池とは何かを正しく理解し、今後のエネルギー戦略にどう活かせるのかを見極めるうえでの参考となるだろう。
次世代電池の技術動向調査レポートを配布中!
▶︎資料(無料)を見てみる
目次
レドックスフロー電池とは?
レドックスフロー電池とは、電解液に含まれる酸化還元反応(レドックス反応)を用いて電気エネルギーを蓄積・放出する二次電池であり、「Redox Flow Battery」の略称としてRFBとも呼ばれる。
リチウムイオン電池などと異なり、固体電極内でのイオンの移動ではなく、液体電解質を外部タンクに貯蔵し、ポンプでセルに循環させる構造が特徴だ。充放電のエネルギー容量は電解液の量で決まり、出力はセルのサイズに依存するため、容量と出力を独立に設計できるスケーラビリティに優れる。これにより、大規模な電力貯蔵用途にも柔軟に対応できる技術として注目されている。
レドックスフロー電池の原理自体は古くから知られていたが、開発が本格化したのは1970年代以降であった。1980年代には、オーストラリア・ニューサウスウェールズ大学のMaria Skyllas Kazacos教授によって、正負電解液の両方にバナジウムを用いるバナジウムレドックスフロー電池の概念と試作機が提案された。この方式は交差汚染の課題を回避できる点で注目を集め、現在でも主流の構成となっている。
その後、2000年代には世界各国でパイロットプロジェクトや実証実験が進み、日本でも新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を中心に、日立造船や住友電工といった民間企業が技術開発や実証に取り組んできた。現在では、再生可能エネルギーの出力変動を吸収し、電力の需給調整を担う次世代の定置型蓄電技術として、レドックスフロー電池への期待が高まっている。
次世代電池の技術動向調査レポートを配布中!
▶︎資料(無料)を見てみる
レドックスフロー電池の仕組み
レドックスフロー電池は、主に「電解液」「電池セル」「ポンプと配管」の3つの要素で構成されている。
この電池では、正極と負極にそれぞれ異なる酸化還元物質を含む電解液が用意され、一般的には水溶液中にバナジウムなどの金属イオンが溶解している。これらの電解液は外部タンクに貯蔵され、必要な量を増やすことで蓄電容量を柔軟に拡張できるという特性をもつ。
電池セルは、2種類の電解液を隔てるイオン交換膜を中心に構成されており、充電時には一方の電解液で酸化反応が進行し、電子が奪われると同時に、もう一方の電解液では還元反応によって電子が受け取られる。こうした電気化学反応により、外部回路に電流が流れ、化学エネルギーとして電気を蓄積することができる。放電時には逆の反応が起こり、蓄えたエネルギーを電力として取り出すことが可能だ。
ポンプは、正極側および負極側の電解液を常時セルに循環させる役割を担っており、反応が安定して継続されるための基本機構である。さらに配管は、電解液の移送経路として、流量や温度、圧力といった条件を制御し、最適な動作環境を維持するために重要な働きを果たしている。これらの構成要素が連携することで、レドックスフロー電池は高い安定性と柔軟なスケーラビリティを実現している。
次世代電池の技術動向調査レポートを配布中!
▶︎資料(無料)を見てみる
レドックスフロー電池の市場規模
レドックスフロー電池の市場は、再生可能エネルギーの安定供給に資する大型蓄電技術として注目されており、今後の成長が期待されている。富士経済の「2025 電池関連市場実態総調査」によると、レドックスフロー電池における2023年の国内外を合計した市場規模は454億円であり、2030年には7,247億円、2035年には1兆3,196億円、2040年には1兆6,252億円に達すると予測されている。また、2023年から2040年までの国内外市場の年平均成長率(CAGR)は約19.3%にのぼる。
一方、海外の調査レポートでは、2024年の世界市場は2億8,244万米ドル、2025年には3億2,133万米ドル、2037年には19億8,000万米ドルに成長すると予測されており、この間のCAGRは16.2%と見込まれている。
なお、太陽光や風力といった不安定な再生可能エネルギーの安定化を図る大型定置用電池として、レドックスフロー電池への期待が集まっている。
次世代電池の技術動向調査レポートを配布中!
▶︎資料(無料)を見てみる
レドックスフロー電池のメリット
レドックスフロー電池には、他の蓄電池にはない独自の利点が存在する。ここでは、長期間にわたって使用できる特性や高い安全性をはじめ、スケーラビリティなどの観点から注目される4つのメリットを紹介する。
長寿命である
レドックスフロー電池は、充放電時に使用される電極材料が物理的・化学的に劣化しにくい構造をもっている。さらに、エネルギーの蓄積と放出は、外部に設置された電解液の酸化還元反応によって行われるが、この反応は可逆的であるため、繰り返しの利用に適している。
この仕組みにより、一般的なリチウムイオン電池と比較しても圧倒的に長い寿命を実現しており、1万回以上の充放電サイクルにも耐えられるとされている。したがって、定置型の蓄電用途においては、長期間の運用が求められる電力インフラへの適用に非常に有利である。
安全性が高い
レドックスフロー電池は、水溶液を用いた電解液を採用しており、発火や爆発のリスクが極めて低い点で高い安全性を備えている。これに対し、一般的なリチウムイオン電池では、有機溶媒を含む可燃性電解液が使われており、過充電や内部短絡によって熱暴走を引き起こし、発火や爆発といった重大な事故につながる危険性がある。
レドックスフロー電池は電気化学反応が穏やかで、発熱も抑えられているため、常温での運転が可能であり、冷却システムの簡略化や安全対策の負担軽減にもつながる。これにより、再生可能エネルギーと組み合わせた長時間・大規模な蓄電用途において、極めて信頼性の高い選択肢とされている。
大規模化が可能
レドックスフロー電池は、電解液を外部タンクに貯蔵し、ポンプで電池セルに循環させる構造を採用している。この仕組みにより、蓄電容量は電池セルではなくタンク内の電解液の量に依存する。そのため、容量を拡大するにはタンクのサイズや電解液の量を増やすだけでよく、セルの数を増やす必要がない。従来のリチウムイオン電池のように多数のセルを直列・並列に接続してスケーリングする方式とは異なり、シンプルかつ柔軟に大規模化が可能である。
これにより、電力系統向けや再生可能エネルギーの平準化を目的とした長時間・大容量の定置型蓄電システムに適しており、経済的かつ効率的なエネルギー運用を実現できる。
充電残量の把握が容易で電池制御しやすい
レドックスフロー電池は、充電残量の把握が容易で電池制御がしやすいという利点を持つ。一般的な蓄電池では、セルごとに充放電の状態が異なり、バラツキが生じやすいため、電池管理システムが複雑化する。一方、レドックスフロー電池では、1つの大型タンクから複数のセルスタックへ同一濃度の電解液が供給されるため、全セルが均一な充電状態を維持する。この構造により、充電残量のモニタリングが容易になり、残量推定の誤差が小さく正確な制御が可能となる。結果として、システム全体の信頼性向上と効率的な運用につながる。
次世代電池の技術動向調査レポートを配布中!
▶︎資料(無料)を見てみる
レドックスフロー電池の課題やデメリット
レドックスフロー電池には多くの利点がある一方で、克服すべき課題も存在する。ここでは、導入や普及に影響を与える3つの主な課題について紹介する。
エネルギー密度が低く小型化が難しい
レドックスフロー電池の課題の一つが、エネルギー密度の低さである。特にバナジウム系のレドックスフロー電池では、体積エネルギー密度は一般的に15〜30Wh/L、重量エネルギー密度は約20Wh/kg程度とされ、リチウムイオン電池の5分の1程度にとどまる。そのため、同じ電力量を蓄えるには大容量の電解液と大型のタンクが必要となり、小型化が難しく、モバイル機器などスペース制限のある用途には不向きである。これが普及における大きな障壁の一つとなっている。
コストがかかる
レドックスフロー電池は、構造上多くの周辺設備を必要とするため、初期コストが高くなる傾向にある。具体的には、電気化学反応を行うセルスタックに加え、電解液を大量に保管するための大型タンク、電解液を循環させるポンプ、流路を構成する配管、動作を監視・制御するセンサーや制御ユニットなど、多岐にわたる機器が必要だ。これらを設置・施工するためのコストも加わることで、他の蓄電池と比較して導入費用が高くなりやすいのが実情である。
資源や小型化などの点から実用化にいたっていない
レドックスフロー電池は、再生可能エネルギーの不安定な発電量を補う蓄電技術として注目されているが、家庭や小規模施設向けの小型モデルについては、いまだ実用化には至っていないのが現状である。その理由として、構造的に大型の装置や補機類を必要とするため、スペースやコストの面で制約が大きい。また、活物質に使用されるバナジウムの資源リスクも無視できない。世界の主要産出国が中国、ロシア、南アフリカに偏っており、供給の安定性や価格の変動が懸念されている。
次世代電池の技術動向調査レポートを配布中!
▶︎資料(無料)を見てみる
レドックスフロー電池の主な用途
| 用途分野 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 自然エネルギーとの連携 | 太陽光や風力の発電変動を補う蓄電池としての導入 |
| 非常用電源 | 病院や避難所などで災害時のバックアップ電源として活用 |
| ピークカット用途 | 工場やビルで電力使用のピークを抑えるために使用 |
| スマートグリッド・マイクログリッド | 地域単位の電力自給システムの中核技術として期待 |
レドックスフロー電池の主な用途は、太陽光発電や風力発電など自然エネルギーと連携した定置型蓄電である。これらの再生可能エネルギーは天候や昼夜の影響で発電量が変動するため、安定した電力供給を実現するために蓄電池が必要不可欠となるが、レドックスフロー電池は大容量化が容易で長寿命かつ安全性が高いため、発電所や工場、地域の電力供給拠点での導入が進んでいる。
また、将来的には、地域単位で電力を自給自足するスマートグリッドやマイクログリッドといった次世代エネルギーインフラにおいて中核技術の一つとして期待されている。他にも、災害時の非常用電源や病院・避難所でのバックアップ用途、工場・ビルのピークカット用途としても導入が進んでおり、持続可能なエネルギー社会を支える技術として活用されている。
レドックスフロー電池を開発している企業・メーカー
レドックスフロー電池の実用化に向けて世界中で開発競争が進む中、日本や中国の企業も独自の技術で注目を集めている。ここでは、住友電工をはじめとする代表的な3社を紹介する。
次世代電池の技術動向調査レポートを配布中!
▶︎資料(無料)を見てみる
住友電気工業株式会社(住友電工)
住友電気工業株式会社(住友電工)は、レドックスフロー電池の開発に約30年以上取り組んできた国内有数のメーカーである。同社は、出力変動の大きい再生可能エネルギーとの親和性の高い蓄電技術として本電池に着目し、数多くの実証・納入実績を重ねてきた。2017年には台湾電力総合研究所に出力125kW・容量750kWhのレドックスフロー電池を納入し、需給調整と自立運転の実証に貢献した。さらに2022年4月には、北海道電力ネットワークへ出力17MW・容量51MWhという大規模な系統用蓄電池を納入し、再エネ導入に伴う出力変動の抑制に活用されている。
大連融科儲能技術発展(Dalian Rongke Power)
大連融科儲能技術発展(Dalian Rongke Power)は、中国におけるバナジウム系レドックスフロー電池の分野で先駆的な企業である。同社は、中国科学院大連化学物理研究所と連携し、独自の全バナジウムレドックスフロー電池技術を実用化。
2022年には、約40万kWhの蓄電容量を持つ大連市の国家級エネルギー貯蔵実証プロジェクトにおいて試運転を開始し、同年6月に本格稼働に至った。この大規模設備は、再生可能エネルギーの有効活用と非常時の送電網支援を実現している。同社はその後も急成長を遂げ、2024年には大連市初のユニコーン企業となり、企業評価額は約92億元(約2,024億円)に達した。
株式会社LEシステム
株式会社LEシステムは、日本におけるバナジウムレドックスフロー電池(VRFB)用電解液の専門メーカーとして、1970年代から研究開発に取り組んでいる企業である。2023年12月にはRSテクノロジーズの完全子会社となり、グローバル展開と電池メーカーとの連携を本格化させた。2025年1月中旬には、スペインの発電所向けにVRFB用電解液を大規模出荷し、タンク507本、蓄電容量約8.5MWhという日本企業初の規模を達成。この出荷実績は、国際市場における同社の技術力と供給能力の高さを示す事例となっている。
レドックスフロー電池の今後と将来性
レドックスフロー電池は、再生可能エネルギーの普及に伴って注目を集めている定置型蓄電技術であり、太陽光や風力といった発電量が変動する電源と組み合わせることで、電力インフラの安定化に貢献する可能性を秘めている。特に長寿命や高い安全性、柔軟な容量拡張性などの利点から、大規模なエネルギー貯蔵用途に適しているとされている。
しかしながら、エネルギー密度の低さや導入コストの高さ、バナジウム資源の供給安定性、小型化の困難さといった課題も依然として解決が求められている。現在、国内外で大規模な実証実験や導入プロジェクトが進展しており、標準化や製造技術の確立といった取り組みが加速している。今後、これらの課題を克服できれば、レドックスフロー電池は持続可能な社会を実現する中核技術となり得るだろう。