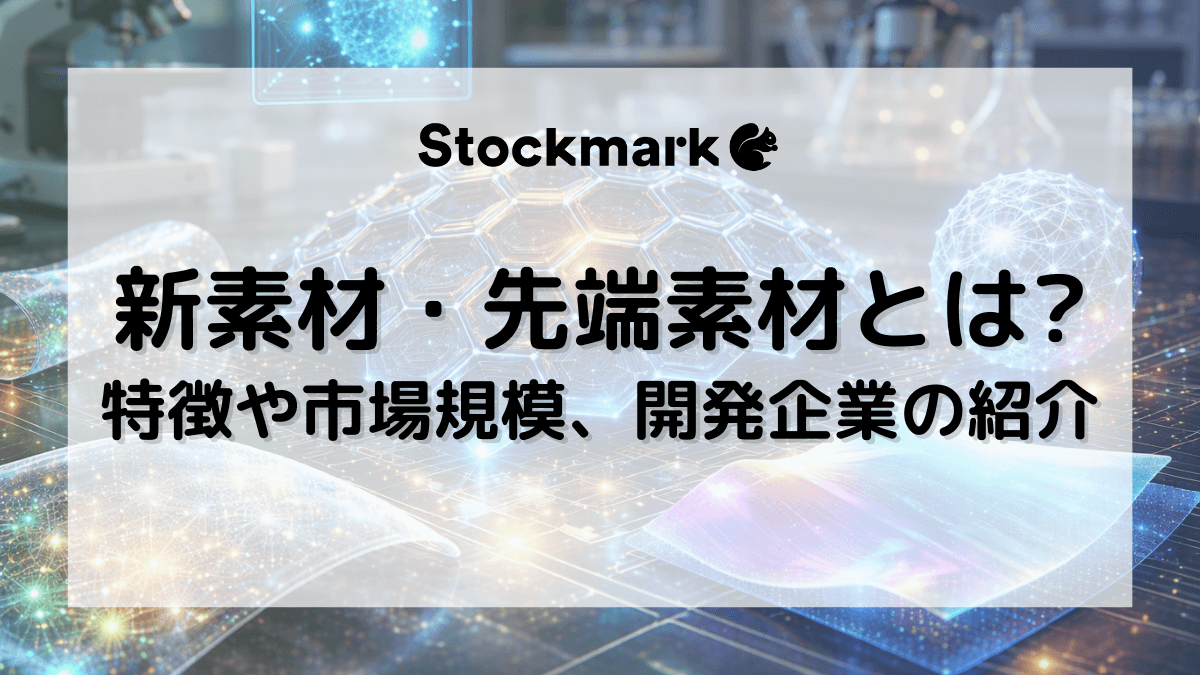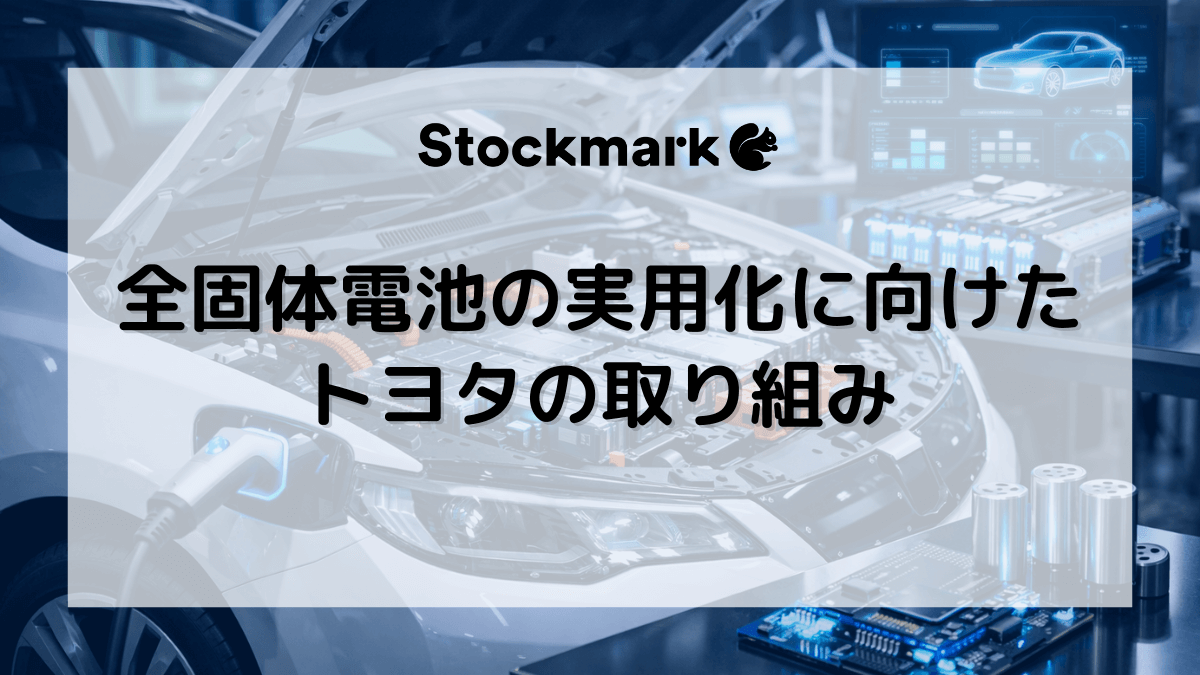省エネの実現やCO2排出削減の流れの中で、パワー半導体は欠かせない存在だ。パワー半導体とは、大きな電圧や電流を効率的に制御・変換できる半導体であり、エネルギーロスを最小限に抑える特性を持つ。産業機器や鉄道、電気自動車、再生可能エネルギー設備など幅広い分野で導入が進んでおり、特に電動化や高効率化が求められる現場での需要は急速に拡大している。
近年はSi(シリコン)に加え、SiC(シリコンカーバイド)やGaN(ガリウムナイトライド)といった次世代材料の採用も増え、高耐圧・高耐熱性能を活かした製品開発が活発化している。パワーデバイス市場は世界的にも成長を続け、技術革新や新用途の開拓が将来の競争力を左右する状況にある。
本記事では、パワー半導体の定義や特徴、種類、材料、用途、そして市場動向や課題についてわかりやすく解説する。
目次
「パワー半導体の最新動向レポート」を配布中!
▶︎資料を無料ダウンロード
パワー半導体(パワーデバイス)とは?
パワー半導体(パワーデバイス)とは、高電圧や大電流を効率的に制御・変換できる半導体を指し、電力の供給や変換を担う重要な役割を果たす。そもそも半導体とは、電気を通す導体と通さない絶縁体の中間的な性質を持つ物質であり、電流の流れを自在に制御できることから、トランジスタやIC(集積回路)などの電子部品の基礎材料となっている。
通常の半導体では、一定以上の電流や電圧がかかると熱暴走を起こし、素子や機器そのものを破損させる恐れがある。これに対し、パワー半導体は高耐圧・高耐熱構造を備え、電力のオン・オフを高速に切り替えるスイッチング動作によって電圧・電流の変換を行うため、エネルギーロスが極めて少ない。
従来、電流や電圧の制御は抵抗器によって行われていたが、抵抗による変換では熱として失われるエネルギーが多く、効率面で課題があった。パワー半導体はこうした課題を解決し、省エネルギー化や小型化、軽量化を可能にしている。用途は多岐にわたり、パソコンやスマートフォンなどの情報端末、テレビやエアコンといった家電製品、電気自動車や鉄道車両、再生可能エネルギー発電設備、さらには人工衛星や5G通信基地局など、高効率な電力変換が求められるあらゆる分野で採用が進んでいる。
アナログ半導体やロジック半導体との違い
パワー半導体は、高電圧や大電流の制御・変換を目的とした半導体であり、アナログ半導体やロジック半導体とは役割が大きく異なる。アナログ半導体は、温度や電圧、音声信号など連続的に変化するアナログ信号を処理するもので、センサーや増幅器、電源制御ICなどに使われる。一方、ロジック半導体は、0と1のデジタル信号を処理して論理演算や制御を行うもので、コンピュータやスマートフォンのCPU、メモリ制御回路などに用いられる。これらが情報や信号を処理する「頭脳」や「神経」に相当するのに対し、パワー半導体はモーターや発電装置、電源回路などで大きな電力を直接扱い、必要に応じて電圧・電流を変換して機器を駆動させる「筋肉」の役割を担う。
パワー半導体・アナログ半導体・ロジック半導体の違い
| 半導体の種類 | 主目的・役割 | 扱う信号・対象 |
|---|---|---|
| パワー半導体(パワーデバイス) | 高電圧・大電流の制御や変換を行い、電力を効率よくスイッチングする | 電力(電圧・電流)そのもの |
| アナログ半導体 | 連続量の信号を計測・変換・増幅して制御系に渡す | 電圧・電流・温度・音声などのアナログ信号 |
| ロジック半導体 | デジタル信号の論理演算・制御・情報処理を行う | 0/1のデジタル信号 |
「パワー半導体の最新動向レポート」を配布中!
▶︎資料を無料ダウンロード
パワー半導体の起源と歴史
パワー半導体の起源は明確ではないが、1874年にドイツの物理学者フェルディナント・ブラウンが半導体の整流作用を発見したことが最初とされている。この発見により、半導体が電流を一方向にのみ流す性質を持つことが明らかになり、後の応用研究の出発点となった。その後、1947年に米ベル研究所でジョン・バーディーンとウォルター・ブラッテンが世界初の点接触型トランジスタを発明し、翌年にはウィリアム・ショックレーがより安定したサンドウィッチ型トランジスタを開発した。
これらの発明は、電子機器の小型化・高性能化を一気に加速させ、半導体産業の急成長を促した。そして1957年、米ゼネラル・エレクトリック(GE)社がパワー半導体の代表格であるサイリスタを初めて商品化。これにより、高電圧・大電流を効率的に制御できる技術が産業界に広まり、モーター制御や電力変換装置など幅広い分野で応用が進んだ。
パワー半導体が注目される理由
パワー半導体が注目される最大の理由は、省エネルギー化と高効率な電力制御を同時に実現できる点だ。従来の電力変換では、多くのエネルギーが熱として失われていたが、パワー半導体はスイッチング動作により電力損失を大幅に低減できる。そのため、産業機器や家電、自動車、さらには再生可能エネルギー発電設備など、あらゆる分野で活用が広がっている。
特に電気自動車では、バッテリーからモーターへの効率的な電力供給や急速充電の実現に不可欠なデバイスとなっている。また、風力や太陽光発電では、不安定な発電出力を安定化させるためのインバータやコンバータに搭載され、再エネ普及の鍵を握っている。さらに、データセンターや5G基地局など膨大な電力を消費するインフラでも、エネルギーコスト削減やCO₂排出量低減のためにパワー半導体の導入が進んでいる。世界的な脱炭素化の流れと電動化の加速が相まって、その需要は今後も急拡大していくと考えられる。
「パワー半導体の最新動向レポート」を配布中!
▶︎資料を無料ダウンロード
パワー半導体の用途
パワー半導体の主な役割は、大きな電圧や電流を効率的に制御・変換することにあり、その中心となるのが電力スイッチングである。
直流電圧変換では、電気自動車のバッテリー電圧を走行や充電に最適化するなど、機器に応じた電圧供給を実現する。また、直流と交流の相互変換は、インバータや整流器を通じて太陽光発電の電力を送電網に接続したり、家庭用や産業用機器へ供給したりする際に不可欠である。さらに、交流の周波数変換を行うことで、モーターの回転数を低速から高速まで精密に制御でき、鉄道や産業機械、エアコンなどで省エネ運転や静音化に寄与する。
これらの機能によって、再生可能エネルギーの有効利用や電力ロス削減が可能となり、エネルギー効率の向上と環境負荷の低減に大きく貢献している。
| 役割 | 効果・目的 |
|---|---|
| 直流⇔交流変換 | 送電網接続・高効率電力変換 |
| 交流周波数変換 | 低速〜高速の精密制御、省エネ・静音化 |
| 直流電圧変換 | 最適電圧供給による高効率化・小型化 |
「パワー半導体の最新動向レポート」を配布中!
▶︎資料を無料ダウンロード
パワー半導体に用いられる材料
パワー半導体は用途や求められる性能によって素材が異なり、それぞれが特有の強みを持っている。ここでは代表的な4つの材料を紹介し、その特性や活用分野について解説する。
| 材料 | バンドギャップ (eV) | 絶縁破壊電界 (MV/cm) | 電子移動度 (cm²/Vs) | 熱伝導率 (W/cmK) |
|---|---|---|---|---|
| Si(シリコン) | 1.1 | 0.3 | 1,400 | 1.3 |
| SiC(4H-SiC) | 3.26 | 2.8 | 1,200 | 4.9 |
| GaN(ガリウムナイトライド) | 5 | 3.4 | 2,000 | 1.5 |
| ダイヤモンド | 5.47 | 10 < | 4,500 | 22 |
Si(シリコン)
Si(シリコン)は、パワー半導体において最も歴史が長く、現在でも広く使用されている材料である。シリコンは地殻中に豊富に存在し、資源的に入手しやすく、加工もしやすいという利点を持つ。また、化学的・物理的性質が安定しており、製造プロセスや品質管理のノウハウが長年蓄積されているため、信頼性の高い半導体素子を大量かつ低コストで供給できる。そのため、トランジスタやダイオード、MOSFETなど多くの基本的なパワー半導体デバイスに採用され、産業機器や家電、自動車など幅広い分野で利用されてきた。
しかし、シリコンは物理的な限界として、高耐圧や高温環境での動作ではスイッチング損失が大きくなりやすく、熱耐性も限定的である。そのため、近年では電動車や再生可能エネルギーシステムなど、より高効率で高耐久性が求められる用途では、炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)といった新素材への置き換えが進みつつある。
SiC(シリコンカーバイド)
SiC(シリコンカーバイド)は、炭化ケイ素とも呼ばれるワイドバンドギャップ半導体で、高耐圧・高温耐性・高周波特性・低損失性といった特性に優れている。これにより、高電圧・高出力が求められる電動車のインバーターや鉄道車両、産業用モーター、太陽光発電や風力発電のパワーコンディショナーなどで採用が拡大している。特にシリコンと比べて絶縁破壊電界が約10倍高く、動作温度も200℃近くまで耐えられるため、小型化と高効率化を同時に実現できる点が大きな強みだ。
しかし、SiCは硬く脆い性質を持ち、結晶成長やウエハ加工に高度な技術が必要となるため製造難易度が高く、結果として材料コストや製造コストが依然として高い。これらの課題を克服するため、世界各国で量産技術の改良や設備投資が進められており、今後は価格低下とともにさらなる普及が期待される。
GaN(ガリウムナイトライド)
GaN(ガリウムナイトライド)は、もともと青色LEDやレーザーダイオードなど光デバイスの材料として広く利用されてきた窒化ガリウムとも呼ばれるワイドバンドギャップ半導体だ。近年では高周波特性や低損失性を活かして電源回路や無線通信機器、高速充電器といった分野で採用が進んでいる。シリコンと比較してバンドギャップが広く、耐圧性能やスイッチング速度に優れるため、回路の小型化や高効率化を実現できる点が大きな利点である。
一方で、GaNは炭化ケイ素(SiC)と同様に製造難易度が高く、結晶成長や基板製造に特殊な技術が必要となることから、量産コストが依然として高い。また、長期信頼性や放熱設計といった実用化に向けた課題も残っており、現時点では一部の高性能用途に限られている。しかし、研究開発と製造技術の進歩により、今後は幅広いパワー半導体分野での利用拡大が期待される。
ダイヤモンド
ダイヤモンドは、理論的にはパワー半導体材料として最高クラスの性能を発揮できるとされる次世代素材だ。非常に広いバンドギャップ、高い熱伝導率、優れた耐電圧性を兼ね備えており、これまでのシリコンやSiC、GaNを大きく上回る特性を有する。このため、高電圧・大電流を扱う送配電システムや電気鉄道、再生可能エネルギーの変換装置、さらには電気自動車向けインバーターなどでの利用が期待されている。また、圧倒的な熱伝導性能により、高出力動作時でも発熱を効率的に逃がすことができ、冷却システムの小型化や省エネにも寄与する。
しかしながら、人工的に高品質なダイヤモンド単結晶を製造する技術はまだ発展途上であり、基板サイズの制限や加工コストの高さが実用化の障壁となっている。現在はCVD(化学気相成長)法などによる製造技術の改良が進められており、今後の量産化とコスト低減が進めば、パワー半導体材料の最有力候補として市場に広く普及する可能性が高い。
「パワー半導体の最新動向レポート」を配布中!
▶︎資料を無料ダウンロード
パワー半導体の種類
パワー半導体には用途や特性に応じて複数の代表的なタイプが存在する。以下では、その中から特に重要な三つを取り上げ、それぞれの仕組みや特徴、活用される分野について解説する。
サイリスタ
サイリスタは、直流と交流の間で電力をスイッチングし、精密な電流制御を行うための半導体素子だ。構造としてはアノード、カソード、ゲートと呼ばれる3つの端子を持ち、ゲートに信号を与えることで電流のオン・オフを制御する。
電流が一度流れ始めると、ゲート信号がなくてもアノードからカソードへの電流が継続する「ラッチ特性」を備えており、大電力を効率よく制御できるのが特徴だ。高耐圧・大電流に対応できるため、電力変換装置やモーター制御、鉄道の駆動システム、送配電設備など、産業分野で広く活用されている。また、発熱や損失を抑えられるため、省エネや長寿命化にも寄与する。ただし、高速スイッチングには不向きであり、用途によってはIGBTやMOSFETなど他のパワー半導体が選ばれることも多い。
パワートランジスタ(IGBTなど)
パワートランジスタは、電気信号の増幅やスイッチングを行う半導体素子であり、動作時に1W以上の電力を扱えるものを指す。高電圧・大電流を効率的に制御できるため、電源回路やモーター駆動、インバータ制御など幅広い用途に用いられている。
代表的な種類には、スイッチング損失が少なく高速動作に優れるパワーMOSFET、バイポーラトランジスタの高耐圧性能とMOSFETの高速スイッチング特性を併せ持つIGBT、そして従来から大電流制御に利用されるバイポーラトランジスタがある。特にIGBTは、高耐圧と低損失を両立しやすいため、鉄道車両や産業用モーター、大型インバータなどで広く採用されている。一方で、用途や条件によって最適な種類が異なるため、設計段階での選定が重要である。
ダイオード
ダイオードは、電気を一方向にのみ流す性質を持つ半導体素子であり、電流の逆流を防ぐ整流作用を基本機能とする。構造はP型半導体とN型半導体を接合した単純なもので、順方向では低い電圧で電流が流れる一方、逆方向ではほとんど電流を通さない。この特性を利用して、交流を直流に変換する整流回路や、信号から特定の成分を抽出する検波回路、電圧を安定化させる電圧制御、電流変換などの用途で広く使用されている。
パワー半導体分野では、高電圧や大電流に対応できるパワーダイオードが用いられ、発電所や産業用機械、電動車両の電源回路などで不可欠な役割を果たす。また、より高速なスイッチングが必要な場面ではショットキーバリアダイオードや高速回復ダイオードが採用され、効率向上や損失低減に貢献している。
パワー半導体の主な用途
パワー半導体は、私たちの生活や産業を支える幅広い分野で活躍している。ここでは、自動車や再生可能エネルギーなど、代表的な5つの用途について解説する。
自動車
自動車分野におけるパワー半導体は、電動パワートレインや回生ブレーキ、車載充電器などの主要部品で欠かせない役割を果たしている。特に電気自動車やハイブリッド車では、高電圧バッテリーとモーター間の電力変換を担い、効率的な加速や減速、エネルギー回収を実現する。さらに、パワー半導体は空調や電動パワーステアリングなどの補機類にも使用され、省エネ性能と信頼性向上に貢献している。近年ではSiCパワー半導体の採用が進み、長距離走行や急速充電への対応力が向上している。
再生可能エネルギー
再生可能エネルギー分野において、パワー半導体は発電された電力を効率的に変換・制御するための中核デバイスだ。太陽光発電では、パネルで生成された直流電力を交流に変換するインバータに用いられ、送電網への安定供給を可能にする。風力発電では、発電機の出力特性に応じて電圧や周波数を制御し、効率を最大化する役割を果たす。また、パワー半導体の高効率化はエネルギーロスを低減し、発電コスト削減にも直結する。近年はSiCやGaNの採用が進み、大容量化と高耐環境性が求められる設備に対応している。
産業機器・工場設備
産業機器や工場設備において、パワー半導体はモーター駆動や電力制御の効率化に欠かせない存在だ。工作機械や搬送装置では、インバータを介してモーターの回転数やトルクを精密に制御し、生産効率や製品品質の向上に寄与する。溶接機や産業用ロボットでは、高速かつ安定した電力供給を実現し、作業の精度や安全性を高めている。また、大規模プラントでは、送配電システムや無停電電源装置(UPS)に組み込まれ、設備の安定稼働を支えている。近年は省エネやCO₂削減の観点から、SiCやGaNを用いた高効率パワー半導体への置き換えも進んでいる。
鉄道・電車
鉄道や電車において、パワー半導体は駆動システムや電力変換装置の要となる部品だ。車両のモーター制御には、交流と直流の変換や電圧・電流の調整が不可欠であり、インバータやコンバータに搭載されたパワー半導体がこれを担っている。これにより、発進から高速走行まで滑らかな加速や減速が可能となり、エネルギー効率も向上する。また、回生ブレーキと組み合わせることで、減速時の運動エネルギーを電力として回収し再利用でき、省エネ効果が高まる。さらに、高耐圧・高効率なSiCパワー半導体の採用により、装置の小型軽量化やメンテナンス性の向上も進んでいる。
情報通信機器・データセンター
情報通信機器やデータセンターにおいて、パワー半導体は安定した電力供給と高効率な電力変換を実現する中核部品である。基地局や光通信装置では、電源回路に用いることで信号処理機器へ必要な電圧や電流を安定的に供給し、通信品質の維持に貢献している。データセンターでは、膨大なサーバ群を稼働させるために大規模な電力が必要となるが、パワー半導体を搭載した電源ユニットや無停電電源装置(UPS)により、変換ロスを抑えて電力コストを削減し、同時に発熱量の低減も実現する。これにより冷却負荷が軽減され、省エネと安定稼働の両立が可能となっている。
「パワー半導体の最新動向レポート」を配布中!
▶︎資料を無料ダウンロード
パワー半導体の市場規模と動向
1980年代後半、日本は「日の丸半導体」と称され、世界の半導体市場で圧倒的な存在感を誇っていた。総務省の調査によれば、1988年時点で世界シェアは50.3%と首位に立ち、2位のアメリカ(36.8%)を大きく引き離していた。しかし1990年代以降、韓国やアメリカの台頭とともに日本のシェアは低下し、2019年には10%まで落ち込んでいる。かつてのシェアを取り戻すことは難しいとみられるが、パワー半導体分野においては依然として日本企業が強い存在感を示している。
2021年のOmdia調査では、世界トップ10メーカーに三菱電機、富士電機、東芝、ルネサスエレクトロニクス、ロームの5社がランクインしており、各社ともSiCパワー半導体の開発や量産体制の強化を進めている。
富士経済の調査によると、電気自動車需要の一時的な落ち込み、新型コロナウイルスによる工場停止、中国経済の減速などで2024年前半まで市場は低迷したが、同年後半から回復基調に入り、2025年には市場規模が5138億円に達すると予測されている。さらに、次世代パワー半導体の普及を見込み、2035年には市場全体で7兆7710億円、次世代パワー半導体だけでも3兆1981億円規模に拡大するとされ、日本企業にとって重要な成長領域となる見通しだ。
「パワー半導体の最新動向レポート」を配布中!
▶︎資料を無料ダウンロード
パワー半導体における課題
パワー半導体は、大きな電圧や電流を効率的に制御・変換するため、放熱性能の確保が不可欠であり、多くの機器にはヒートシンクや回転ファンが搭載されている。しかし、電子機器の小型化や高性能化が進む中で、こうした冷却部品を極力減らし、半導体自体の効率向上と小型化を実現することが求められている。現在主流のSi(シリコン)パワー半導体では、素材の限界から大幅な性能改善は難しいとされ、この課題を打破するためにSiC(炭化ケイ素)やGaN(窒化ガリウム)といった次世代パワー半導体が注目されている。
しかし、これらの新素材にも課題は残る。例えば、SiCやGaNデバイスでは「ゲート」と呼ばれる制御部に欠陥が生じやすく、信頼性確保が技術的ハードルとなっている。また、SiCパワー半導体の基板となるSiCウェーハは、世界的に供給企業が限られており、その上位シェアはすべて海外メーカーが占める。日本国内では十分な供給体制が整っておらず、材料調達リスクが依然として大きい。このため、製造コストの高さや供給安定性の確保も含め、技術開発とサプライチェーン構築の両面で課題解決が急務となっている。
「パワー半導体の最新動向レポート」を配布中!
▶︎資料を無料ダウンロード
パワー半導体を開発する企業やメーカー
パワー半導体分野では、日本企業が高い技術力を武器に世界市場で存在感を示している。ここでは、世界的評価を受ける代表的なメーカーを5つ紹介する。
三菱電機
三菱電機は、日本を代表する総合電機メーカーであり、パワー半導体分野において世界的な技術力と高い市場シェアを誇っている。特にIGBTモジュールの開発と量産においては世界トップクラスの実績を持ち、高耐圧・高電流対応を強みとして鉄道、産業機器、電気自動車など幅広い分野に製品を供給している。
また、次世代技術として注目されるSiCパワー半導体の開発にも早期から注力しており、2010年代初頭にはSiC-MOSFETやSiC-SBDの製品化を実現した。さらに、2013年には鉄道車両向けとして世界初となるフルSiCパワーモジュール搭載インバータシステムを商用運行させ、省エネルギー化や小型軽量化に大きく貢献している。同社は今後も生産能力の強化や新技術の開発を進め、次世代パワー半導体市場での存在感を一層高めていくとみられる。
ルネサスエレクトロニクス
ルネサスエレクトロニクスは、自動車向けマイコン分野で世界トップクラスのシェアを誇る半導体メーカーでありながら、近年はパワー半導体分野でも急速に存在感を高めている。2023年には閉鎖していた甲府工場を再稼働させ、炭化ケイ素(SiC)やシリコンベースのパワー半導体を対象とした300mmウェハ生産ラインの導入を発表し、翌年には本格稼働を開始した。
さらに、2024年にはGaNパワー半導体の分野で高い技術力を持つ米国Transphorm社を買収し、材料技術と製品ポートフォリオの拡充を図った。そして2025年7月には、新世代の650V GaN FETの量産を開始し、AIサーバ、電気自動車(EV)充電器、無停電電源装置(UPS)、再生可能エネルギー向けインバータなど、高効率かつ高信頼性を求められる用途に向けて製品提供を行っている。同社はこれらの取り組みにより、次世代パワー半導体市場での競争力を着実に強化している。
東芝
東芝は1960年代からシリコンパワー半導体の研究と製造を継続してきた老舗メーカーであり、その長年の経験を基礎にスーパージャンクション構造や高放熱パッケージといった高性能化技術を確立している。これらの技術は電力損失低減や耐久性向上に寄与し、産業機器や電力インフラ分野で広く活用されてきた。2000年代以降は、電気自動車や鉄道インバータ向けを中心にSiC MOSFETの開発を進め、耐高圧・高効率動作を可能にする製品群を拡充している。
さらに、次世代材料であるGaNの研究にも注力しており、2023年には第一世代のGaN-Siカスコード製品を市場投入。2024年には高速寄生発振を抑制する新技術を搭載したGaNパワーモジュールの試作にも成功している。これにより、東芝はシリコンからSiC、GaNに至る幅広い材料技術を活かし、多様な電力変換ニーズに応える体制を整えている。
富士電機
富士電機は、1923年の設立以来、発電・制御・電力変換技術を中核に据えた事業を展開し、長年にわたりパワーエレクトロニクス分野で高い技術力を培ってきた。1975年には世界に先駆けてパワートランジスタの量産を開始し、その後も産業機器や鉄道、エネルギー分野など幅広い用途向けにパワー半導体を供給してきた。2000年代に入ると、より高効率・高耐圧を実現する次世代デバイスとして炭化ケイ素(SiC)を用いたパワー半導体の研究開発を本格化。
製造プロセスやモジュール設計技術の高度化を進め、信頼性と性能を両立した製品を市場投入している。2024年にはデンソーと連携し、SiCパワー半導体の生産能力強化に向けた大規模投資を発表し、モジュール製造の量産体制を大幅に拡充。これにより、電気自動車や再生可能エネルギー向けインバータなど、急成長が見込まれる分野への安定供給体制を整えている。
ローム
ロームは1958年に設立された日本の半導体メーカーで、アナログICやディスクリート半導体に加え、次世代パワー半導体分野においても世界的に高い評価を得ている。特にSiC(炭化ケイ素)やGaN(窒化ガリウム)といった次世代材料を用いた製品開発に注力しており、2004年にはSiC MOSFETの試作に成功。2010年12月には世界初となるSiCトランジスタ「DMOSFET」の量産を開始し、業界に先駆けた量産体制を築いた。さらに2010年代には、低損失と高耐圧を両立するトレンチ構造のSiC-MOSFETや、1700V耐圧のSiC MOS内蔵AC/DCコンバータICなど、高性能デバイスを次々と開発している。
近年ではGaNパワー半導体の実用化にも取り組み、2025年3月にはマツダと共同で自動車部品への応用開発を開始。高効率化や小型化が求められる電気自動車や再生可能エネルギー分野に向けて、革新的な製品提供を進めている。
パワー半導体の今後と将来性
パワー半導体は、自動車、再生可能エネルギー、産業機器、データセンターなど幅広い分野で電力変換や制御を担う中核デバイスであり、省エネルギー化の実現に欠かせない存在である。近年は、Si(シリコン)に加え、SiC(炭化ケイ素)やGaN(窒化ガリウム)といった次世代材料が実用化され、従来よりも高効率・小型・高耐圧な製品が登場している。
さらに、酸化ガリウムやダイヤモンドといった新素材の研究も加速しており、産業界全体で技術革新が進行中だ。世界的な電力需要の増大や脱炭素化の流れを背景に、この市場は今後10年で大きな成長が見込まれる。本記事で得た基礎知識をさらに深め、市場の詳細な動向や企業戦略を把握するためには、ホワイトペーパー「『2025年 半導体の市場動向』お役立ち資料」の活用が有効だろう。