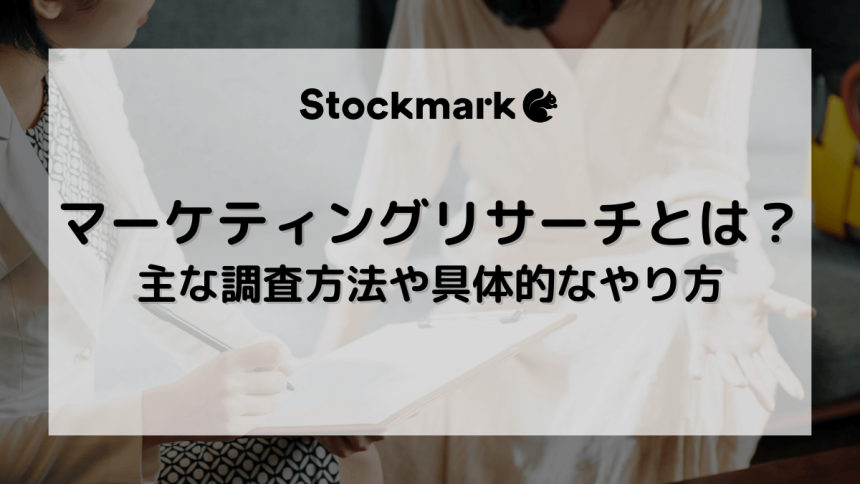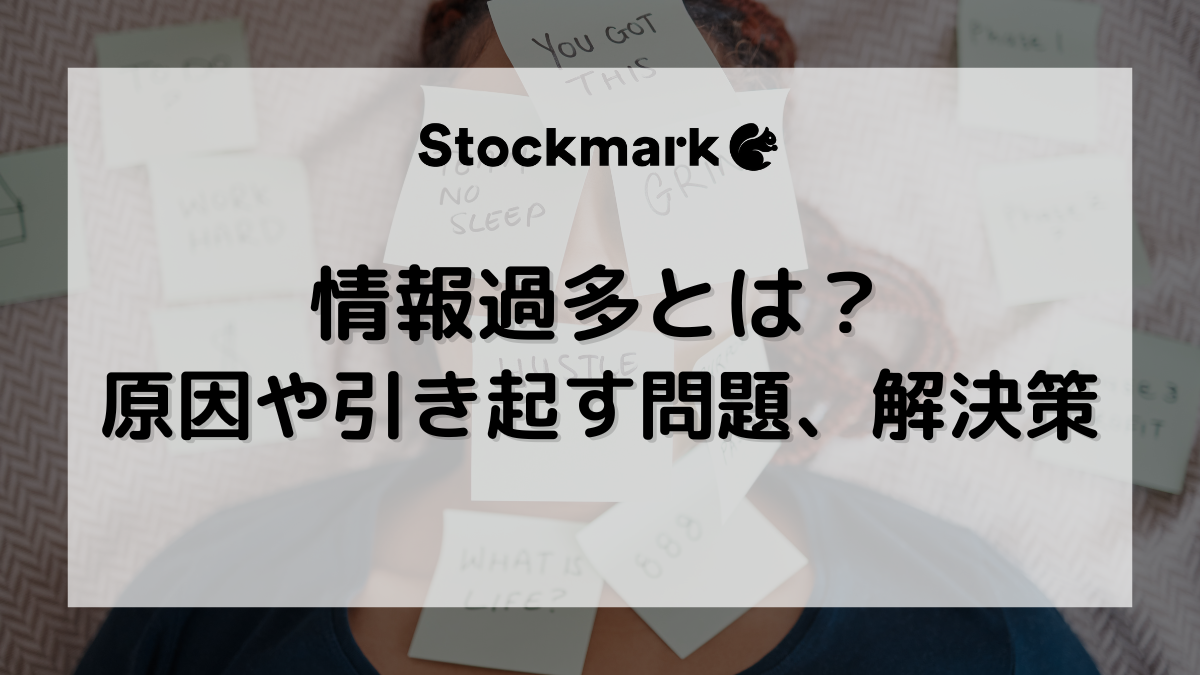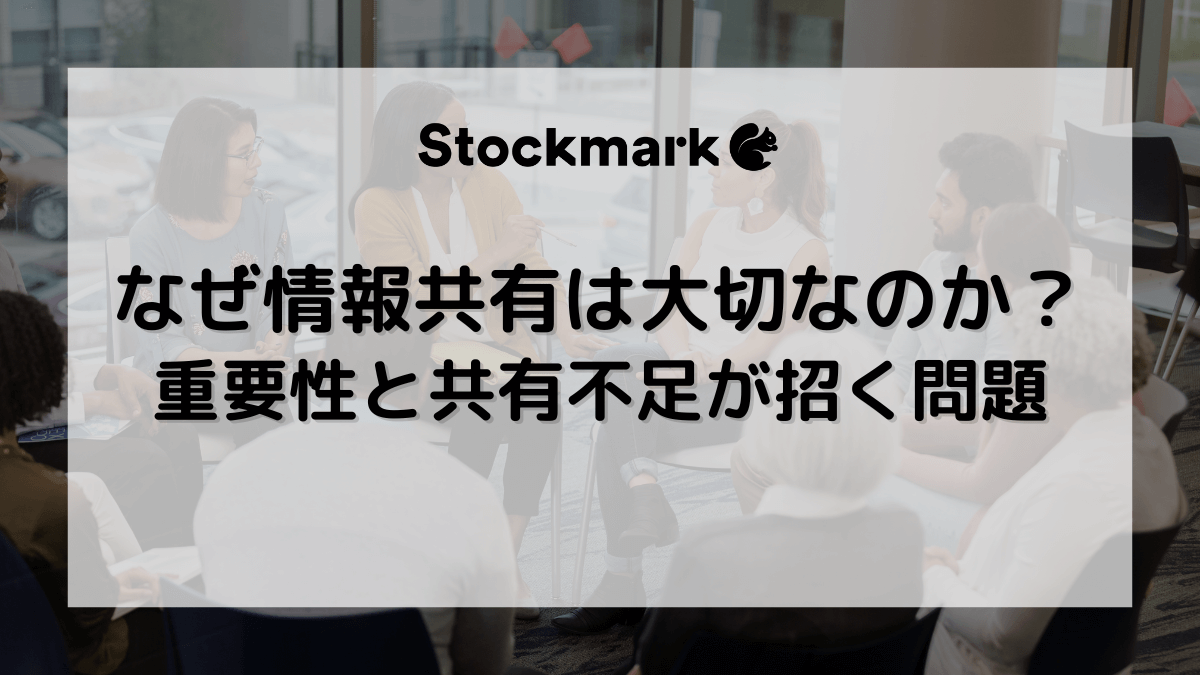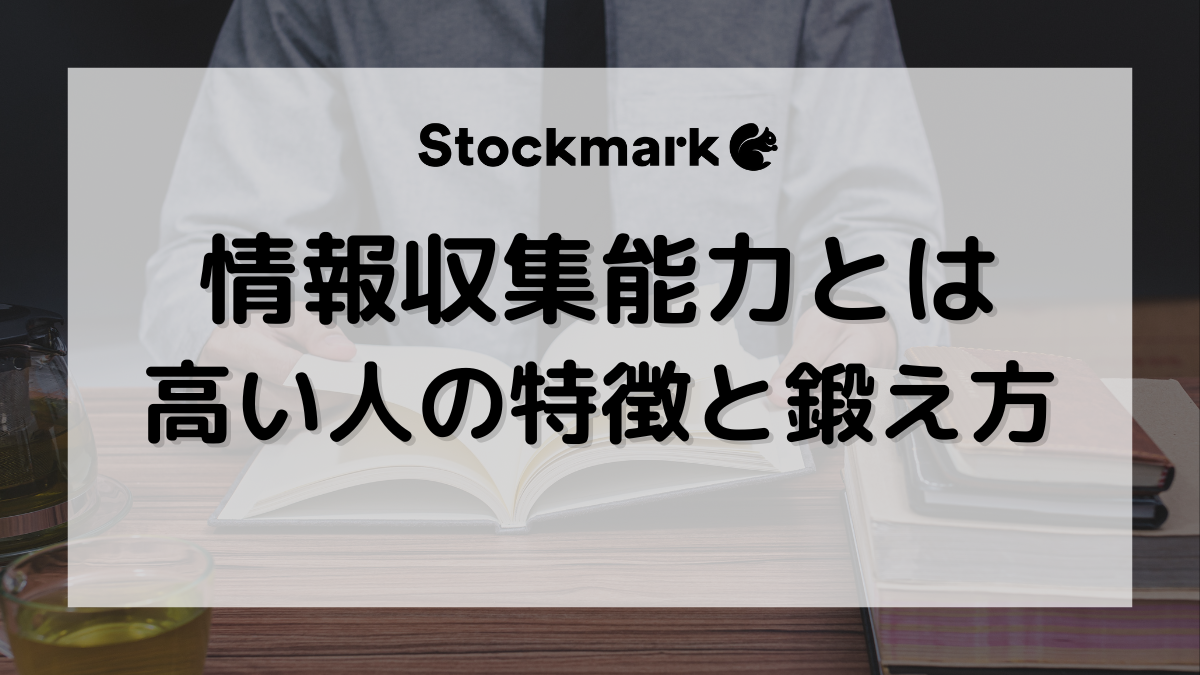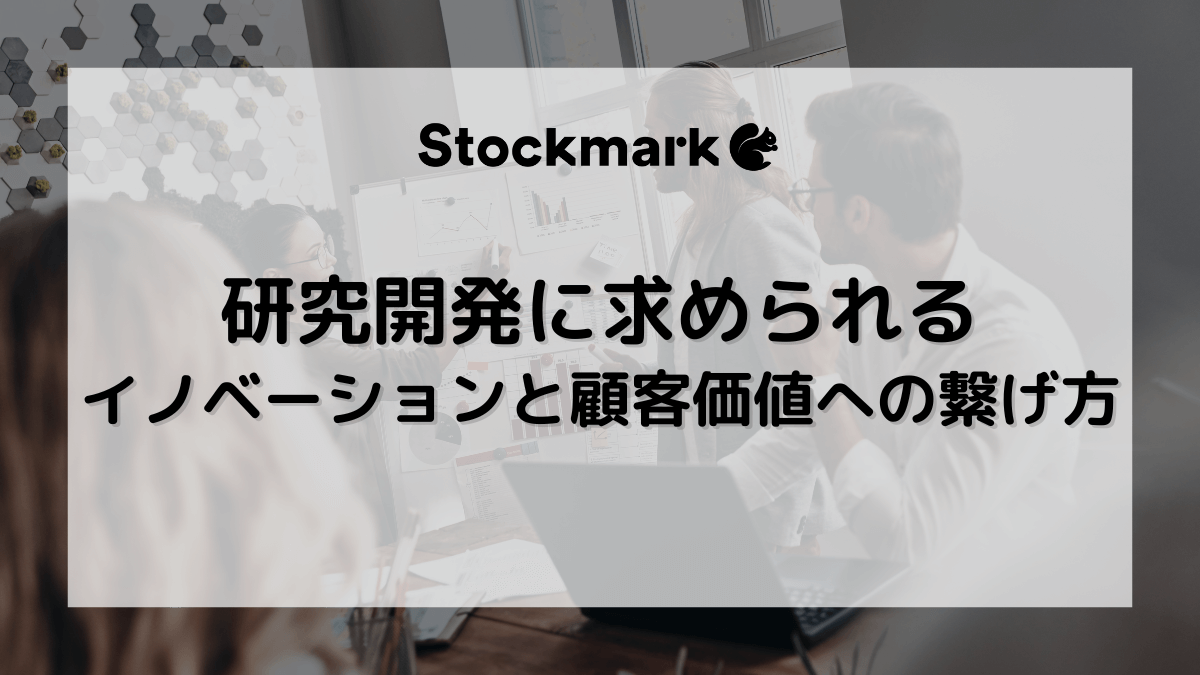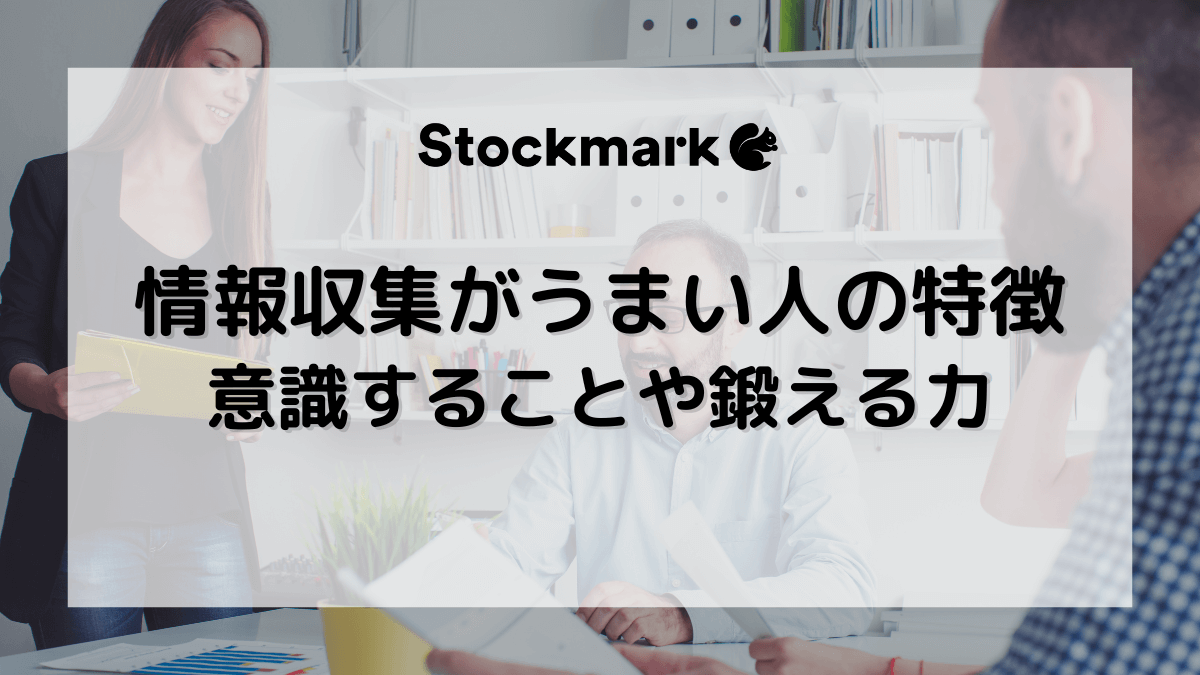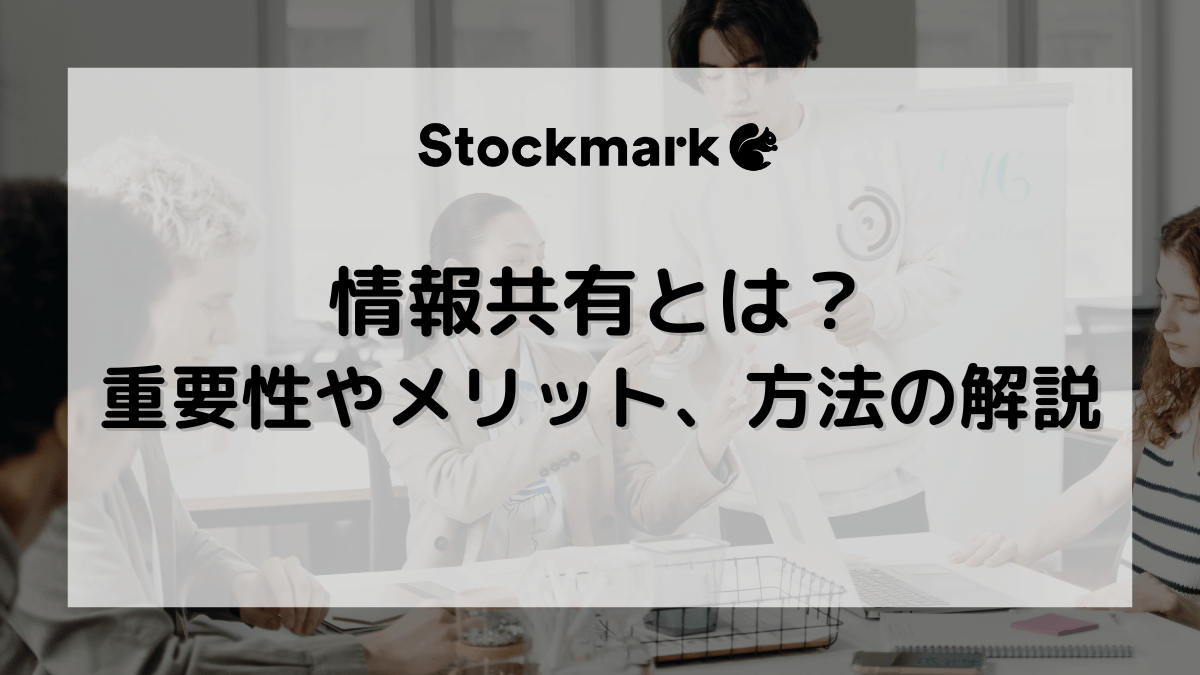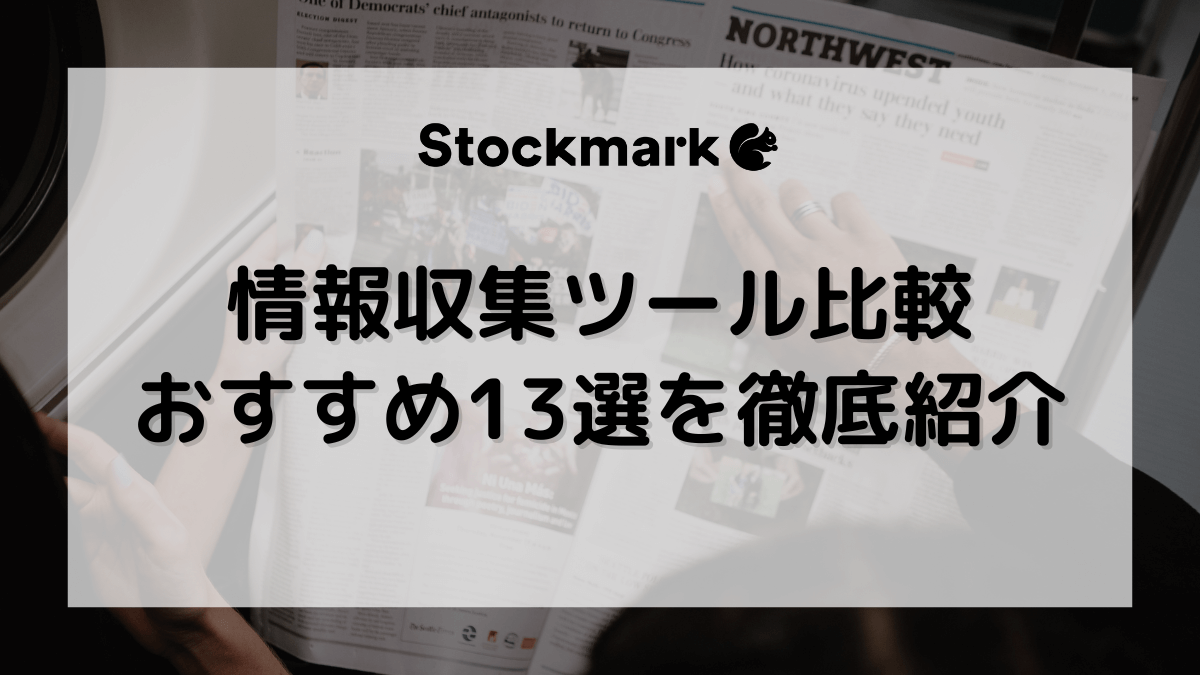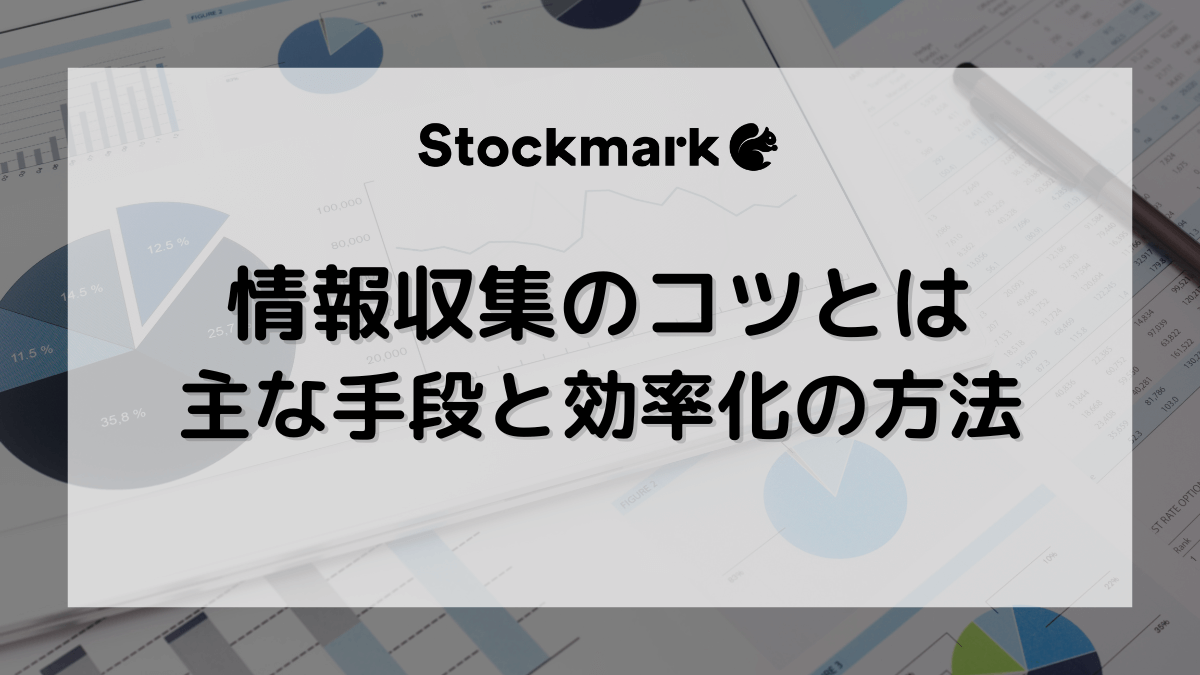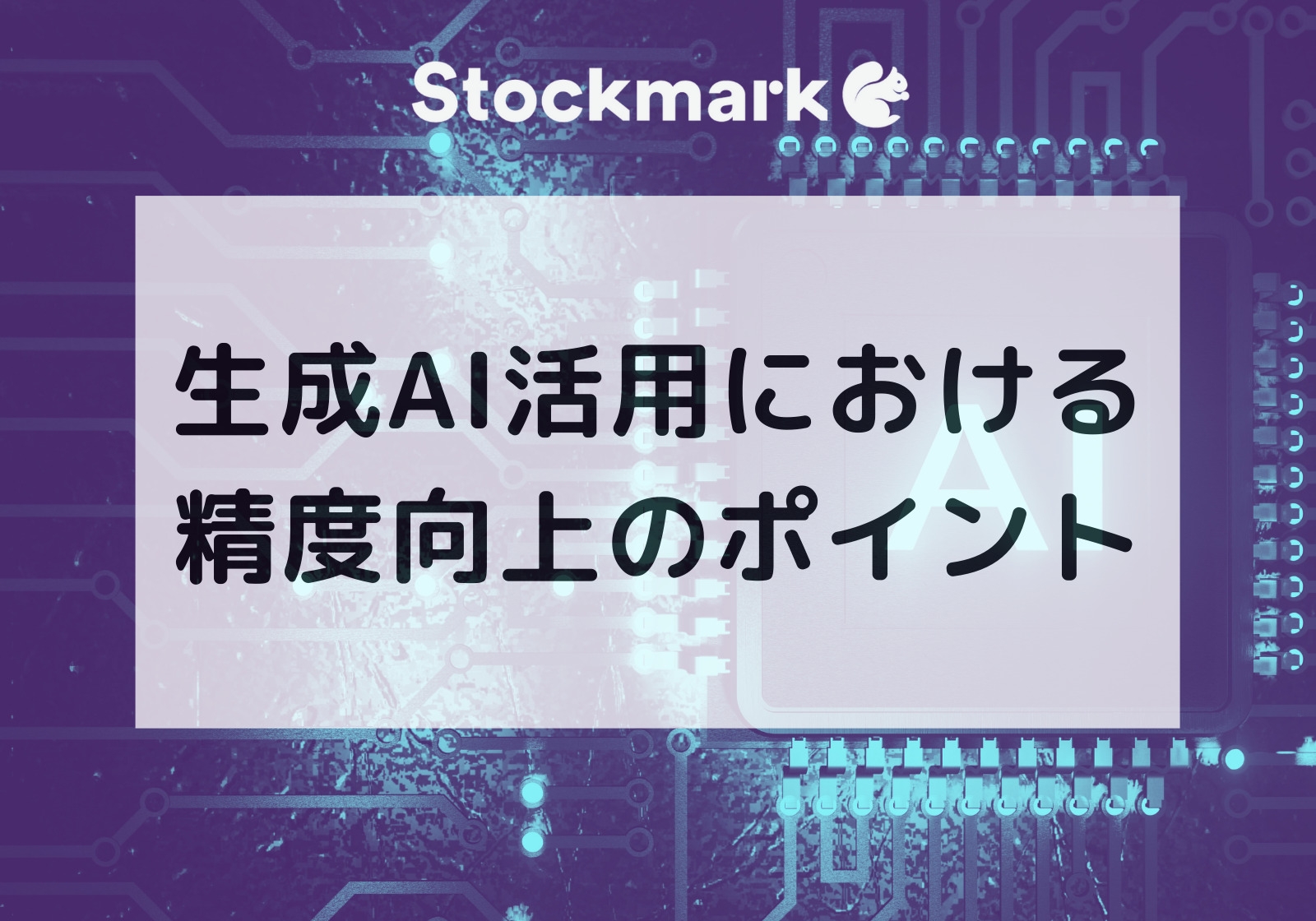マーケティングリサーチは、消費者の行動や市場の変化を把握し、商品開発や研究開発、さらには経営判断に役立てるための重要な調査活動だ。適切に活用することでリスクを軽減し、事業の成功可能性を高められる。
一方で、よく似た言葉にマーケットリサーチがあるが、こちらは市場規模や動向に焦点を当てる調査であり、マーケティングリサーチとは対象範囲に明確な違いがある。
本記事では両者の違いを整理しつつ、マーケティングリサーチの基本から具体的なやり方や手法までをわかりやすく解説する。また、調査を効果的に進めるための流れや実務でのポイントも紹介する。基礎知識を身につければ、自社の戦略立案や施策実行の精度を高め、競争力のある事業運営につなげることができるだろう。
目次
マーケティングリサーチとは?
マーケティングリサーチとは、市場や顧客の実態を理解するために体系的に情報を収集・分析する活動である。調査の対象は幅広く、市場規模や競合の動向、消費者の意識や購買行動、商品やサービスに対する評価、さらには広告やキャンペーンの効果測定まで含まれる。
これらのデータを活用することで、企業は新商品の開発や価格設定、販売戦略の立案、広告施策の改善といった重要な意思決定を勘に頼らず行うことができる。正確なリサーチは経営リスクの低減や競争力の強化につながり、現代のビジネスにおいて重要なプロセスとなっている。
マーケティングリサーチとマーケットリサーチの違い
マーケットリサーチは文字通り「市場調査」を意味し、市場規模や成長性、競合他社の状況、消費者層の特徴といった市場そのものを対象にした調査である。これに対してマーケティングリサーチはより広い概念であり、マーケットリサーチを包含しつつ、商品企画や販売チャネルの評価、広告やプロモーションの効果測定、さらには顧客満足度やブランドイメージの把握といった領域まで含む。

つまり、マーケットリサーチが市場の現状を理解するための一部の調査であるのに対し、マーケティングリサーチは企業が販売活動や顧客対応全般で正しい意思決定を行うための包括的な調査活動であり、ビジネス戦略全体に関わる取り組みとなる。
マーケティングリサーチのメリット・重要性
マーケティングリサーチには、企業が成長するために欠かせない利点がある。また、なぜ重要なのかも一緒に解説する。
顧客ニーズの把握
マーケティングリサーチを行う最大の意義の一つは、顧客ニーズを正確に把握できる点にある。顧客が求める商品やサービスの特徴や価値を理解すれば、開発段階から的確な企画が可能となり、市場投入後の失敗リスクを大幅に減らせる。逆にニーズを外すと顧客に選ばれず、競合に市場を奪われる可能性が高まる。
例えば、スマートフォンの市場では、利用者が重視するカメラ性能やバッテリー持ちの改善が購買行動に直結しているように、顧客の声を的確に捉えることが競争優位につながる。また、潜在的なニーズを探ることで、新しいサービスや市場の創出にも結び付けられる。顧客ニーズの把握は単なる調査結果ではなく、企業の戦略を左右するため重要だ。
顧客満足度の理解
マーケティングリサーチにおける2つ目のメリットは、顧客満足度を理解できることだ。調査を通じて顧客が商品やサービスにどの程度満足しているのかを把握できれば、提供価値の現状や改善点を明確にすることができるため、顧客満足度の理解は企業活動の根幹を支える重要な要素だといえる。
満足度が高い顧客はリピート購入を行いやすく、長期的な売上の安定につながるだけでなく、口コミや紹介を通じて新規顧客の獲得にも貢献する。一方、不満点や要望を明らかにすれば、商品改良やサービス改善に活かすことができ、競合との差別化を実現できる。
したがって顧客満足度を理解することは、単なる評価にとどまらず、企業が成長を続けるための戦略的な基盤となる。
意思決定や施策の精度向上
最後に、意思決定や施策の精度を高めるためにもマーケティングリサーチが重要となる。従来のように勘や経験だけに頼るのではなく、顧客の行動データや市場の動向、アンケートなどの調査結果を基に判断することで、商品企画や価格設定、広告施策を客観的かつ合理的に決定できる。
例えば、新商品の発売時に消費者が重視する機能や価格帯を事前に把握していれば、外れにくい戦略を立てられる。これにより間違った方向性に進むリスクを抑え、限られた資源を効率的に配分できる。また、リサーチを継続的に行うことで市場の変化を早期に察知し、柔軟に施策を修正できるため、競争の激しい環境でも優位性を保ちやすい。こうした精度の高い意思決定こそ、企業の成長に直結する。
マーケティングリサーチのデメリット・注意点
マーケティングリサーチが重要なのは言わずもがなだが、一方で注意点も存在する。ここでは、マーケティングリサーチを行うか否かを判断するために覚えておいていただきたいポイントを3つ紹介する。
時間がかかる
マーケティングリサーチは、調査対象の設定からデータ収集、結果の分析まで多段階を経るため、実施に時間がかかるため注意が必要だ。特に大規模なアンケートやインタビュー調査では、調査票の設計や対象者の選定、回収作業に長い期間を要し、数週間から数か月に及ぶ場合もある。
その間に市場環境や顧客ニーズが変化すると、せっかく得られた結果が古くなり、意思決定に役立たなくなるリスクが生じる。そのため、調査設計の段階で目的を明確にし、必要最低限の範囲に絞り込むことで、スピードと正確さのバランスを取ることが重要である。
費用の負担が大きい
また、マーケティングリサーチでは、調査の設計や実施、データの収集・分析に多くのコストがかかる点にも注意しなければならない。小規模であれば数十万円程度で実施できるが、数百人規模の調査では約100万から500万円程度にまで達することがあり、全国規模で数千人を対象とすると1000万円以上に膨らむこともある。
特に外部の調査会社に依頼する場合や、複雑な統計解析を伴う場合は費用が高額になりやすい。こうしたコストが予算を超えてしまうと、得られる成果に対して投資効果が薄れるリスクがあるため、調査の目的を明確にし、本当に必要な範囲に絞り込む工夫が重要である。
回答に偏りがある
最後の注意点は、マーケティングリサーチの結果が、必ずしも市場や顧客の実態を正確に反映するとは限らないことだ。例えば、インターネット調査ではデジタル機器に慣れた層が多く回答するため、高齢層やデジタルに不慣れな層の意見が十分に反映されないことがある。また、意識の高い顧客だけが回答に積極的な場合も偏ったデータにつながる。
さらに、質問文の表現や選択肢の提示方法、調査環境によっても回答が誘導され、実際の意識や行動と異なる結果が出ることがある。こうした偏りに気づかずに意思決定をすると市場や顧客の実態から外れた戦略を立ててしまい、施策が効果を発揮しにくくなる。
したがって、調査設計の段階で対象者のバランスを考え、質問文を中立的にするなどの工夫を行い、結果を解釈する際にも偏りの影響を十分に考慮することが重要だ。
マーケティングリサーチの主な調査方法
マーケティングリサーチにはいくつかの調査手法があり、それぞれ目的や状況に応じて使い分けられている。ここでは代表的な5つの方法を紹介する。
定量調査(量的調査)
定量調査(量的調査)は、データを数値として収集し、統計的に分析することで市場や顧客の傾向を把握する調査方法である。具体的には、アンケートで「満足度を1から5段階で評価する」といった形式で回答を集めることが多く、多数の人から同じ設問に基づいた情報を得るため、結果を比較したり予測に活用したりしやすい点が特徴である。
例えば、新商品の購入意欲を数値化することで市場規模を推定したり、広告効果を定量的に測定できる。これにより企業は勘や感覚に頼らず、客観的なデータに基づいた意思決定を行えるようになり、戦略の正確性と再現性を高められる。
定性調査(質的調査)
定性調査(質的調査)は、顧客の考え方や感情、行動の背景を深く理解するための調査方法である。数値で表すのではなく、言葉や態度から得られる情報を重視し、少人数を対象としたインタビューやグループディスカッション、観察などによって実施される。
例えば「なぜその商品を選んだのか」「購入後にどんな体験をしたのか」といった動機や価値観を探ることで、数値化だけでは見えない潜在的なニーズを把握できる点が大きな特徴である。数値データほどの汎用性はないが、新商品のアイデア創出やサービス改善の方向性を見出す上で有効なアプローチとなり、マーケティングリサーチにおいて重要な役割を果たしている。
アドホック調査
アドホック調査は、特定の課題や目的に応じて「一度限り」で実施される調査方法である。例えば、新商品の発売前に消費者がどのように受け止めるかを確認したり、特定の広告施策の効果を把握したりする場面で活用される。
定期的に行うトラッキング調査などとは異なり、その時々のニーズに応じて調査内容を柔軟に設計できる点が大きな特徴である。これにより状況に即した具体的で実践的な情報が得られる。一方で、時系列での比較や継続的な動向把握には適さないという限界もある。
そのため、アドホック調査は短期的な課題解決や施策の評価に向いており、マーケティング戦略の精度を高めるための手法といえる。
トラッキング調査
トラッキング調査は、同じ内容の質問を「定期的に繰り返し行う」ことで、時間の経過による顧客や市場の変化を把握する調査方法である。具体的には、顧客満足度やブランド認知度、購入意向などを継続的に測定し、施策の改善効果や市場の動向を確認するのに役立つ。
例えば、新しい広告キャンペーンの前後で認知度がどの程度変化したか、顧客満足度が改善しているかといった情報を数値として追える点が大きな強みである。これにより、企業は短期的な成果だけでなく、長期的な戦略や改善の方向性を判断できる。ただし、継続的な調査となるため、時間やコストがかかる点に注意が必要である。
パネル調査
パネル調査は、あらかじめ選ばれた特定の対象者(パネル)に継続的に調査を行い、同じ人々から時系列でデータを収集する方法である。この仕組みにより、消費者の購買習慣や意識の変化を追跡でき、新商品の導入前後での評価の違いや広告接触後の態度変化を把握するのに有効である。
例えば、ある家庭が定期的にどのブランドを購入しているかを追い続けることで、ブランドを想起する要因や広告効果を詳しく分析できる。長期的かつ一貫性のあるデータが得られる点が大きな利点である。一方で、対象者が調査に慣れてしまい回答が形式的になるリスクや、パネルの維持にコストがかかるという課題もある。
マーケティングリサーチの具体手法11選
マーケティングリサーチには状況に応じて使い分けられる多様な調査手法が存在する。ここでは実務で役立つ11の代表的な方法を紹介する。
インターネット調査
インターネット調査は、WEB上でアンケートを配布し、多数の回答を短期間で収集できる手法である。パソコンやスマートフォンから回答できるため全国規模での実施が容易で、費用も比較的低く抑えられる点が大きな特徴だ。
主に定量調査に適しており、満足度を数値で測定したり市場規模を把握したりするのに活用される。一方で、自由記述を取り入れることで定性調査としての要素も加えられる。また、調査設計に応じてアドホック調査、トラッキング調査、パネル調査のいずれにも活用可能であり、広告効果測定から継続的なブランド認知の追跡まで幅広い用途に対応できる。
ただし、インターネット利用者に偏るため、対象者選定やサンプルの質を担保する工夫が不可欠である。
ソーシャルリスニング
ソーシャルリスニングは、SNSや口コミサイト、掲示板などに投稿された消費者の声を収集・分析する調査方法である。専用ツールを用いて大量の投稿データを自動的に集め、頻出するキーワードや感情の傾向を解析することで、ブランドや商品の評判を可視化できる。
定性的には「なぜその評価につながったのか」を把握でき、定量的には投稿数やポジティブ・ネガティブ比率を測定できるため、双方の調査に適している。活用の仕方によって、新商品の発売直後に一度限りで実施するアドホック調査としても、長期的にブランドイメージや満足度の変化を追うトラッキング調査としても機能する。
加えて、炎上や不満の兆候を早期に発見できる点は、従来の調査にはない大きな強みでもある。
街頭調査
街頭調査は、人通りの多い駅前や商業施設周辺などで通行人に声をかけ、その場でアンケートやインタビューを行う調査方法である。質問票に記入してもらう形で数値データを収集すれば定量調査になり、試供品を体験して意見を自由に語ってもらえば定性調査として機能するため、両方に適している。
特に新商品の第一印象や広告デザインの評価など、短時間で幅広い生活者の生の声を集められる点が強みである。一方で、場所や時間帯によって対象者の属性が偏る可能性があり、全国的な傾向を把握するには限界がある。基本的には一度限りで実施されるアドホック調査として用いられることが多く、即時性と手軽さを活かして消費者のリアルな反応をつかむための手段である。
郵送調査
郵送調査は、調査票を郵送で配布し、回答者が自宅で記入して返送する形式の調査方法である。自宅で落ち着いて取り組めるため、長文の設問や記述式の質問にも対応でき、数量的なデータと質的な意見の双方を収集できる点が特徴である。
特に高齢層やインターネット利用が少ない層を対象とする場合に有効であり、地域や属性を絞ったリスト調査にも活用される。通常は特定の目的に応じて一度限りで行うアドホック調査として用いられるが、同じ母集団に繰り返し実施すればパネル調査やトラッキング調査としての活用も可能である。
ただし、回収に時間を要するだけでなく、回収率が低くなりがちな点や返送作業が回答者にとって負担になる点には注意が必要だ。
電話調査
電話調査は、調査員が対象者に直接電話をかけて質問に答えてもらう調査方法である。リアルタイムの会話を通じて回答を得られるため、不明点をその場で補足でき、回答の精度を高められる点が特徴である。比較的短時間で多様な層から情報を収集できることから、世論調査や顧客満足度調査、サービス利用実態の把握などに広く用いられている。
定量調査として多人数の意識や傾向を把握するのに適している一方で、自由回答を通じて定性調査的に意見を得ることも可能であり、両面に対応できる方法である。基本的にはアドホック調査として単発で行われることが多いが、同じ設問を継続的に繰り返すことでトラッキング調査やパネル調査としての活用も可能である。
ただし、近年は固定電話利用者の減少や応答率の低下により対象者の確保が難しく、調査対象の偏りが課題となっている。
訪問調査
訪問調査は、調査員が対象者の自宅や職場を訪れ、対面で質問に答えてもらう調査方法である。直接会って話を聞くことで回答の信頼性が高まり、さらに表情や態度からも補足的な情報を得られる点が特徴である。質問票を用いた聞き取りのほか、実際に製品を試してもらい、その感想を詳しく記録するなど、生活に密着した情報を収集できる。
世帯構成や購買習慣、生活実態の把握に有効であり、定量調査として数値を集めることも、定性調査として深い意見を引き出すことも可能である。多くは新商品の評価や生活行動の理解を目的としたアドホック調査として行われるが、同一対象者に繰り返すことでパネル調査としても機能する。
ただし、訪問には時間や費用が大きくかかり、対象者の協力が不可欠であるため、実施には計画性と効率性が求められる。
会場調査
会場調査は、あらかじめ設定された会場に対象者を集め、その場で商品や広告を体験してもらいながら意見を収集する方法である。統一された条件で複数の対象者から短時間にデータを得られるため、新商品の味やデザインの評価、広告素材やパッケージの比較検討などに適している。
アンケート形式を用いれば数値データが得られ定量調査として活用でき、インタビュー形式で意見を深掘りすれば定性調査にもなるため、両方に対応できる柔軟性がある。多くは発売前の商品や施策を対象とするアドホック調査として利用されるが、同じ形式を繰り返せばトラッキング調査としても有効である。
ただし会場まで足を運べる人が中心となるため、地域や属性に偏りが出やすい点や、参加者の募集コストがかかる点に注意が必要だといえる。
覆面調査(ミステリーショッパー)
覆面調査(ミステリーショッパー)は、調査員が一般客を装い実際に店舗やサービスを利用し、その体験を通じて接客態度や商品提供の質、店内環境などを評価する方法である。現場の従業員には調査であることを知らせず、通常の顧客と同じ状況で行うため、現実に近いサービス品質を確認できる点が大きな特徴である。
得られる情報は、数値化した評価項目として整理すれば定量調査となり、調査員の自由記述や体験談で判断すれば定性調査としても活用できるため、両方に向いている。多くの場合は特定店舗やサービス改善を目的としたアドホック調査として実施されるが、定期的に同じ基準で行えばトラッキング調査の一環としても機能する。
特に小売業や飲食業、金融、ホテルなど顧客対応が重要な業種で利用され、企業がサービス品質を客観的に見直すための有効な手段となっている。
デプスインタビュー
デプスインタビューは、調査員が対象者と1対1で深く対話し、その人の考え方や行動の背景にある価値観や心理を掘り下げる調査方法である。形式的なアンケートでは引き出しにくい本音や潜在的なニーズを把握できる点が大きな特徴で、1〜2時間にわたる詳細な聞き取りを通じて豊富な質的データが得られる。
特に新商品の開発や改善、ブランドイメージの理解、購買動機の解明に役立つため、企業にとって重要な意思決定の材料となる。定量化には向かず、主に定性調査の一種として扱われるが、その自由度の高さから調査目的に応じて柔軟に設計できる。
多くは一度限りの課題解決を目的とするアドホック調査として実施されるが、複数回行えば継続的な比較にも応用可能である。顧客心理の奥深くを理解するための有効なアプローチだといえる。
グループインタビュー
グループインタビューは、6〜8人程度の参加者を一堂に集め、調査員であるモデレーターの進行のもとで自由に意見交換してもらう調査方法である。参加者同士の会話から相互に刺激が生まれ、一人では出てこない新しい発想や気づきを引き出せる点が特徴である。
具体的には、新商品の第一印象やサービス改善点、広告やパッケージの評価を探る場面で用いられることが多い。数値データを得る定量調査には不向きであり、消費者の本音や価値観を探る定性調査に適している。また、目的ごとに内容を設計して行うアドホック調査として活用されることが一般的である。
効率的に多様な意見を集められるため、商品開発の初期段階やアイデア検討の方向性確認において有効な手法だ。
参与観察
参与観察は、調査員が対象者の生活や活動に実際に加わり、行動や習慣を直接観察することでデータを得る調査方法である。単なるアンケートやインタビューでは見えにくい無意識の行動や習慣を把握できるのが大きな特徴である。
例えば、家庭での家電の使い方を共に体験しながら記録したり、店舗での買い物行動を同行して観察することで、本人も気づいていない不満や潜在的なニーズを明らかにできる。これは数値データを集める定量調査ではなく、行動や意識の背景を深掘りする定性調査に適している。
調査の内容は課題や目的に応じて一度限り設計されるため、アドホック調査として行われることが多い。生活実態を深く理解し、新商品開発やサービス改善に役立つ有効な手法である。
マーケティングリサーチの流れ
効果的なマーケティングリサーチを行うには、明確な手順を踏むことが欠かせない。ここでは目的設定から調査の実施、分析までの5つのステップを紹介する。
目的や課題を明確にする
マーケティングリサーチのステップ1は、目的や課題を明確にすることである。調査を始める前に「何を知りたいのか」「その情報をどのような意思決定に活かすのか」を具体的に定めることで、調査の設計全体がぶれずに進められる。
例えば、新商品のターゲット層を把握したいのか、既存顧客の満足度を確認したいのかによって、適切な調査手法や対象者の設定は大きく変わる。目的が明確であれば必要な情報だけを効率的に集められる一方、曖昧なままでは集めたデータを有効に活用できず、時間や費用を無駄にするリスクが高まる。
そのためリサーチの前提として、経営戦略や施策の中でどの部分を改善したいのかを丁寧に整理し、調査のゴールを共有することが重要である。
調査対象を設定する
マーケティングリサーチのステップ2は、調査対象を設定することである。これは「誰に」「どの層」に調査を行うのかを明確に定める作業であり、調査の成否を左右する重要な工程だ。例えば、20代女性や既存顧客、競合製品の利用者といった具体的な対象を設定することで、必要な情報を正確に得ることができる。
対象を曖昧にすると、集まるデータが偏ったり、実際の課題と結びつかず活用できない恐れがある。また、対象の規模や属性を適切に選定することで、統計的な信頼性も高まり、調査結果の再現性が確保される。企業が効果的に意思決定に役立つデータを得るためには、調査対象の設定を緻密に行うことが欠かせない。
対象にあわせた調査手法を選ぶ
マーケティングリサーチのステップ3は、対象にあわせた調査手法を選ぶことである。これは調べたい相手の属性や状況に応じて最適な方法を使い分ける工程であり、調査の精度を左右する。例えば、高齢者層には郵送調査が適しており、落ち着いた環境で回答できるため詳細な意見が得やすい。一方で若年層にはインターネット調査が効果的で、スマートフォンを通じて短時間で多くの回答を集められる。
さらに、購買動機の深掘りが必要な場合はデプスインタビューやグループインタビューが適しており、定性的な理解につながる。このように対象ごとに適した手法を選ばなければ、回答が集まらなかったり偏ったりして結果の信頼性が損なわれる。そのため調査目的と対象をふまえ、適切な手法を選ぶことが正しいデータ収集につながり、効果的な意思決定の基盤となる。
調査実施
マーケティングリサーチのステップ4は「調査実施」であり、設計した計画に基づき実際にアンケートやインタビュー、観察などを行いデータを収集する段階である。ここでは対象者に適切に協力してもらい、できるだけ偏りのない情報を得ることが重要である。
そのため質問内容や説明は分かりやすく、一貫性を持たせる必要がある。また回答者を誘導するような表現は避け、客観的な意見が得られるよう工夫しなければならない。さらに、プライバシー保護や倫理的配慮を徹底し、回答者が安心して参加できる環境を整えることも欠かせない。
データの集計と分析
最後は、データの集計と分析だ。調査で得られた回答や記録を整理し、数値化や分類を通じて傾向や特徴を把握する段階である。アンケート結果はクロス集計や平均値算出などの統計手法を用いてまとめられ、グラフや表を通じて全体像を視覚的に理解できるようにすると良い。
また、自由記述の内容をテーマごとに分類すれば、数値だけでは見えにくい背景も把握できる。重要なのは、入力や計算の誤りを避け、データの偏りや限界を考慮したうえで結論を導くことである。なお、分析結果を実際の戦略や施策に活かすことが本来の目的であり、単なる数字の整理にとどめず、改善点や新しい方向性を見出すことが求められる。
まとめ
マーケティングリサーチは市場や顧客の実態を正しく理解し、企業の意思決定を支える重要な取り組みである。新商品の開発や研究開発にとどまらず、顧客満足度やリピート率の向上、既存製品の改善にも役立つ点が大きな価値である。
一方で、大規模な調査を実施すれば設計や回収、分析に多大なコストと時間が必要となり、場合によっては結果が古くなるリスクもある。そのため、調査の目的を絞り、適切な規模や方法を選ぶことが欠かせない。
また、マーケティングリサーチは市場や顧客に焦点を当てるが、競合他社の動向や業界のトレンド、さらには地政学的な影響といった外部環境の情報も併せて収集することで、より精度の高い戦略立案が可能になる。単なるデータ収集に終わらせず、得られた知見を経営判断や施策に活用することが、成果を最大化するための鍵である。
Aconnectは、AIを活用し社内外に存在する膨大なテキスト情報を自動で収集・整理・要約する情報収集ツールである。市場動向、業界ニュース、競合情報などを一元管理し、検索や分析を迅速に行えるため、情報活用のスピードを大幅に向上可能だ。まずは無料トライアルでお試しいただきたい。