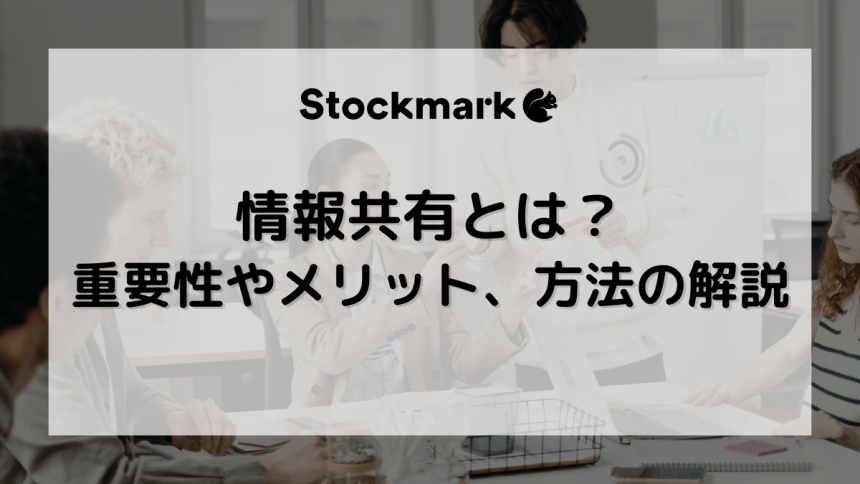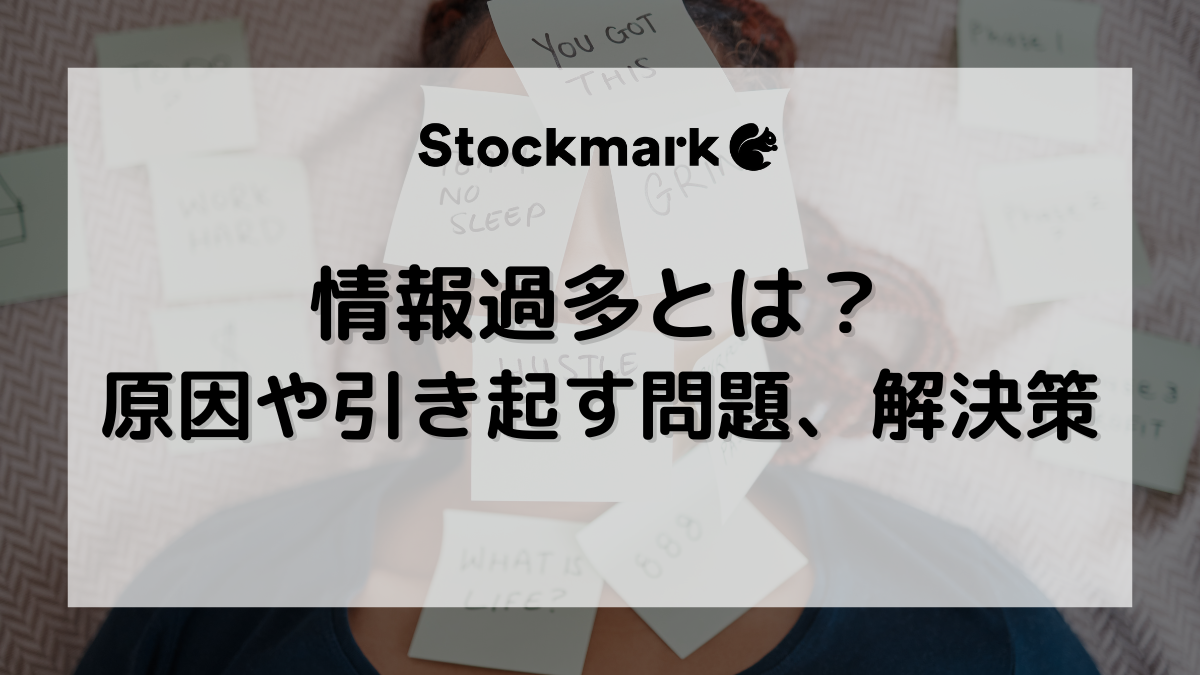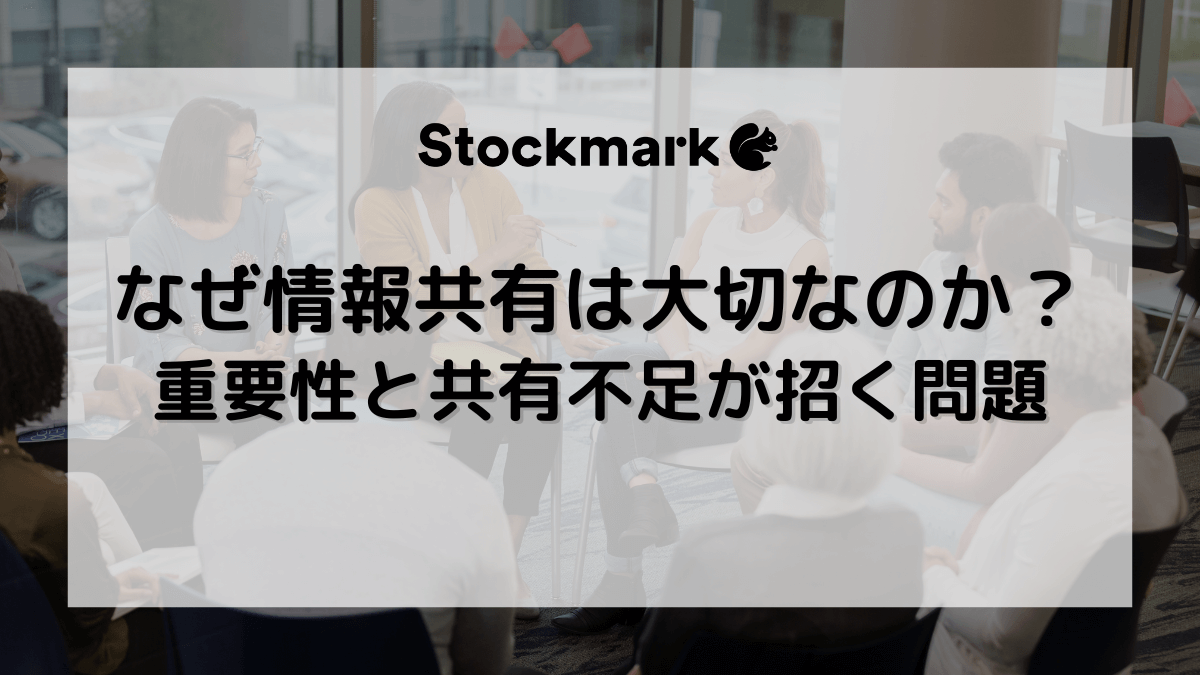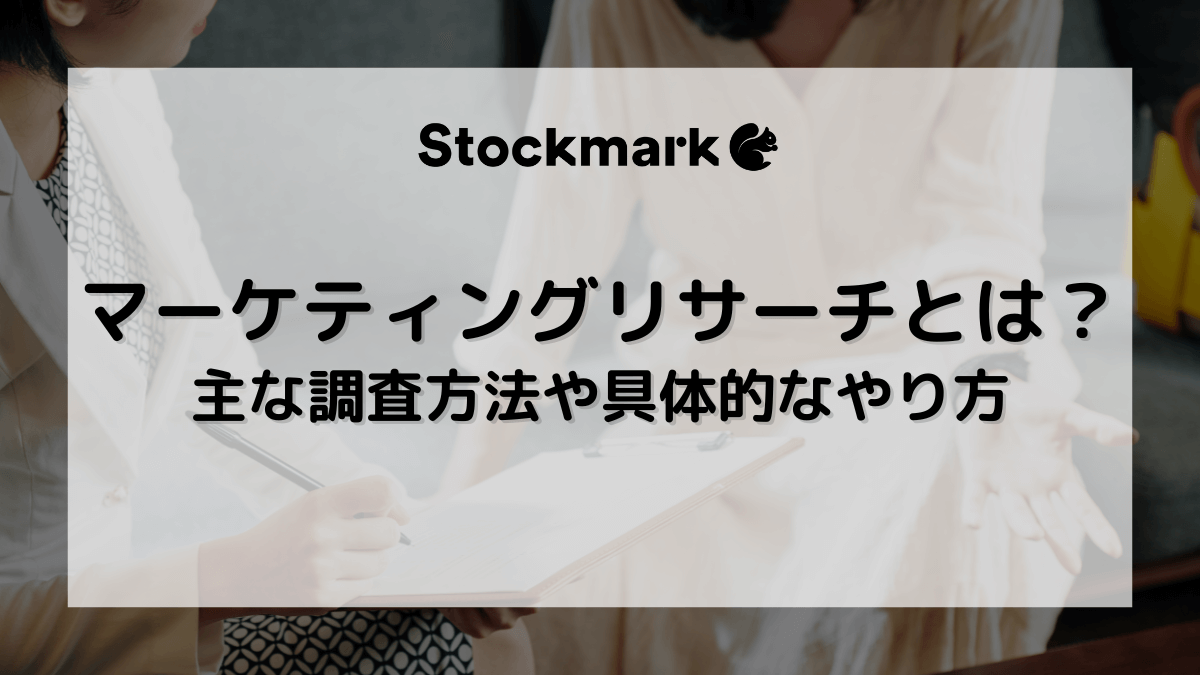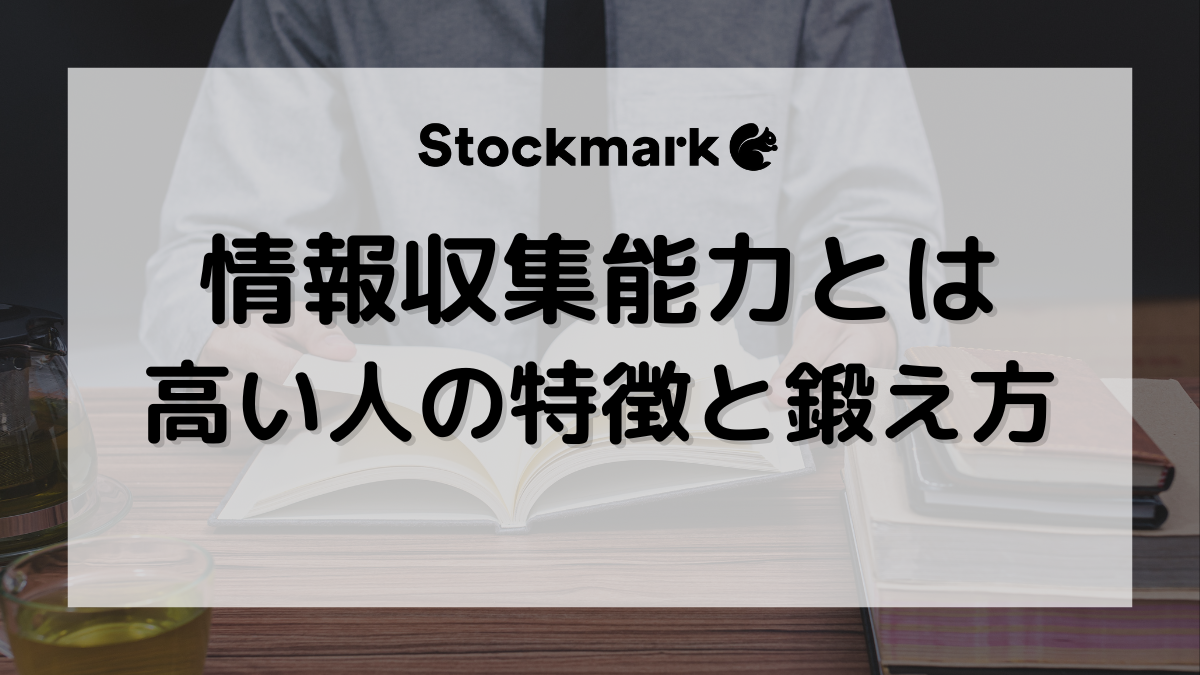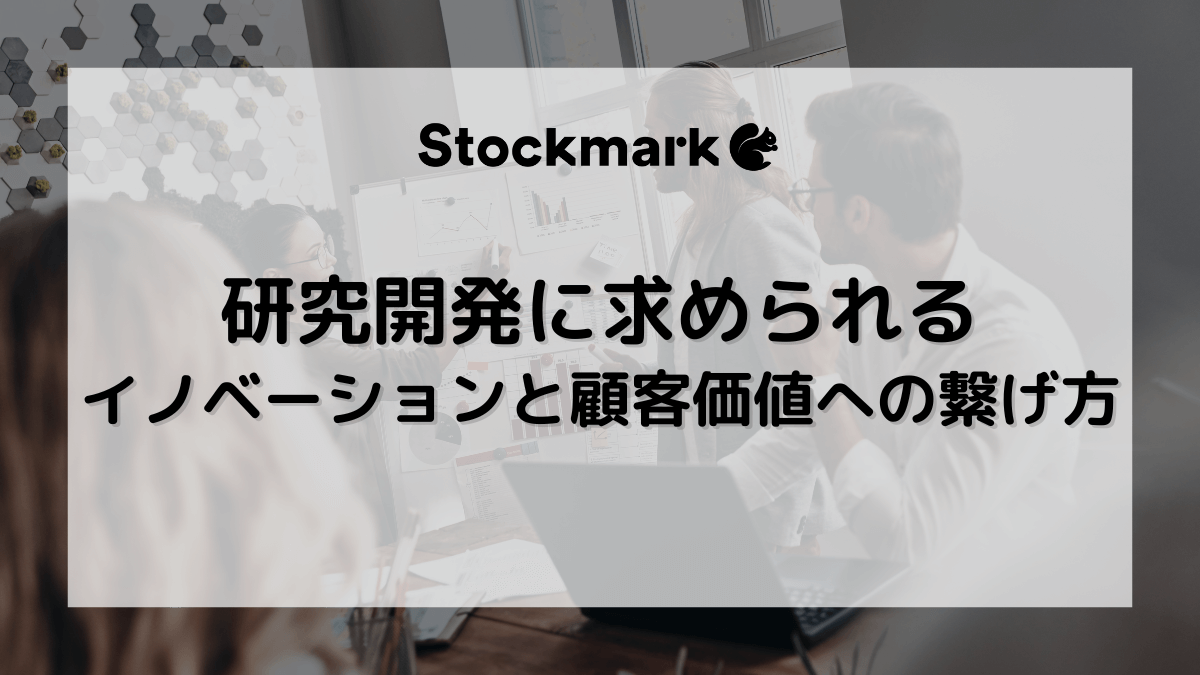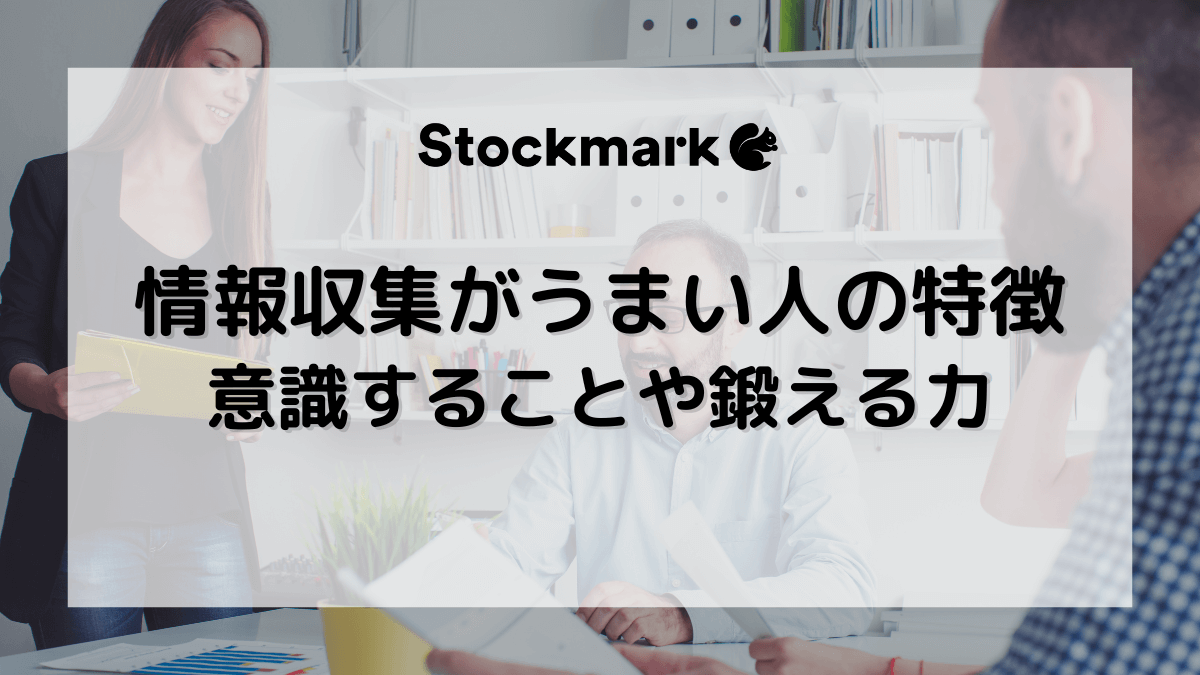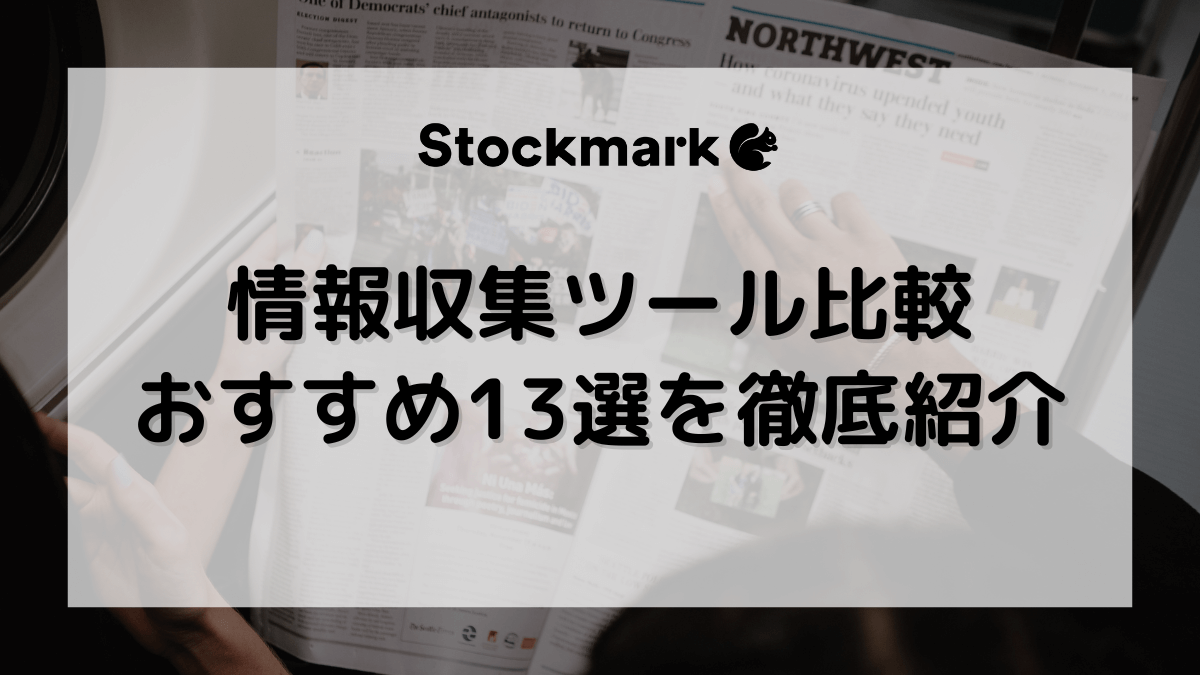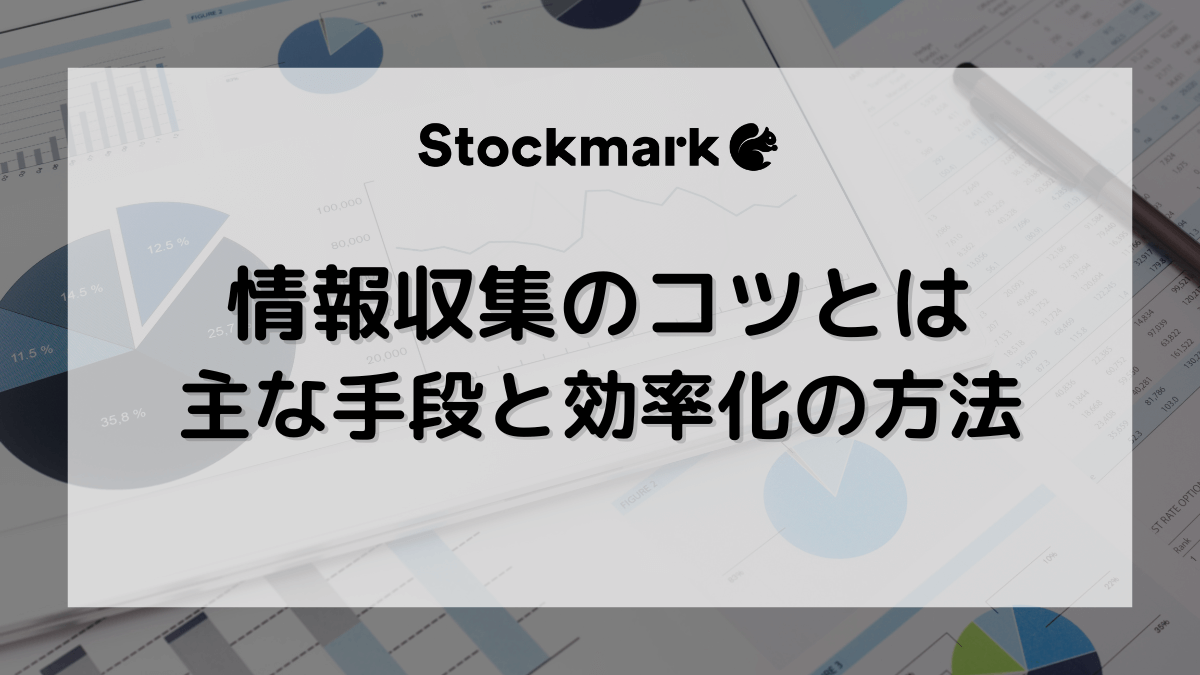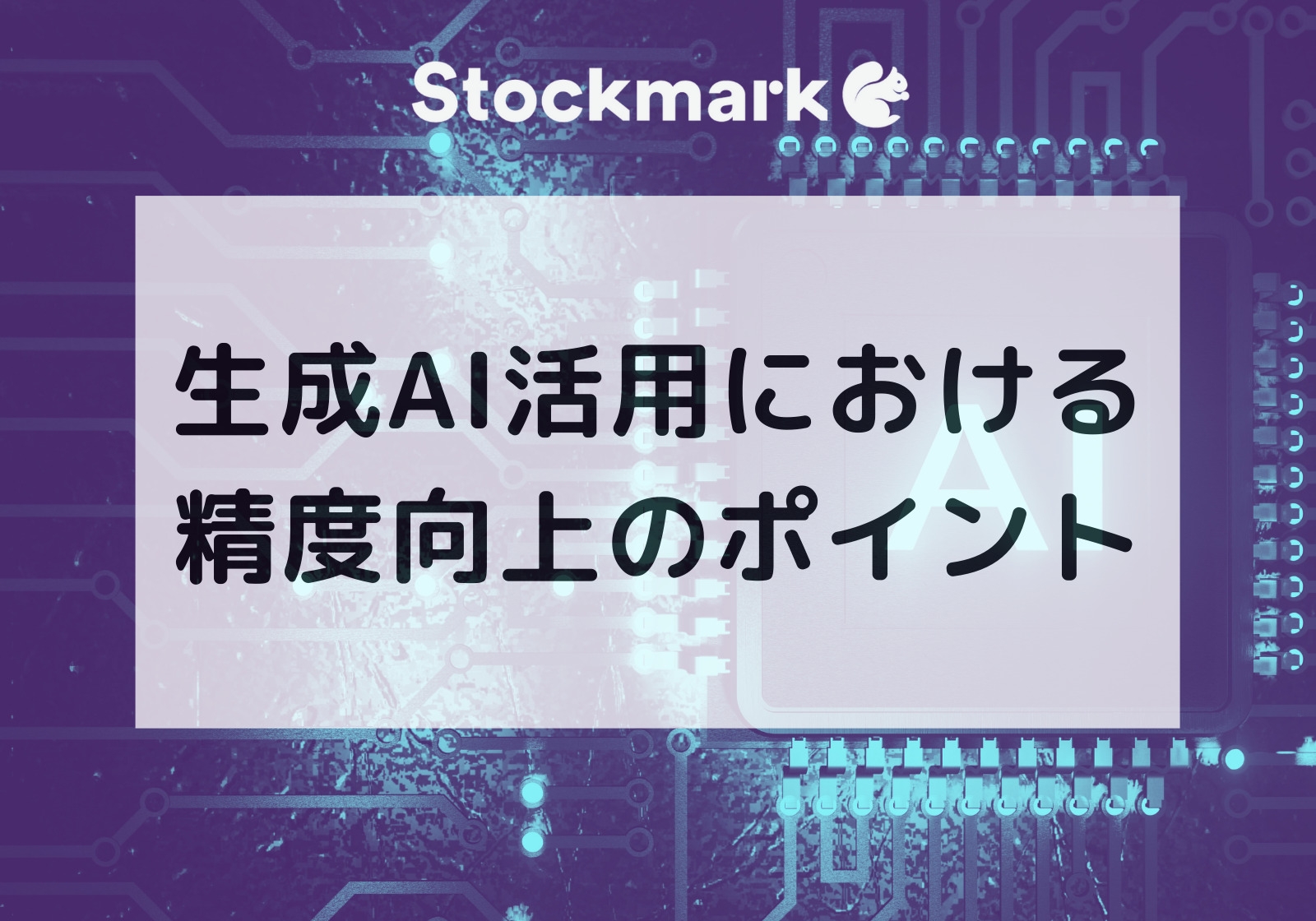現代の組織において、情報共有とは単なる資料やデータのやり取りにとどまらず、組織全体の知識を活かし合う基盤となっている。業務のスピードが加速し市場の変化も激しいなか、個人が抱え込む情報は大きな機会損失につながる。
多くの企業では、情報共有が不十分であるために意思決定が遅れたり、属人化によって業務が停滞する課題を抱えている。このような悩みを解決するためには、情報共有の重要性を理解し、仕組みや文化を整えることが不可欠だ。
本記事では、情報共有の基本的な意味や重要性だけでなく、共有がもたらすメリットを紹介する。また、情報共有における課題や流れ、ポイントなども解説する。情報共有に課題を感じてる方や属人かの解消、生産性の向上を実現したい方は、ぜひご一読いただきたい。
「情報共有」で新しいアイデアが生まれる?
ビジネスを加速させる効果的な実践方法
「情報共有の教科書」を無料でダウンロード
目次
情報共有とは?
情報共有とは、組織やチームの中で必要な情報を関係者同士で伝え合い、活用できるようにする取り組みのことだ。単なる資料の配布や会話の記録ではなく、業務に関わる知識やデータを適切な人が必要なタイミングで参照できる状態をつくることを指す。
例えば、営業担当者が顧客とのやり取りを記録し、別の担当者がその履歴を基に提案を行うケースや、開発チームが進行中のプロジェクトの課題を共有し、設計部門が改善に活かす場面などが挙げられる。このように情報共有は日常の業務の中で自然に行われている一方で、意識的に仕組みを整えることによって組織全体の知識資産として活用できるようになる。
なぜ情報共有は重要なのか
情報共有が重要である理由は、まず属人化を防ぐ点にある。特定の個人だけが情報を抱え込むと、同じ課題に他の人が繰り返し直面したり、既に存在する情報を再び収集するなど無駄な工数が発生する。その結果、業務の遅延や生産性の低下を招き、組織全体のパフォーマンスに悪影響を与える。
また、情報が共有されない状態が続けば、メンバーが自分の努力が組織に反映されていないと感じ、自己効力感や組織効力感の低下につながる恐れがある。さらには、情報の不一致は認識の齟齬を生み、意思決定の遅れや誤解を招きやすくなる。これによりコミュニケーションロスが増加し、チーム内の信頼関係にも悪影響を及ぼす。したがって、情報共有は単なる効率化の手段ではなく、組織の健全な運営に欠かせない基盤だといえる。
「情報共有」で新しいアイデアが生まれる?
ビジネスを加速させる効果的な実践方法
「情報共有の教科書」を無料でダウンロード
情報共有がもたらすメリット
情報共有を徹底することで、組織にはさまざまな好影響がもたらされる。ここでは特に重要な5つのメリットを取り上げ、業務の質やチームの在り方にどのような変化を与えるのかを具体的に解説する。
業務の効率化・生産性の向上・コスト削減
情報共有を徹底することで、まず業務の効率化が実現できる。例えば、必要な資料やナレッジが社内の誰もがアクセスできる形で共有されていれば、担当者ごとに同じ情報を探す無駄な時間を省ける。会議や打ち合わせでも、あらかじめ共有された情報を前提に議論が進められるため、意思決定に至るまでのスピードが速くなる。
こうした効率化は同時に生産性の向上につながる。重複作業を避けることで、従業員は付加価値の高い業務や新しいアイデアの創出に時間を割けるようになり、結果として組織全体のアウトプットが増大する。さらにコスト削減の効果も大きい。
例えば、常に情報が共有されている状態にしておくことで、退職や異動に伴う引き継ぎコストを軽減できるほか、情報不足によるコミュニケーションロスや業務のやり直しといった余計なコストも抑制可能だ。情報共有は単なる便利さにとどまらず、効率と成果、そしてコストの最適化を同時に実現できる。
属人化の防止
業務の属人化を防ぐ上でも極めて有効だ。属人化とは、特定の人物だけが業務の進め方や必要な情報を把握している状態を指し、その人が不在になると仕事が停滞するリスクが高まることを意味する。例えば、営業活動において、商談の進捗や顧客とのやり取りを一人の担当者だけが管理していると、その人が休職や退職をした際に引き継ぎが困難となり、顧客対応の品質が低下する恐れがある。
情報をツールや文書に集約し、チームで共有する仕組みを整えておけば、誰でも業務を引き継ぎやすく、組織全体の安定性が高まる。また、属人化を排除することで、特定の人に負荷が集中する事態も回避でき、チーム内の公平性やモチベーションの維持にもつながる。
心理的安全性の向上と信頼関係の構築
情報共有を積極的に行うことは、組織やチームにおける心理的安全性の向上にも直結する。心理的安全性とは、自分の意見やアイデアを安心して発言できる雰囲気のことであり、情報が透明に共有されている環境では、個人が孤立せず、自然と発言や相談がしやすくなる。
例えば、会議での発言内容や意思決定の背景が共有されていれば、参加者は判断の根拠を理解しやすくなり、不安や疑念を抱くことが少なくなる。その結果、メンバー同士の信頼関係が強化され、建設的な議論や協力体制が生まれる。
さらに、共有された情報を基盤として共通認識が育まれるため、誤解や行き違いが減り、余計な摩擦を避けられる。心理的安全性が高まることで新しい提案や改善案も出やすくなり、組織全体が成長する。情報共有は単なる業務効率化にとどまらず、健全な人間関係と信頼を築くうえで欠かせない。
人材育成および組織力の強化
共有された情報は、特定の経験を持たないメンバーにとって貴重な学びの材料となり、業務に必要な知識や判断基準を効率的に習得できる。例えば、過去の成功事例や失敗事例を文書化して共有すれば、同じ課題に直面した際に適切な対応を導きやすくなる。
また、ベテラン社員のノウハウを可視化して蓄積することで、属人的なスキルに依存せず、組織全体の知識レベルを底上げできる。これにより新人や若手は早期に戦力化され、チーム全体の成長速度が加速する。さらに、情報を共有する習慣は部門を越えた横断的な連携を促し、異なる視点や強みを組み合わせた新しい価値を生み出す基盤となる。
結果として、個々のスキル向上と同時に、組織としての競争力や持続的な成長力を高めることが可能だ。
新しい視点や技術、製品などを発見できる
他にも、情報共有は組織への新しい視点や技術、製品を発見させる原動力となる。個々の社員が得た知識や経験を積極的に開示することで、他のメンバーが持つ情報と結び付き、これまで気づかなかった新しい解決策やアイデアが生まれる。
例えば、営業部門が顧客のニーズを共有し、開発部門がそれをもとに新しい機能を検討することで、顧客満足度を高める製品やサービスにつながる。また、社内外で得られた最新技術や市場動向を組織全体で共有すれば、競合より早くトレンドを捉え、先手を打った戦略を展開できる。
さらには、多様な視点を持つ人材が情報を持ち寄ることで、部門や立場の違いを超えた相互作用が起こり、既存の枠組みにとらわれない革新的な発想が促進される。このように、情報共有は単なる知識の伝達ではなく、組織の成長や競争力強化を支える新しい価値の発見プロセスだといえる。
「情報共有」で新しいアイデアが生まれる?
ビジネスを加速させる効果的な実践方法
「情報共有の教科書」を無料でダウンロード
情報共有がうまくいかない原因
情報共有は組織に大きなメリットをもたらす一方で、実際には思うように浸透せず、形骸化してしまうケースも多い。その背景には、単に情報を伝える仕組みがないという単純な問題にとどまらず、組織文化や個々の意識のあり方など、複数の要因が複雑に絡み合っている。ここでは、情報共有がうまくいかない主な理由について解説する。
情報共有のメリットが理解されていない
情報共有が進まない大きな原因の一つは、従業員や管理者がそのメリットを実感できていない点にある。日常業務の中では、情報を共有する行為は「余計な手間」や「時間がかかる作業」と認識されやすい。共有した結果がすぐに自分の業務に返ってくるわけではないため、短期的な成果を優先する環境では後回しにされる傾向が強い。
また、経営層やマネジメントが「共有によって効率化できた事例」や「コスト削減につながった実績」を明示的に伝えていないと、従業員はその価値を理解できず、共有を積極的に行う理由を見失う。この認識不足が、情報共有を根付かせる大きな障害だといえる。
情報を共有する仕組みや文化がない
情報共有が定着しないもう一つの大きな要因は、組織としての仕組みや文化が整っていないことだ。例えば、情報をストックするためのシステムが存在しなかったり、複数のツールに分散して使われていたりすると、従業員は「どこに情報を置けばよいのか」「どう探せばよいのか」がわからず、共有が形骸化してしまう。
また、評価制度や人事制度の中に「共有する行為」が組み込まれていない場合、従業員は「共有してもしなくても自分の評価は変わらない」と考え、積極的に取り組まない。さらに、組織として「失敗や学びも共有してよい」という心理的安全性を確立できていない場合、成功体験しか表に出ず、情報共有が部分的かつ限定的になってしまう。
社内やチームのコミュニケーション・雰囲気に問題がある
情報共有が滞る背景には、単なる人間関係の不和だけでなく、組織の構造や文化に起因する原因が潜んでいる。例えば、上司が部下の意見を一方的に否定する風土や、発言に対する評価が不透明な体制では、従業員は「余計なことを言わないほうが安全だ」と考え、情報を出さなくなる。
また、部門間に壁があり縦割り意識が強い場合も、他部署に情報を渡すことが「自分のリソースを奪われる」行為とみなされやすい。このように、心理的な安全性の欠如や組織構造上の断絶が、情報の流れを妨げる大きな原因となっている。
そもそも情報収集や共有の時間を確保できない
時間が確保できない根本的な原因は、業務設計や優先順位付けの仕方にある。多くの現場では「今目の前のタスクをこなすこと」が最優先とされ、情報収集や共有といった長期的に効率を高める活動は後回しにされがちだ。
さらに、業務量が常に過剰で人員が不足している環境では、情報整理や共有は「余裕があるときにやること」と扱われるため、慢性的に時間が取れない。結果として、重要な情報が各個人のメールやPC内に閉じ込められ、組織として活用されない。この状況は、業務プロセスの設計段階で情報共有を前提に組み込んでいないことが最大の原因である。
「情報共有」で新しいアイデアが生まれる?
ビジネスを加速させる効果的な実践方法
「情報共有の教科書」を無料でダウンロード
情報共有の文化を作る流れ
情報共有を一時的な取り組みで終わらせず、組織に根付かせるためには段階的な工夫が欠かせない。そのためには、日常業務の中で情報を扱う時間を意識的に設けることから始め、共有された情報をどう活かすかを仕組みに落とし込むことが必要だ。ここでは文化を定着させるために重要な4つの流れを紹介する。
意図的に情報を収集・整理する時間を設ける
意図的に情報を収集・整理する時間を確保することは、場当たり的な調査や情報収集を防ぎ、常に鮮度と質の高い材料を手元に揃えるための前提となる。例えば、毎朝15分のトレンド収集、週1回30分の整理といった定時ブロックをカレンダーに固定し、テンプレートに沿って目的・仮説・検索キーワード・出典・信頼度・要点・未解決点を記録する。
さらに、命名規則やタグ(テーマ、顧客、技術、期間)で一貫して分類すれば、ノイズを減らし再検索時間を短縮できる。この「決まった手順×決まった時間」により、個人の勘や記憶に依存しない再現性のある情報収集プロセスが確立し、結果として組織全体の情報の扱いが安定する。
情報を共有する時間を作る
情報を共有する時間をあらかじめ確保することは、偶発的な雑談任せの共有を脱し、共有行為を業務の前提に格上げする効果がある。定例の15分共有会や週次レビューをカレンダーでブロックすれば、誰がどの視点を持ち寄るかが明確になり、情報の属人化や“持ち帰りっぱなし”を防げる。
また、発見を言語化して伝えるプロセス自体が暗黙知を形式知へ変換し、論点の粒度も揃う。さらに、定期的な場は「次までに何を観測し、どう検証するか」という期待値をチームに埋め込み、更新のリズムを生む。結果として、共有は後回しにならず、組織内での知の循環が継続的に加速する。
共有された情報を活用する
共有された情報を実際の判断や施策に結び付けることは、共有を「単なる報告」から「価値創出の仕組み」へ格上げする核となる。活用されない共有は発信者の情報共有に対する動機を削ぎ、文化が根付かない。例えば、営業が拾った競合の値上げ情報を基に提案価格と訴求軸を即日更新し、受注率の変化を追う。
CSが集約した問い合わせ傾向をプロダクトのUI改善やFAQ改訂に反映し、問い合わせ量の推移で効果を検証する。こうして「共有→活用→成果の可視化→再共有」の循環が生まれると、メンバーは自分の情報が組織成果に寄与する手応えを得ることができ、結果として共有は継続され質も量も向上する。
従業員の評価項目に情報共有を含める
従業員の評価項目に情報共有を含めることは、組織全体で情報共有を自然に行うための大切な仕組みだ。情報を共有することが個人の善意や余裕に依存していると、忙しい時期にはどうしても後回しになりがちだが、評価基準に明確に組み込むことで、共有の重要性が日常的に意識されやすくなる。
例えば、定期的な知見の発信や他部署での活用状況を評価に反映させれば、自分の発信が組織に役立っていることを実感でき、モチベーションの向上にもつながる。また、情報をまとめてわかりやすく整理する役割や、チーム内で積極的に質問に答える行動も評価対象とすれば、多様な形での貢献が認められる。
こうした仕組みを整えることで、情報共有は一部の人だけでなく、組織全体で支え合いながら続けていける文化として根付いていくだろう。
「情報共有」で新しいアイデアが生まれる?
ビジネスを加速させる効果的な実践方法
「情報共有の教科書」を無料でダウンロード
情報共有を行う際のポイント
情報共有を行う際には、単に情報を集めるだけではなく、それをいかに円滑に広め、定着させるかが大切だ。特に文化として根づかせるためには、意識的に取り組むべきいくつかの工夫が必要になる。ここでは、情報共有を実践する上で押さえておくべき5つのポイントを紹介する。
情報共有の重要性や目的を啓蒙する
情報共有の重要性は、抽象論ではなく事実と自部署の課題で示すのがよい。例えば、情報が共有されないことにより同じ調査を三度繰り返し週に合計6時間失っている、一次回答の品質が担当者でばらつく、などを定量と具体例で伝えることだ。また、過去の事例を検索したことで作業時間が30分程度短縮したといった共有による成功体験を伝えるのもいいだろう。
加えて、目的は意思決定を速く正確にすることや、同じ前提で議論できる状態をつくること、あるいはリスクや学びを横展開することのように、明確に言語化し、定例会の冒頭で繰り返し掲示するとよい。
情報共有のルールや仕組みを作る
情報共有を円滑に進めるためには、場当たり的に情報をやり取りするのではなく、明確なルールや仕組みを設けることも重要だ。例えば、どのような情報を誰に向けて、どのタイミングで共有するのかを定義しておくことで、不要な情報の氾濫や重要情報の見落としを防げる。
また、共有の方法も統一することが望ましい。メールや口頭報告に頼るのではなく、社内Wikiやチャットツール、ドキュメント管理サービスなど、組織に合ったプラットフォームをあらかじめ指定することで、情報の散在を防ぎ、必要な人がいつでも参照できる環境が整備できる。
他にも、情報のフォーマットを統一する仕組みを設けることも有効である。例えば、会議の議事録をテンプレート化する、プロジェクトの進捗を共通のシートで管理するなどの工夫は、情報を整理しやすくするだけでなく、異なるチーム間でも理解しやすい形で活用できるようになる。こうしたルールや仕組みを整えることで、情報共有は属人的な努力に依存せず、組織全体に根付く文化として定着しやすくなる。
組織内のコミュニケーションを活性化させる
組織内のコミュニケーションを活性化させることは、情報共有を根付かせるために欠かせない要素である。例えば、上司と部下が定期的に1対1で話し合う1on1ミーティングを実施することで、業務上の課題やキャリアの方向性を早期に把握でき、信頼関係の構築にもつながる。
また、社内イベントや懇親会、サークル活動などを通じて交流の機会を増やせば、部署を超えたつながりが生まれ、日常業務での相談や協力がしやすくなる。さらには、チャットツールや社内SNSを導入すれば、メールよりも気軽に意見交換でき、リアルタイムでの情報共有が可能だ。
他にもオフィスのフリーアドレス制やランチ交流の機会を活用すれば、固定化された人間関係を超えて新しいコミュニケーションが促進されるだろう。これらの取り組みを組み合わせることで、情報が自然に行き交い、組織全体の協働意識が高まり、情報共有が円滑に進む環境が醸成されるだろう。
情報共有ツールを導入する
情報共有ツールは、知見を個人や部門に依存させず情報を一元管理できる点がおすすめだ。メールやチャット、個別のドキュメントで情報をやり取りすると、担当者ごとに表現や粒度が異なり、同じ情報であっても受け手によって理解に差が出やすい。
これに対して、情報共有ツールであれば共通のフォーマットやルールに基づいて記録できるため、情報の一貫性が保たれ、誰が見ても同じように理解できる。また、タグ付けや検索機能を備えたナレッジベースを構築できることで、必要な情報にすぐアクセスでき、探す時間を大幅に削減できる。
他にも、権限設定や監査ログといった機能により、情報セキュリティやコンプライアンスを担保できる点も重要である。情報を一元的に管理することで「情報がどこにあるかわからない」「共有が形骸化する」といった課題も解消できる。
小さく始め、些細なことでも共有する
情報共有を文化として根づかせるためには、まず小さな範囲から始めることが効果的だ。最初から会社全体で一斉に共有を徹底しようとすると、何を共有すべきか分からずに戸惑いが生まれ、結果として取り組みが停滞しやすい。その点、上司と部下、あるいは同僚同士といった個人間のやり取りや、チーム内といった小さな枠組みであれば、失敗しても影響が限定的であり、心理的なハードルも低い。
また、共有する内容も特別なものに限る必要はなく、「先日の業務でAIを試した」「営業先でこういう意見を聞いた」といった些細な体験や気づきを伝えることから始めるのがよい。些細な情報でも共有してよいという体験を積み重ねることで、社員一人ひとりに共有の習慣が身につきやすくなる。他にも、その最初の一歩を踏み出す人、いわばファーストペンギンが存在することで、他のメンバーも自然に後に続き、徐々に共有の輪が組織全体へ広がっていく。
「情報共有」で新しいアイデアが生まれる?
ビジネスを加速させる効果的な実践方法
「情報共有の教科書」を無料でダウンロード
情報共有におすすめなツール
情報共有を円滑に進めるためには、目的や利用シーンに応じて適切なツールを選ぶことが重要だ。ここでは、日常のやり取りから情報の蓄積、顧客管理まで幅広く役立つ5つの代表的なツールを紹介する。
ビジネスチャット
ビジネスチャットとは、SlackやChatwork、LINEなどに代表されるリアルタイムでのやり取りを可能にするコミュニケーション手段を指す。最大の特徴は即時性の高さであり、メールのように形式に縛られることなく、必要なメンバーだけを巻き込んで効率的に会話を進めることができる。また、発言内容はスレッド化され履歴として残るため、過去のやり取りを容易に確認でき、引き継ぎや状況の把握もスムーズである。
口頭やメールに比べて心理的なハードルが低く、思いついた情報を気軽に投稿できる点も、情報共有の速度を高めるだろう。他にも、オープンなチャンネルに共有することで、直接関わらない人でも進捗や状況を把握でき、透明性の高い情報共有を実現できる。
ファイル共有サービスやドライブ
ファイル共有サービスやドライブとは、GoogleドライブやBox、OneDriveなどのクラウドストレージが該当する。インターネット環境さえあれば、場所やデバイスを問わずファイルにアクセスできるため、リモートワークや出張といった多様な働き方を支える。さらに、GoogleドライブやOneDriveでは複数人による同時編集が可能で、バージョン管理も自動で行われるため、常に最新の情報を共有できるという利点がある。
一方で、権限設定を誤ると意図しない相手に情報が流出するリスクがあり、さらにファイルやフォルダが増えすぎると整理や検索が難しくなり、かえって効率を下げる恐れもある。したがって、導入時には適切なルールづくりや運用設計が不可欠であり、利便性と安全性を両立させることが重要だ。
SFAおよびCRM
SFAおよびCRMとは、顧客情報を一元管理し、営業活動や顧客対応を効率化するためのシステムのことで、代表例としてセールスフォースやHubSpotが挙げられる。これらのツールを活用することで、顧客情報や商談履歴、営業活動の進捗状況をリアルタイムに共有できるようになり、担当者が不在でも他のメンバーがスムーズに顧客対応を引き継ぐことが可能だ。
また、蓄積されたデータを基に分析やレポートを容易に作成できるため、経営判断や戦略立案の精度を高める点も大きな利点である。一方で、導入や運用には一定のコストがかかり、従業員にシステムの利用を定着させるための教育や習慣づけが必要である。
加えて、入力作業の負担を煩わしく感じる社員も多く、正確な情報が記録されなければシステムの効果は大きく損なわれる。他にも、顧客情報というセンシティブなデータを扱う性質上、セキュリティリスクや権限設定の不備による情報漏えいの危険性も無視できないため、慎重な運用と管理体制の整備が必須だ。
社内Wikiや社内ポータル
社内Wikiや社内ポータルは、組織の知識や情報を体系的に蓄積し、社員が必要なときにすぐに参照できる仕組みとして有効だ。代表的なサービスにはNotionやSharePointがあり、社内規程や業務マニュアル、ナレッジ記事を整理して共有するのに適している。検索機能を活用すれば、必要な情報に素早く辿り着くことができ、特定の人に依存せずに業務を進められるため、属人化の防止にもつながる。
一方で、情報更新が滞れば内容が古くなり、誤った情報が流通して混乱を招く恐れがある。また、社員が日常的に更新や参照を行わなければ、せっかくの仕組みも形骸化しやすくなる。さらに、情報が増えすぎると検索の精度が課題となり、かえって目的の情報に辿り着きにくくなる場合もある。加えて、システムの維持管理には一定のコストやリソースが必要であり、情報の整備や運用ルールを定めておくことが欠かせない。
グループウェア
グループウェアは、企業や組織での情報共有と協働作業を効率化するために設計された統合ツールである。代表的なものにMicrosoft 365 や Google Workspace があり、スケジュール管理、文書共有、ワークフロー申請、掲示板、チャットなど複数の機能を一つのシステム上で利用できる点が特徴だ。
こうした環境を導入することで、情報が部署やチームを横断して一元的に共有され、必要な人に必要な情報が漏れなく届く体制を作りやすい。また、権限設定やアクセス制御が整っているため、セキュリティを確保しながら情報を管理でき、履歴やログが残ることで業務の引き継ぎや透明性の向上にもつながる。
一方で、導入や運用にはコストがかかり、大規模組織ほど初期設定やカスタマイズに手間がかかる。また、機能が多すぎるがゆえに利用者が全てを使いこなせず、結果的にメールやチャットに依存する状況へ逆戻りしてしまうケースもある。さらに、自社の文化や既存の業務フローと合わない場合は、かえって非効率を招くリスクも存在する。
情報収集と情報共有をセットで解決するなら
当社が提供するAconnectは、製造業をはじめとした知識集約型の組織に適した情報共有ツールである。特に市場動向や技術開発を追い続ける必要がある部門にとって、社内外の膨大な情報を効率的に収集し、共有する仕組みが求められている。
Aconnectは国内外約3万5千のニュースサイト、特許や論文、官公庁レポートを自動で収集するだけでなく、ツール内にアップロードした社内資料までを調査し、必要な知見をグループに共有できる環境を提供する。また、Chrome拡張機能やモバイルアプリにより、気づいた情報を即座にチームに届けられ、レポート化や自動通知によって組織全体の知識活用を加速させることが可能だ。これにより情報のサイロ化を防ぎ、意思決定のスピードを高めることができるだろう。
社内における情報共有やナレッジマネジメントに課題を感じている方は、気軽に無料トライアルをお試しいただきたい。