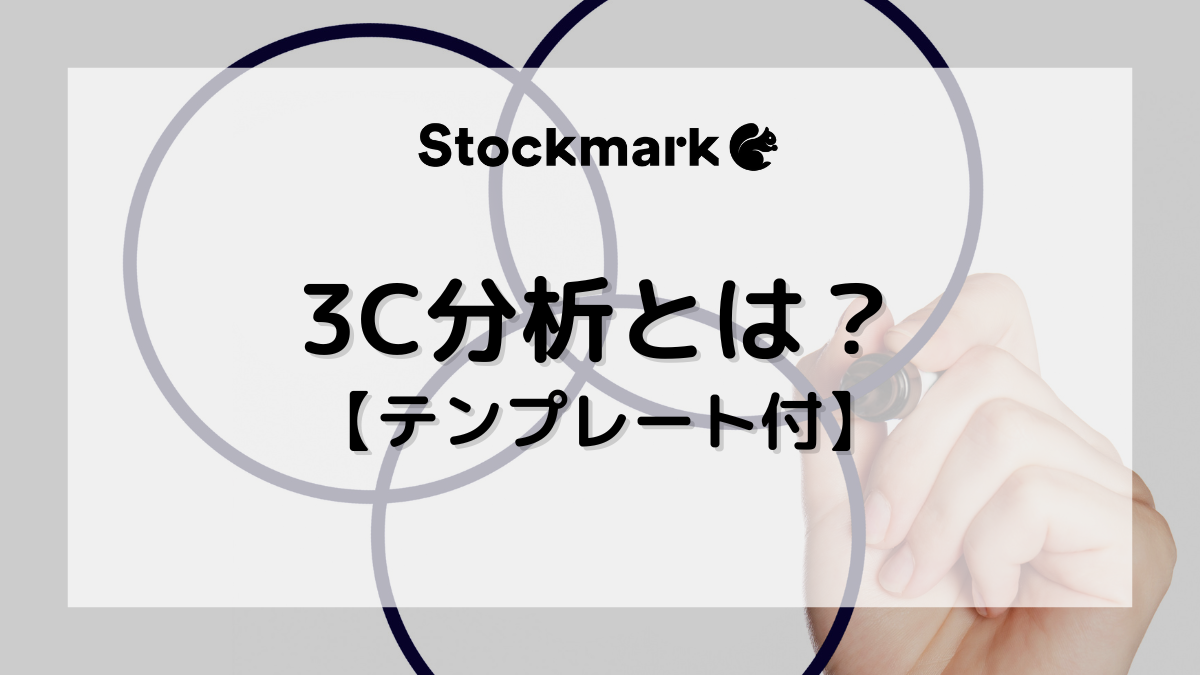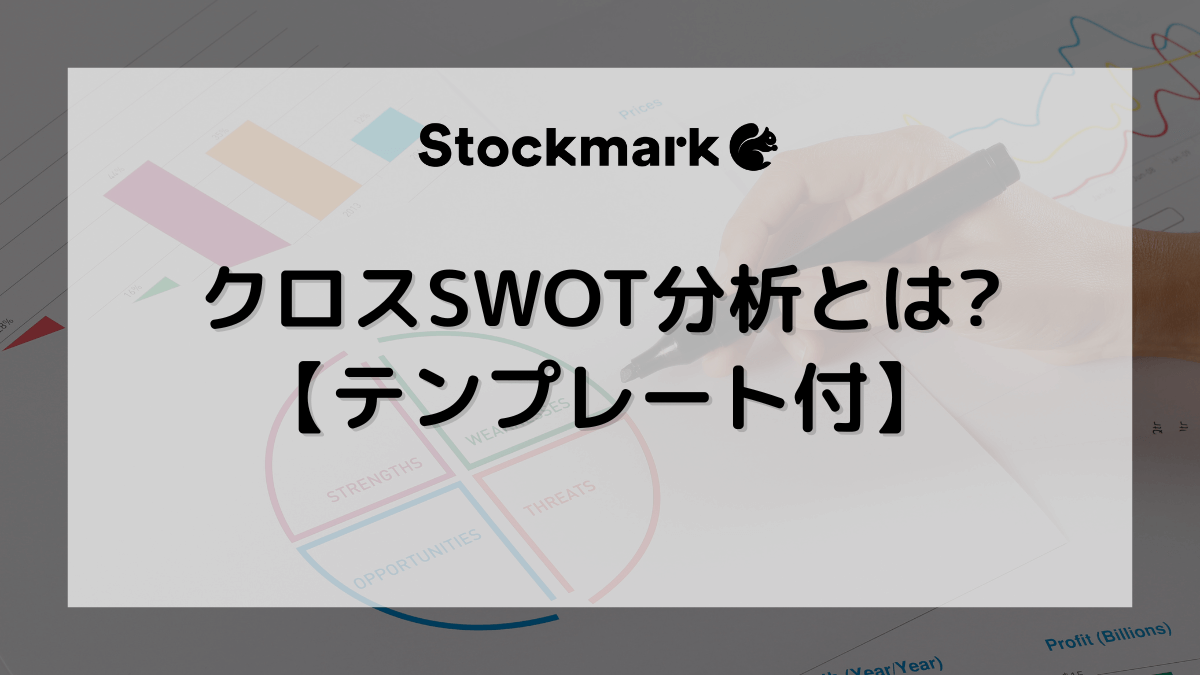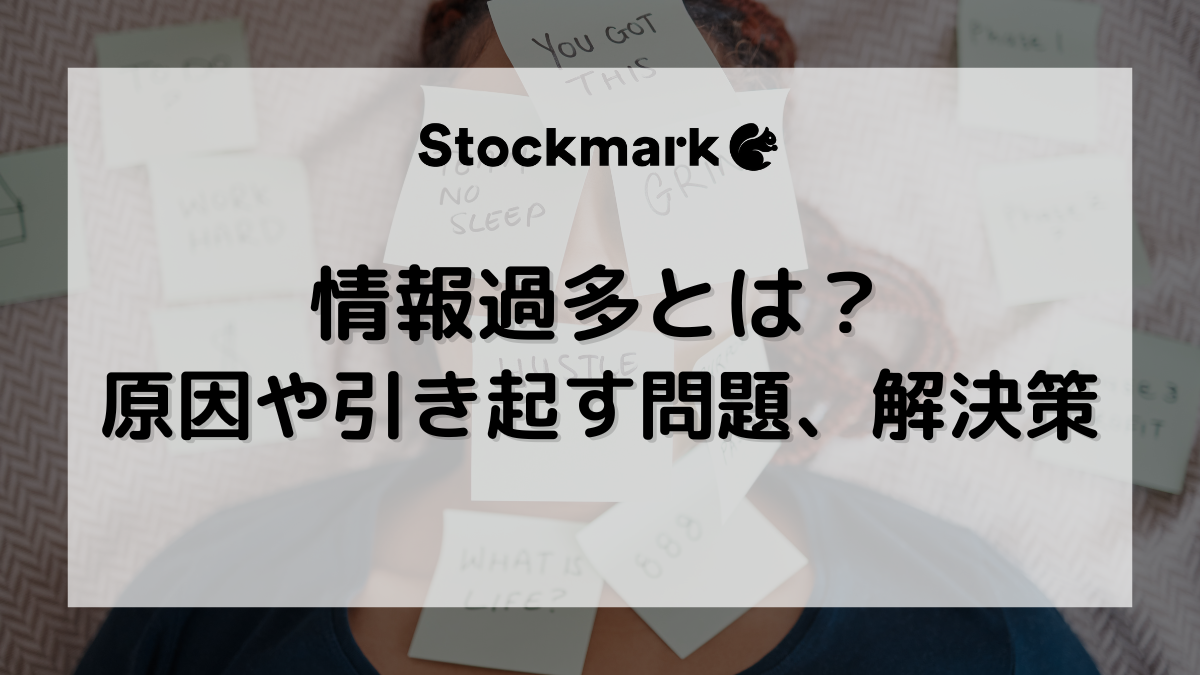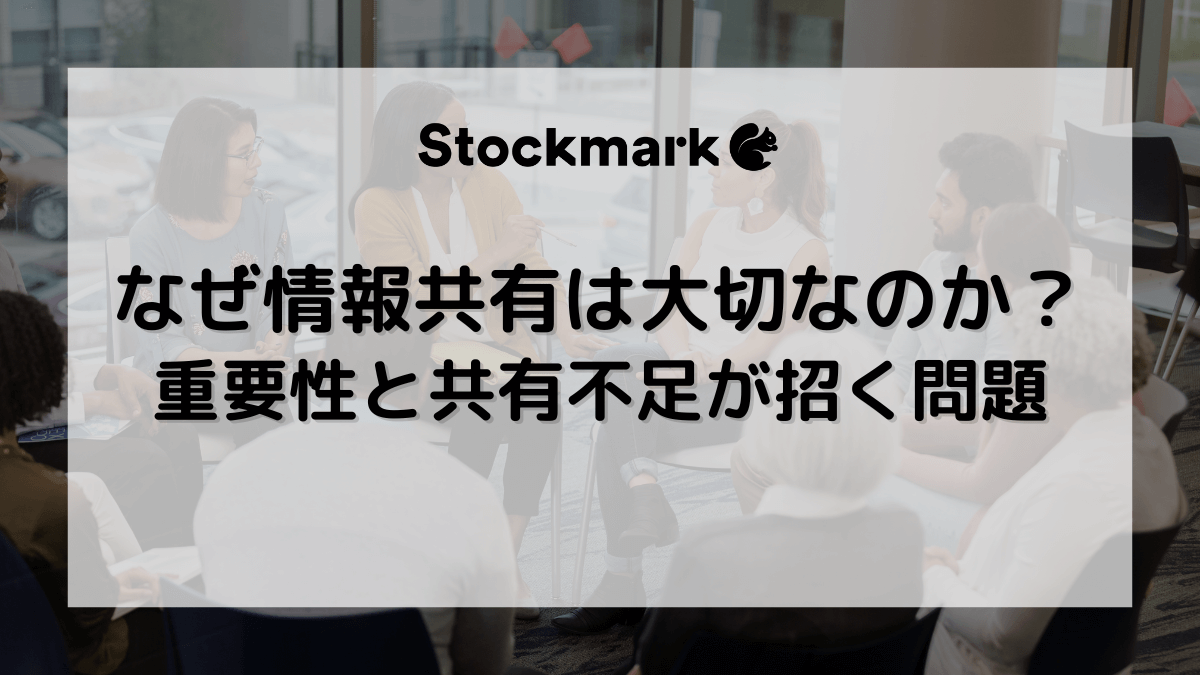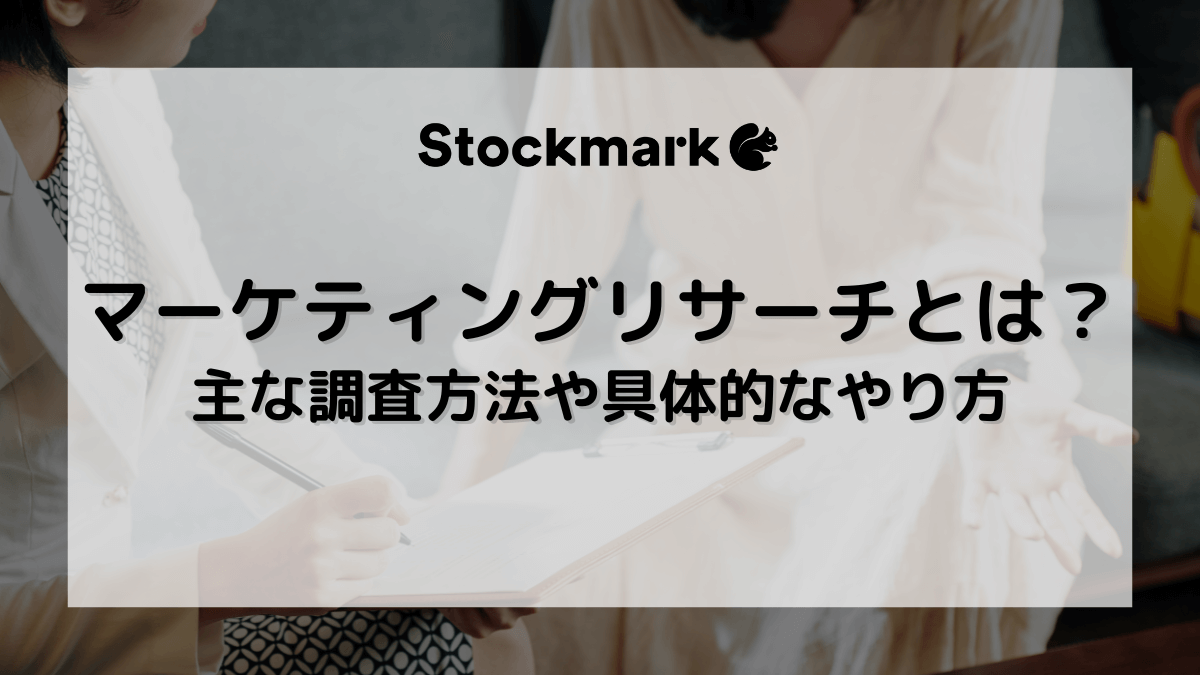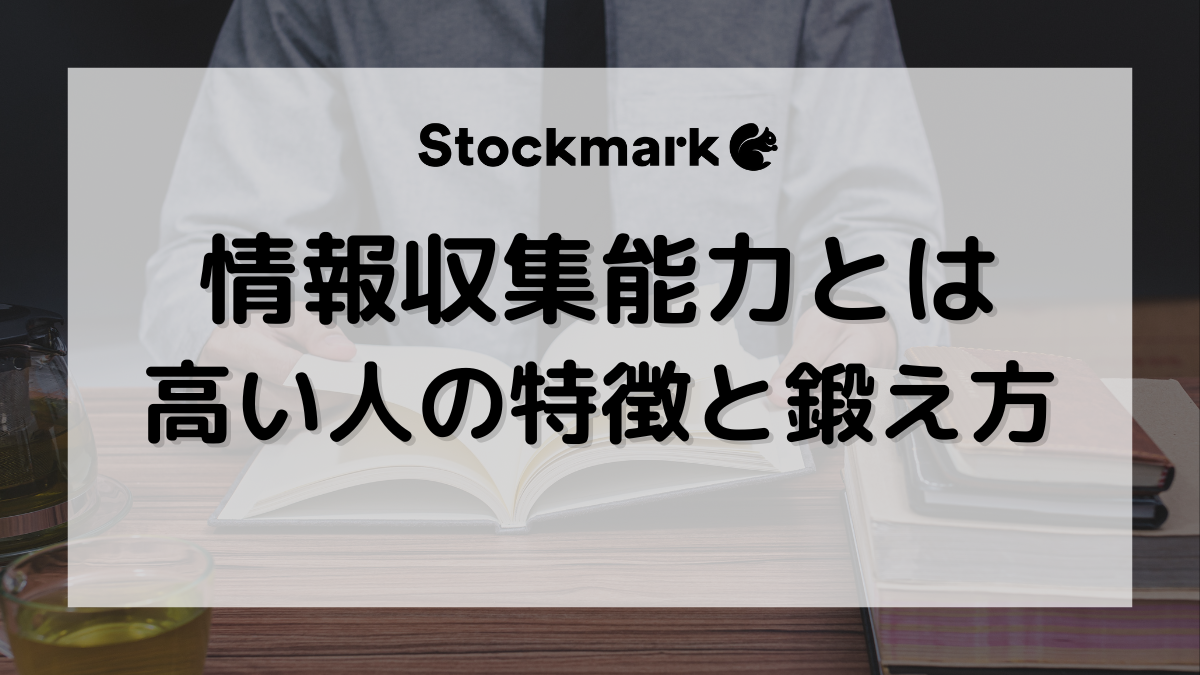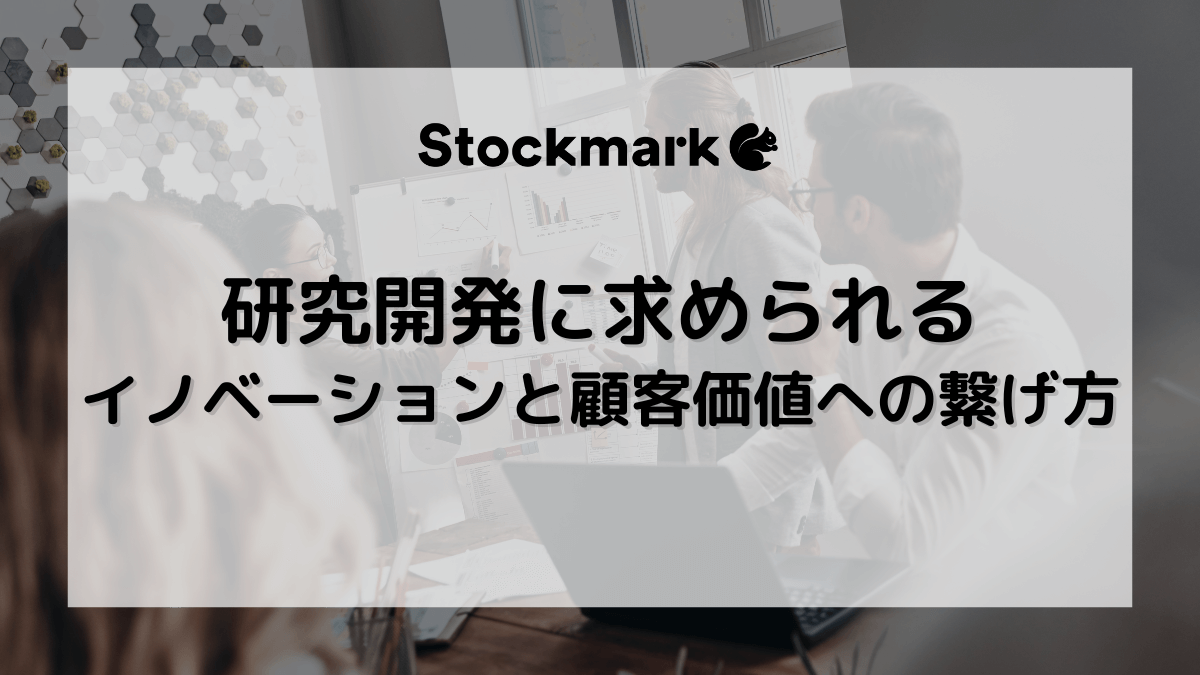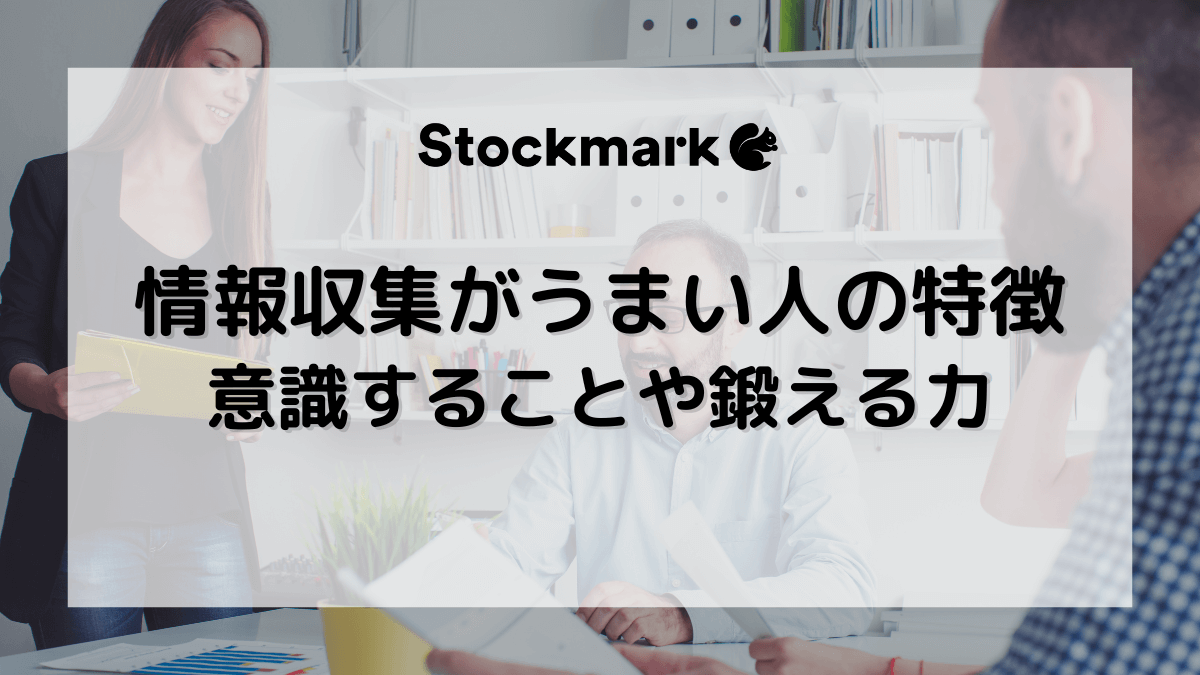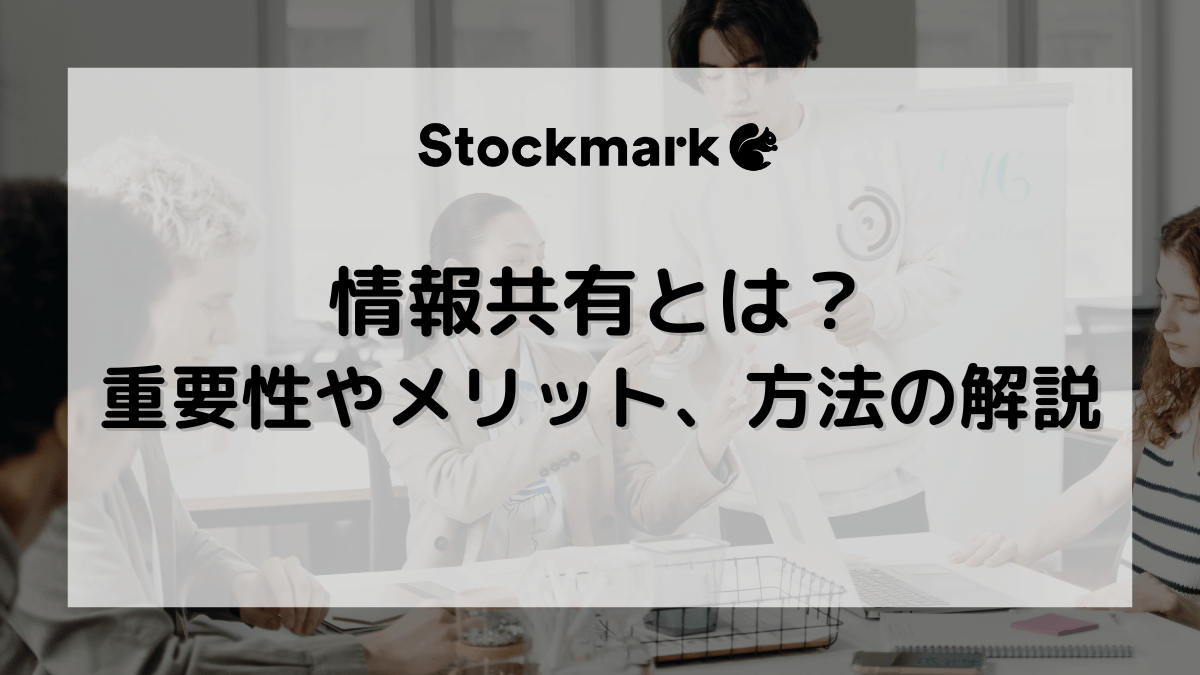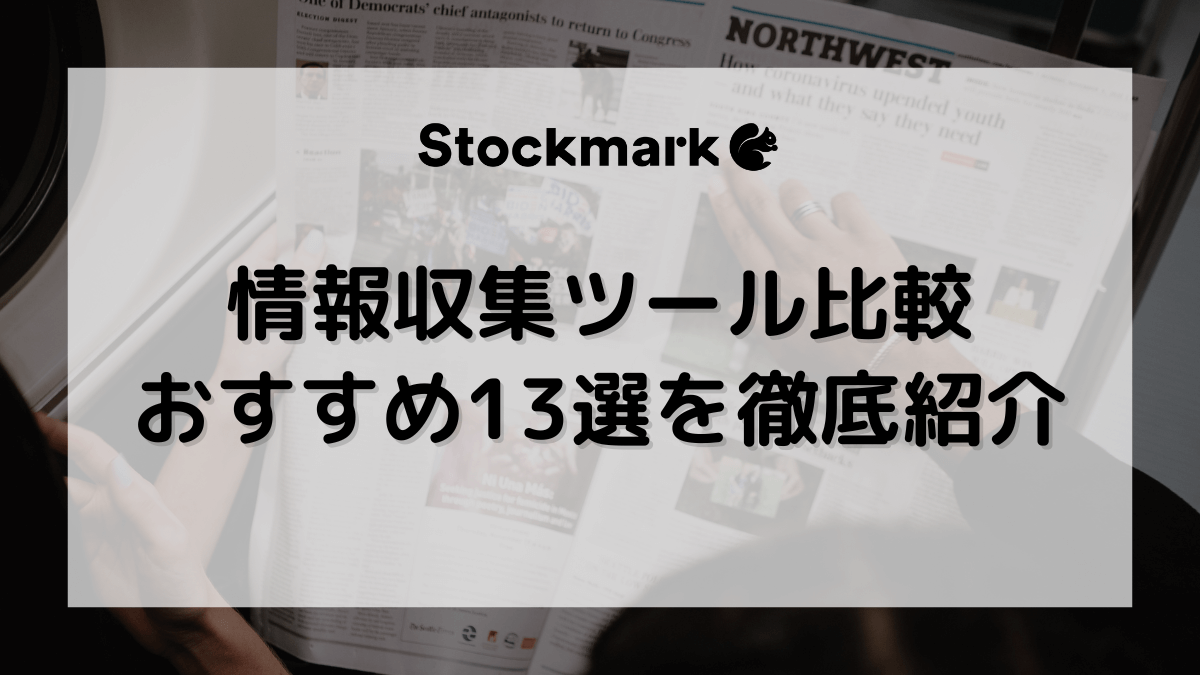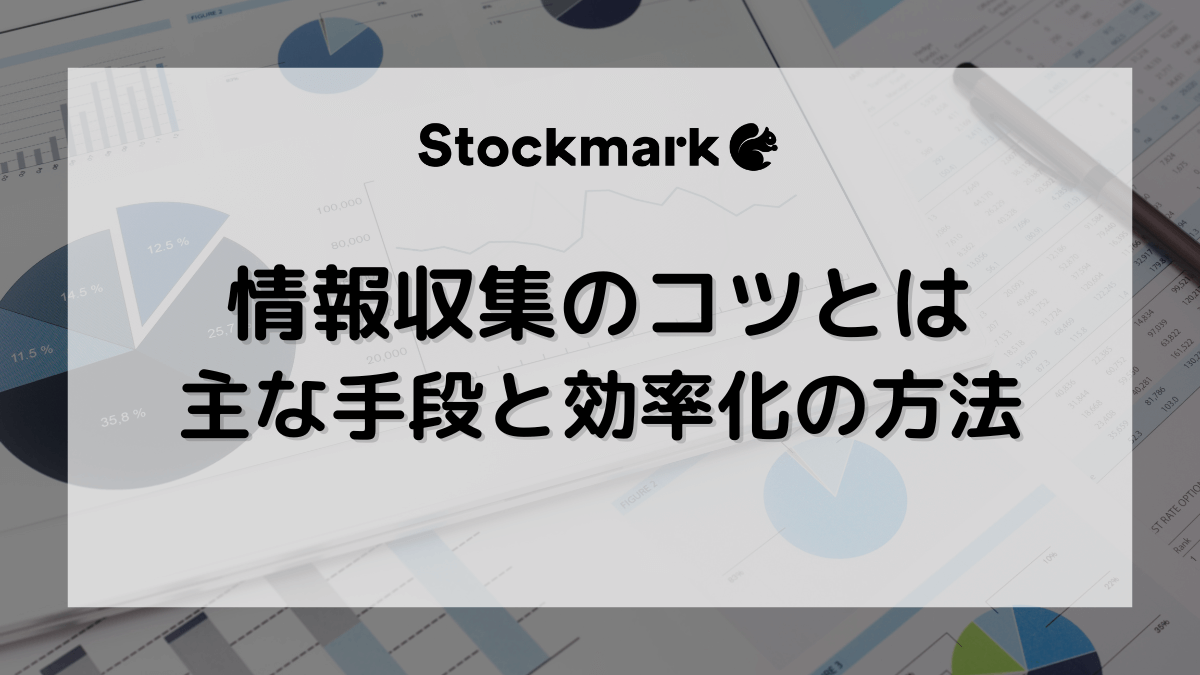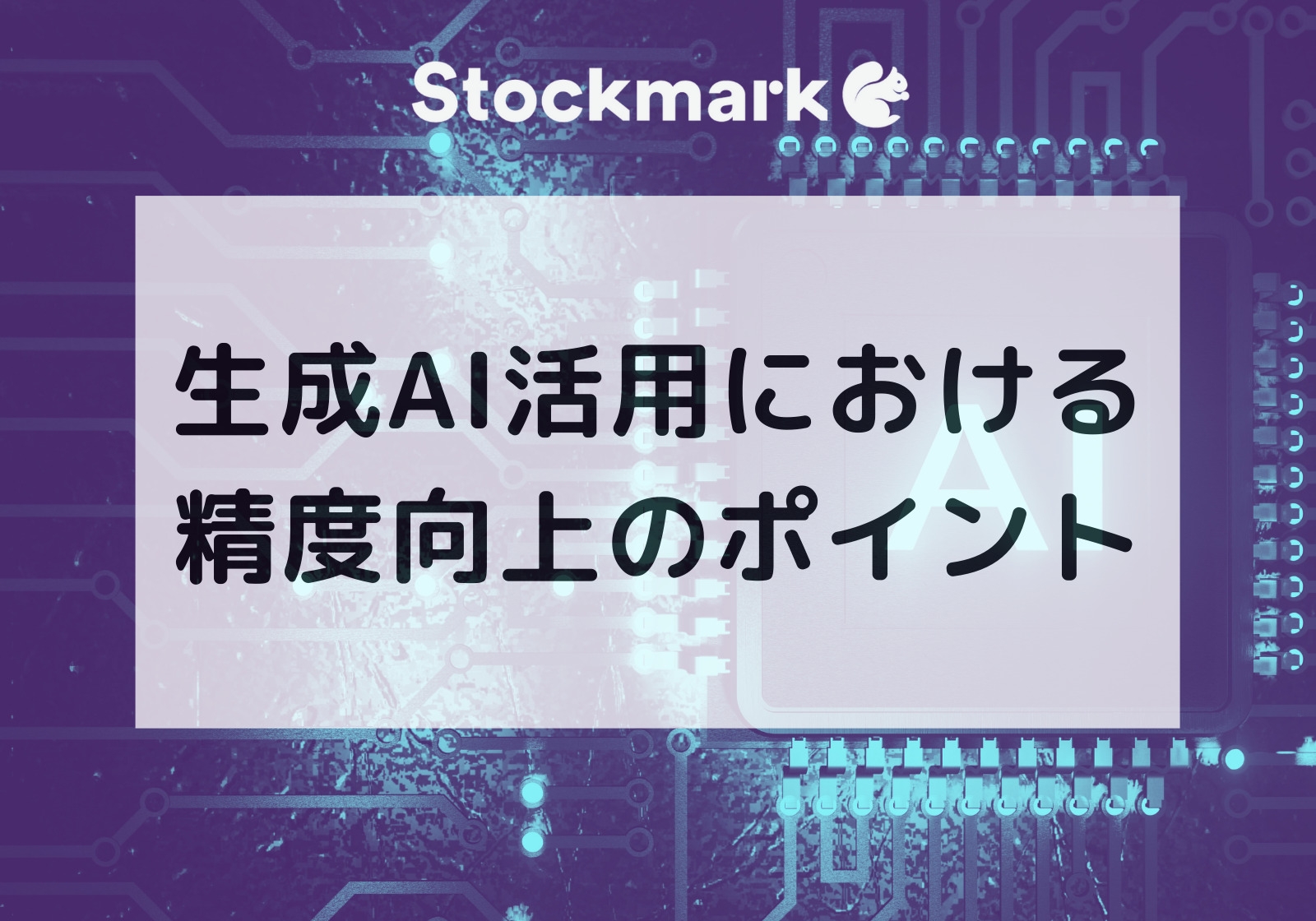業界動向を的確に調べることは、マーケティング戦略や経営判断、新規事業開発、研究開発など、いずれにおいても欠かせない取り組みである。業界全体の流れを把握できれば、自社の立ち位置や競合との差異を明確化でき、新たな市場機会をつかむと同時にリスクの芽を早期に摘むことが可能になる。
この記事では、業界動向を調べる13の具体的な方法や注視すべきポイントに加え、市場規模の算出手法やフレームワークを活用した分析アプローチまでを解説する。業界動向を調べることで、迅速かつ的確な意思決定が可能になり、激変する市場環境に対応できる競争力を備えることができるだろう。
業界動向の調査をもっと効率化したい
最新の業界情報を“自動で収集・整理”するなら Aconnect
まずは資料を無料ダウンロードする
目次
業界動向を調べる13の方法
業界の変化を正しく把握するには多角的な情報収集が欠かせない。ここでは信頼性の高い13の調べ方を紹介する。
急激に変化する市場の動向を的確に捉えるには?
やった気で終わらせないための市場調査の教科書
「市場調査の教科書」を見てみる
ニュースアプリ・サイト
ニュースアプリやニュースサイトは、業界動向を調べる最も手軽で効率的な手段である。スマートフォンやPCさえあれば、通勤時間や隙間時間でも最新情報にアクセスでき、速報性の高さから市場の変化や競合企業の動きをいち早く把握できるのが強みだ。
例えば、日経電子版やBloombergのようなニュースサイトは経済や産業全体の流れを押さえるのに有効であり、SmartNewsやNewsPicksといったニュースアプリはトレンドを幅広く拾える。一方で、自分の関心のある分野ばかりを閲覧しがちな傾向があるため、関連性の低いと思える業界ニュースにも意識的に触れる姿勢が重要だ。
検索機能を活用すれば紙媒体よりも効率的に情報を抽出できるため、最新情報を取り入れたい場合に非常に有用な調べ方である。
全国紙
全国紙(全国新聞・一般新聞)は、幅広い業界の動向や経済全体の流れを把握するのに有効な情報源である。日本経済新聞、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞などは、政策動向や国際関係、産業別のニュースを網羅的に取り上げており、業界全体のマクロな環境を理解するのに役立つ。
特に日経新聞は企業の決算情報や市場分析に強く、経営判断や投資戦略の参考になる。一方で速報性を重視する性質上、後に情報が訂正される場合もあるため、内容を鵜呑みにせず更新状況を確認する姿勢が求められる。全国紙の強みは、自身の関心分野に限らず他業界や政策、外交問題など幅広い情報に自然と触れられる点にある。
業界動向を調べる際に信頼性と網羅性を兼ね備えた媒体を選ぶなら、全国紙が最も堅実な選択肢である。
専門紙
専門紙(専門新聞)は特定の業界に特化して情報を提供する新聞や雑誌であり、その分野の動向を深く理解するのに最適な媒体である。例えば、化学工業日報や電波新聞、鉄鋼新聞などはそれぞれの業界に関するニュースや技術革新、規制の動きを詳細に取り上げている。
全国紙が経済全体や政策といったマクロ視点の情報を提供するのに対し、専門紙は業界内部の動きに焦点を当てるため、実務に直結する情報を得やすい。特に、新製品の発表や業界特有の課題への対応状況などは専門紙だからこそ得られる知見といえる。
ただし、自身の業界に関する情報は豊富でも、他分野の情報には触れにくいため、全国紙や官公庁の資料と組み合わせて利用するのがいいだろう。
海外紙
海外紙は、国際的な市場環境や海外競合の動きを把握するのに適している情報源である。ニューヨーク・タイムズや、フィナンシャル・タイムズ、ウォール・ストリート・ジャーナルなどは、世界経済や多国籍企業の動向を詳細に報じており、日本のメディアでは拾いきれない視点を得られる。
特に、自動車や半導体、エネルギーといったグローバルに展開する産業においては、現地発のニュースが経営戦略に直結する場合がある。一方で、紙媒体は言語の壁があるため利用しにくく、日本語以外の言語に習熟していない場合はおすすめできない。各社が提供するWEB版であれば、翻訳機能を活用して効率的に情報を取り込むことができるだろう。
業界動向の調査をもっと効率化したい
最新の業界情報を“自動で収集・整理”するなら Aconnect
まずは資料を無料ダウンロードする
白書
白書は官公庁が発行する年次報告書で、特定分野の現状や課題、将来の方向性を体系的にまとめた資料である。例えば、経済産業省のものづくり白書や総務省の情報通信白書は、それぞれの分野における統計データや政策の動向を網羅的に整理している。
政府が提供する公式資料であるため信頼性が高く、業界全体の動向を俯瞰するのに適している。一方で年次単位の報告となるため速報性には欠け、直近のトレンドを把握するには新聞やニュースサイトに劣る。しかし、過去のデータを用いた振り返りや中長期的な傾向分析には非常に有効であり、新規事業や研究開発の基盤情報としても役立つ。
各省庁が公開する統計データ
各省庁が公開する統計データは、産業や市場の実態を客観的に把握できる有力な情報源である。例えば、経済産業省が発表する鉱工業指数や総務省の労働力調査、特許庁が公開する特許出願件数などは、製造業や研究開発分野の動向を知るうえで欠かせない。また、資源エネルギー庁が提供するエネルギー需給統計は、エネルギー関連事業の将来性を評価する際に役立つ。
これらのデータは政府機関が提供しているため信頼性が高く、数値に基づいた客観的な分析が可能になる点が強みだ。ただし、自分が必要とする統計が存在しない場合や専門外の情報に触れる機会が少ない点には注意が必要だといえる。そのため、新聞やニュースサイトと併用して幅広い情報を補完する姿勢が望ましい。
各企業のIR情報
各企業のIR情報は、決算発表や経営戦略、中期経営計画などを公開する資料であり、企業の業績や事業方針を知るうえで極めて有用である。例えば、トヨタ自動車の決算資料からは自動車市場の販売台数や収益構造を読み取ることが可能、ソニーグループのIR情報からはエレクトロニクスやエンターテインメント分野の投資戦略を確認できる。
こうした情報を競合ごとに比較すれば、業界内でのポジションや成長領域を把握する手がかりになる。ただし、IR情報は株式公開企業に限られるため、未上場企業の動向は反映されない。また、IRはあくまで自社の現状と戦略を発信するものなので、市場全体の俯瞰には不向きであり、場合によっては企業側の都合で強調された情報が含まれることもある。
IR情報は競合分析や個別事例の把握に適しているが、業界全体を理解するには他の資料と併用する必要がある。
業界団体の公開資料
業界団体の公開資料は、特定の業界に特化した統計や市場動向を把握するのに非常に有効な情報源である。例えば、日本自動車工業会が発表する自動車の生産・販売台数や、日本化粧品工業連合会が公開する市場規模データは、業界の実態を数値で捉えることができる。
これらの資料は政策提言や調査報告を含むことも多く、経営戦略や製品開発の方向性を検討する際の基礎データとして活用できる。また、月次や四半期ごとに発行される速報性の高い情報もあり、最新の動きを迅速に把握できるのが利点である。
ただし、業界団体がまとめる資料であるため、特定の立場や方針に基づいた情報が強調される場合があることには留意が必要だ。業界全体を深く理解するためには、他の情報源と組み合わせて分析することが望ましい。
業界動向の調査をもっと効率化したい
最新の業界情報を“自動で収集・整理”するなら Aconnect
まずは資料を無料ダウンロードする
民間調査会社の調査データ
民間調査会社の調査データは、市場規模や成長予測、競合分析を詳細に把握するのに適した情報源である。例えば、NTTコムリサーチはICTや通信分野の最新調査を提供し、消費者動向や市場ニーズを明確に示している。また、マクロミルはマーケティングリサーチを強みとし、生活者の購買行動や意識調査を基にしたデータを発信しており、新商品開発や広告戦略に直結する情報が得られる。
官公庁の統計に比べて具体性や即時性が高く、ニッチな分野や海外市場まで幅広くカバーされる点も大きな特徴だ。ただし、調査方法やサンプル数によっては精度に差が生じるため、データの正確性を過信せず、複数の調査結果を突き合わせることが重要である。
シンクタンクの調査レポート
シンクタンクの調査レポートは、経済や産業に関する中長期的な動向を専門家が分析した資料であり、戦略立案や将来予測に活用できるのが特徴である。例えば、三菱総合研究所や日本総合研究所が発行するレポートは、エネルギー政策やデジタル化の影響といった社会全体の変化を踏まえて業界に与える影響を解説している。
民間調査会社が消費者アンケートや市場調査を通じて比較的短期的で具体的なデータを提供するのに対し、シンクタンクは政策提言や社会課題を含めた広い視点から分析を行うため、政治経済と産業の関係を理解するのに役立つ。
特に、人口動態や環境問題など個別企業では扱いにくいテーマに関しても、信頼性の高い知見を提供してくれる。業界動向を社会的背景と結びつけて把握するにはシンクタンクの調査レポートが有効である。
金融機関の調査レポート
金融機関の調査レポートは、銀行や証券会社が景気や産業を分析し発行する資料であり、業界全体の先行きやリスクを把握するのに有効である。例えば、三菱UFJリサーチ&コンサルティングや野村総合研究所が提供するレポートでは、金融市場の動向を踏まえた上で、自動車やエネルギーなど特定業界の将来性を予測している。
金融機関は資金の流れや投資動向を直接見ているため、レポートには市場の実態を反映した実用的な分析が多く含まれる。企業の資金調達や投資が盛んな分野に関しては、投資家や金融機関が注目していることを意味し、成長期待の高さを示す材料にもなる。
GoogleトレンドやSNSトレンド
GoogleトレンドやSNSトレンドは、検索数や投稿数の増減から人々の関心を把握できるツールであり、リアルタイムで世の中の注目テーマを捉えるのに適している。例えば、Googleトレンドで「電気自動車」を検索すれば、一定期間での検索数の推移や地域ごとの関心度を確認でき、市場での注目度を定量的に把握できる。
同様に、Xのトレンドを活用すれば、消費者や企業がどのテーマに反応しているかを即座に把握できる。ただし、専門的な分野はトレンドとして上がりにくいため、業界全体の深い分析には向かない。むしろ、社会的に話題となっている業界や製品の兆しを掴む入口として活用し、その後に専門紙や調査レポートで裏付けを取るのが効果的である。
書籍
書籍は業界動向を体系的かつ網羅的に学ぶのに適した情報源である。出版までに半年から1年以上を要するため速報性には欠けるが、その分内容は整理され、背景知識や周辺分野との関連まで含めて深く理解できるのが特長だ。
例えば、自動車業界に関する書籍であれば、歴史的な技術革新や政策の影響、グローバル市場の動向まで一貫して学ぶことができる。出版物は出版社の編集や校閲を経て裏付けが取られているため、信頼性の高い情報源として安心して利用できる。また、学術的な研究や新規事業の基礎知識を得たい場合にも有効である。
速報性を求めるならニュースサイトや調査レポートと組み合わせることで、書籍で得た知識を最新動向と照らし合わせながら活用でき、より精度の高い業界分析につなげられるだろう。
業界動向の調査をもっと効率化したい
最新の業界情報を“自動で収集・整理”するなら Aconnect
まずは資料を無料ダウンロードする
業界動向を調べる際に見るべきポイント
業界動向を正しく理解するには着目すべき観点がある。ここでは特に重要となる7つのポイントを紹介する。
売上高や生産量
売上高はその業界の市場規模や成長性を示し、生産量は供給力や需要動向を把握する指標となる。例えば、自動車業界ではトヨタやホンダといった主要メーカーの売上高や販売台数を比較することで、業界全体の景況感やシェアの変化が見えてくる。
また、半導体業界では需要増加に伴い生産能力の拡張が注目されることが多く、生産量の推移を追うことで供給不足や価格変動の兆候をつかめる。売上高や生産量のデータは決算発表や各省庁、業界団体の統計から入手でき、短期的な景気動向だけでなく、中長期的な成長予測にも役立つ。
マーケットシェア
マーケットシェアの大小は各企業の競争力や市場での立ち位置を示し、業界構造を理解する手がかりとなる。例えば、スマートフォン市場ではAppleとSamsungが高いシェアを持ち、ブランド力や技術力が競争優位につながっていることがわかる。
また、日本の飲料業界ではコカ・コーラやサントリーのシェアが大きく、新規参入企業が競争する際の障壁を示している。シェアの変動は、技術革新や消費者ニーズの変化、新規参入の有無によって大きく影響を受けるため、定期的に確認する必要がある。
ランキング
ランキングは業界の勢力図を一目で把握できる指標である。売上高、製造台数、顧客満足、特許件数など評価軸ごとに順位は変わるため、目的に合うランキングを選ぶことが重要だ。例えば、半導体の世界売上高ランキングで上位が入れ替わる局面は、最新技術の台頭や新素材の発見などが市場に反映された可能性を示す。
ただし、集計期間・対象・算出方法により結果は異なるため、出所を確認し単年の順位だけで判断しないことが肝要である。
合併・買収・協業の動き
合併・買収・協業の動きは、業界の構造変化や企業戦略を理解するうえで欠かせない。企業がどの分野に注力し、どの領域で競争力を高めようとしているのかを示すものであり、業界再編の兆しを読み取る手掛かりとなる。例えば、自動車業界ではEVや自動運転技術の開発を背景に、大手メーカーとIT企業の協業やスタートアップの買収が相次いでいる。
これにより、技術革新の方向性や資本の流れを把握することができ、自社の戦略立案や投資判断に役立つ。さらに、こうした動きを追うことで新しいビジネスモデルの登場や競合の強みを早期に察知できるため、長期的な経営計画に大きな影響を与える情報となる。
急激に変化する市場の動向を的確に捉えるには?
やった気で終わらせないための市場調査の教科書
「市場調査の教科書」を見てみる
政策と法規制
政策と法規制は業界動向を調べるうえで極めて重要だ。政府の補助金や優遇制度は新規参入や技術開発を後押しする一方、規制強化は市場の縮小や参入障壁の上昇につながる。例えば、再生可能エネルギー業界では固定価格買取制度が普及を加速させたが、制度改正により採算性が変化し、多くの企業の経営戦略に影響を与えた。
また、自動車業界では排ガス規制や安全基準の強化が電動化や自動運転技術の開発を促している。こうした政策や規制の変化を見落とすと、市場機会を逃すだけでなくリスクを被る可能性もある。そのため、官公庁の発表や法改正の動向を常にチェックし、自社の事業計画や投資判断に反映させることが重要だといえる。
経済指標
経済指標は景気や消費、雇用、物価といった経済全体の状況を数値で示すデータの総称であり、業界動向を把握する上では欠かせない。例えば、鉱工業生産指数の上昇は製造業全体の需要拡大を示し、雇用統計の改善は消費意欲の増加につながる。
逆に、金利の上昇や景気動向指数の悪化は投資の抑制や需要減退を予兆するものとして重要である。経済全体の流れを理解することで、自社が属する業界の成長性やリスクをより正確に見極められる。自動車業界や住宅業界のように景気に敏感な産業では、経済指標の変化が直接的に業績へ影響を及ぼすため、経営戦略や投資判断に積極的に活用する必要がある。
最新技術やトレンド
最新技術やトレンドは業界の未来を方向付ける重要な要素であり、新しい需要や市場の変化を生み出す原動力となる。例えば、自動車業界ではEVや自動運転技術の進展が従来のビジネスモデルを大きく変えつつあり、これをいち早く捉えることで競争優位性を確立できる。
また、IT分野では生成AIやクラウド技術の進化が新たなサービス開発や業務効率化の機会を提供している。こうしたトレンドを把握することは、単に流行を追うだけでなく、将来の事業戦略や投資の方向性を定める上で不可欠である。
急激に変化する市場の動向を的確に捉えるには?
やった気で終わらせないための市場調査の教科書
「市場調査の教科書」を見てみる
市場規模の算出方法
市場規模を正しく把握することは戦略立案の基盤となる。ここでは市場規模を算出する際に、実用的な方法を2つ紹介する。
売上高×業界シェア
市場規模を算出する代表的な方法の一つが、売上高に業界シェアを掛け合わせる手法である。具体的には、業界内の主要企業の売上高やシェアを調べ、その合計や推定値から市場全体の大きさを導き出すやり方だ。
例えば、自動車業界において特定メーカーの国内シェアが20%で年間売上高が2兆円であれば、単純計算で市場全体は約10兆円と見積もることができる。また、売上がわからない場合は、1台あたりの相場と販売台数からおおよその売上を算出することもできる。
この方法は比較的シンプルで実用的であり、特に既存市場の規模感を迅速に把握するのに適している。ただし、正確性を高めるには対象とする売上の範囲やシェアデータの信頼性を確認する必要がある。
フェルミ推定
フェルミ推定は、限られた情報から市場規模を素早く概算する手法である。母数を仮定し因数へ分解して掛け合わせるのがポイントだ。
例えば、国内のスマートグラス市場を推定するなら、人口1.25億人のうち対象年齢を60%、購入意向者5%、年間購入率1/3、平均単価3万円と置く。1.25億×0.6×0.05×1/3×3万円=約375億円となる。
仮定は粗いが桁感を掴むのに有効で、後に公開統計や調査で仮定を検証・更新して精度を高める前提で用いるべき手法である。
業界動向の調査をもっと効率化したい
最新の業界情報を“自動で収集・整理”するなら Aconnect
まずは資料を無料ダウンロードする
業界動向の分析に役立つフレームワーク
業界動向を深く理解するためには分析も重要だ。ここでは業界動向の分析に活用されている代表的な4つのフレームワークを紹介する。
3C分析
3C分析とは、顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の三視点から市場を体系的に捉え、差別化仮説を導く枠組みである。
例えば機能性飲料を新発売する場合、顧客では健康志向や購買頻度、許容価格を把握し、競合では主要ブランドの品揃え・価格・販促を比較し、自社では配荷力や原価構造、ブランド資産を検証する。三者のギャップから狙うべきセグメントと提供価値が明確になり、製品仕様や価格、チャネル施策へ具体化できる。
PEST分析
PEST分析とは、政治(P)・経済(E)・社会(S)・技術(T)の四領域から外部環境を構造的に把握し、機会と脅威を抽出する手法である。
例えばEV市場を検討するなら、補助金や排ガス規制の動向、金利や為替・資源価格の変化、脱炭素志向や移動需要の変容、電池コストや充電インフラの進展を一体で評価する。これにより参入時期や価格戦略、投資の優先順位を定量的に検討でき、シナリオ設計とリスク対策の土台となる。
SWOT・クロスSWOT分析
SWOT分析とは、自社の強み(Strength)・弱み(Weakness)と外部環境における機会(Opportunity)・脅威(Threat)を整理し、現状を多角的に把握するフレームワークである。例えば製造業において、高い技術力を強みとしつつ原材料価格の高騰を脅威と捉えれば、効率化投資や代替素材開発といった戦略が導かれる。
さらにクロスSWOT分析では、内部要因と外部要因を掛け合わせて具体的な戦略シナリオを導き出す。強みを活かして新市場に参入する積極策や、弱みを克服して脅威を回避する防衛策など、戦略の方向性を明確化できるのが特徴である。
ファイブフォース分析
ファイブフォース分析とは、ハーバード大学のマイケル・ポーターが提唱した競争環境の分析手法であり、業界の収益性や競争の激しさを左右する五つの力を体系的に評価するものである。具体的には、新規参入の脅威、代替品の脅威、買い手の交渉力、売り手の交渉力、そして既存競合間の敵対関係を対象とする。
例えば、航空業界を分析すると、低価格航空会社の参入(新規参入の脅威)、新幹線や高速バス(代替品の脅威)、燃料供給企業の価格交渉力(売り手の力)、旅行代理店や顧客の選択肢拡大(買い手の力)、そして大手航空会社同士の激しい価格競争(競合関係)といった要因を整理できる。この枠組みを使えば、業界の競争環境を客観的に理解し、自社が取るべき戦略を明確にできる。
業界動向を調べる際におすすめの情報ソース
| 媒体 | 種類 | 向いている情報収集 |
|---|---|---|
| 読売新聞 / 朝日新聞 / 毎日新聞 / 産経新聞 | 全国紙 | 政治・経済を含む社会全般の動向把握 |
| 日本経済新聞 | 経済・産業全体の動向や企業活動の把握 | |
| 日経産業新聞 | 専門紙 | ビジネス全般の新製品・新技術・企業戦略 |
| フジサンケイ ビジネスアイ | ビジネス全般の経済ニュースと企業情報 | |
| 日刊工業新聞 | 工業・製造業の技術動向や新製品情報 | |
| 日経ヴェリタス | 金融・投資・株式市場の動向分析 | |
| 保険毎日新聞 | 保険業界の制度、商品動向 | |
| 日本農業新聞 | 農業分野の政策、技術、需給動向 | |
| 水産新聞 | 水産業界の市場・流通・漁業関連情報 | |
| 日刊電波新聞 | 電機・エレクトロニクス産業動向 | |
| 週刊BCN | IT業界の製品動向やベンダー戦略 | |
| 交通新聞 | 交通・運輸・鉄道分野の政策と市場動向 | |
| 化学工業日報 | 化学産業の研究開発・市場動向 | |
| 電気新聞 | 電気・エネルギー業界の政策と事業動向 | |
| 科学新聞 | 科学技術の研究や政策動向 | |
| The New York Times / WSJ / FT | 海外紙 | 世界経済・海外市場・グローバル企業の動向 |
| 各種白書 (消費者白書、科学技術白書、エネルギー白書など) | 官公庁資料 | 業界全体の現状と将来展望の体系的把握 |
| 各省庁公開データ (経産省、資源エネルギー庁、総務省統計局など) | 市場規模、需給動向、政策関連データ | |
| 業界団体資料 (日本電機工業会、日本製薬工業協会など) | 業界団体 | 業界内統計、課題、提言 |
| 特許庁 / IPA など | 官公庁 | 技術開発や知財、セキュリティ動向 |
業界動向の調査をもっと効率化したい
最新の業界情報を“自動で収集・整理”するなら Aconnect
まずは資料を無料ダウンロードする
なぜ業界動向を調べることが重要なのか
業界動向を調べることは、企業が持続的に成長するための基盤となるため重要である。まず、市場環境を正しく把握することで、自社の立ち位置や成長余地を明確にできる。また、新規事業や商品開発においては、需要の高まりや未充足のニーズを把握することで競争力のある企画につなげられる。
さらには、景気変動や規制強化などのリスクを事前に把握すれば、適切な経営判断を下すことができる。その他にも、競合の戦略やシェアの変化を分析し、自社との差別化を図ることで市場優位性を確立できる。したがって、業界動向の調査は単なる情報収集ではなく、経営判断と戦略構築の土台となるため重要なのだ。
まとめ
業界動向を調べることは、自社のビジネスの方向性を定め、長期的に持続可能な経営を行うために欠かせない取り組みだ。特に製造業の研究開発や技術開発では、市場規模の把握や最新技術の動向を理解することが成果を左右する大きな要因となる。
業界調査は一度きりではなく、定期的に実施することで精度が高まり、リスク回避や新しい事業機会の発見にもつながる。当サイトが提供するAconnectは、検索エンジンで見つからない情報まで独自に収集することができ、約3万5000のサイトをクローリングして業界動向を把握するための強力な情報源となる。
日常的にツールを活用し、調査を習慣化することが、将来の競争優位性を築く鍵となるだろう。現在、無料トライアルも用意しているので、まずは気軽に試していただきたい。