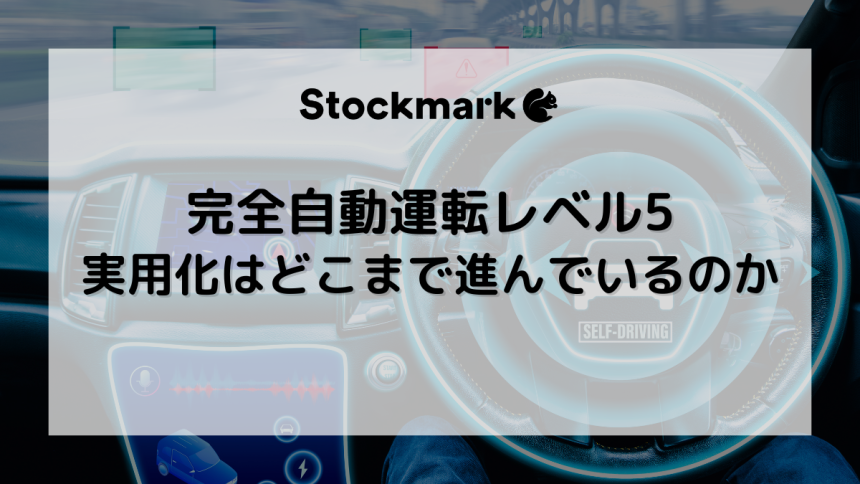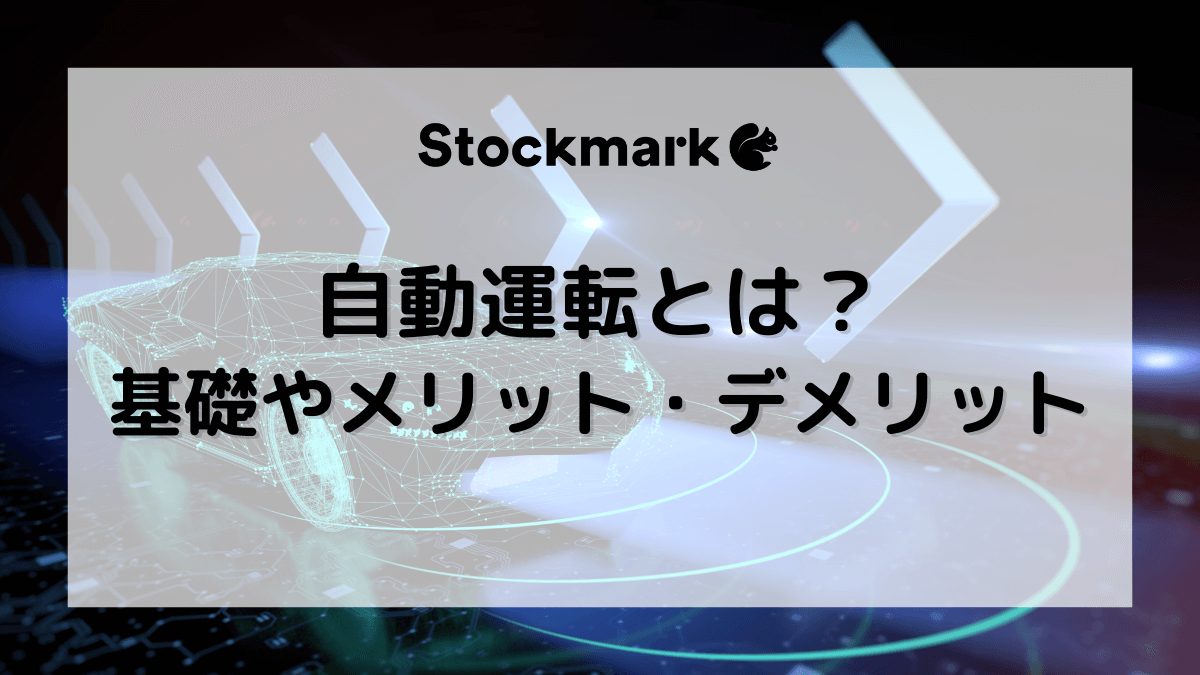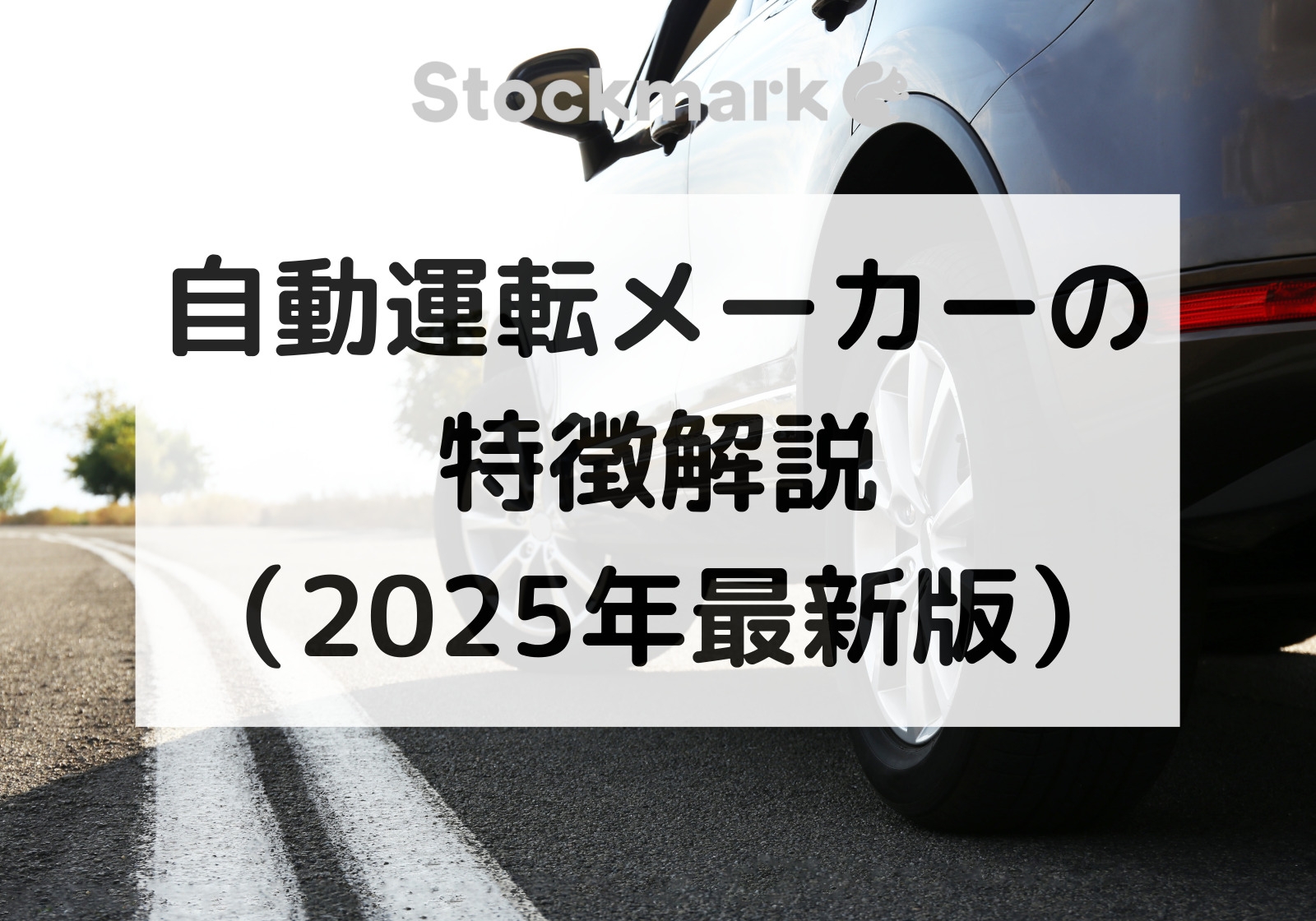完全自動運転が現実のものとなる日が、いよいよ現実味を帯びてきた。特定条件下での走行を自動化するレベル4までの実証・商用運用が始まる中、運転者の関与を一切必要としない自動運転レベル5の実現に注目が集まっている。
レベル5の世界では、運転席すら不要となり、車が自律的に目的地まで移動する。この技術は交通の効率化や高齢化社会の課題解決にもつながる革新である。本記事では、自動運転の基礎から各レベルの定義、そして完全自動運転の実現時期とその課題について詳しく解説したい。
「自動運転」市場のいまが3分でわかる!
市場動向、注目企業、技術トレンドを凝縮した「自動運転の最新動向レポート」無料配布中
レポートを読んでみる
目次
自動運転とは?
自動運転とは、ドライバーの操作なしに自動車が自律的に走行する仕組み、またはそのための技術を指す。車両に搭載されたセンサーやAIが周囲の状況を把握し、加減速やハンドル操作、停止などの判断を行うことで、安全かつ効率的な走行を可能にしている。近年は自家用車だけでなく、無人シャトルバスや配送ロボットなど、公共交通や物流分野にも応用が広がっている。
なお、自動運転技術は車だけに限らず、航空機、船舶、鉄道など他の移動手段にも古くから活用されてきた。なかでも、1981年に開業した神戸ポートライナーは、世界初の完全無人運転を実現した自動運転電車として知られている。
日本における自動運転の実用化と現在地については、詳しくは「自動運転とは?日本では現状どこまで進んでいる?メリットやデメリットを解説」の記事をご覧いただきたい
自動運転のレベル分けの定義とは?
| レベル | 状態 | 運転主体 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 0 | 運転自動化なし | 運転者(人) | 運転者が全ての運転タスクを実施 |
| 1 | 運転支援 | アクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作のどちらかが、部分的に自動化された状態 | |
| 2 | 部分運転自動化 | アクセル・ブレーキ操作およびハンドル操作の両方が、部分的に自動化された状態 | |
| 3 | 条件付運転自動化 | システム | 限定条件下でシステムが全ての運転タスクを実行(作動継続が困難な場合は運転者が対応) |
| 4 | 高度運転自動化 | 限定条件下でシステムが全ての運転タスクを実行 | |
| 5 | 完全運転自動化 | システムが全ての運転タスクを実施 |
自動運転のレベルは、レベル0からレベル5までの6段階に分けられており、どの程度ドライバーが関与するかによって分類されている。これらの基準は、アメリカのSAE International(米国自動車技術者協会)が2016年に策定した規格「J3016」に基づくもので、世界的な標準とされている。
日本においても、2018年に公開されたJASO TP18004(自動車技術会による日本語訳版)に準拠し、国内外で共通のフレームワークとして運用されているのが特徴だ。各レベルでは、運転支援の範囲から完全自動運転に至るまで、システムが担うタスクや責任の範囲が明確に区分されており、自動運転車の普及や法整備、技術開発の指針にもなっている。今後、自動運転技術の進展を正しく理解するうえで欠かせない基準である。
自動運転技術の概要と市場動向、開発に携わる注目企業をまとめた資料を公開中!
資料(無料)を見てみる
各自動運転のレベルと特徴
自動運転は6つのレベルに分けて段階的に定義されており、それぞれで運転操作の自動化範囲が異なる。ここでは、完全自動運転に至るまでの各レベルとその特徴を6つ紹介する。
自動運転レベル0(運転自動化なし)
自動運転レベル0は、運転操作に関して一切の自動化が行われていない状態を指す。これは一般的に従来型の自動車に該当し、アクセルやブレーキ、ハンドル操作、車線変更などすべての運転行為をドライバー自身が行わなければならない。運転支援機能として警告音や表示による注意喚起が搭載されている場合もあるが、それらは運転の自動化とは見なされない。完全に人間の判断と操作に依存して走行するため、誤操作や注意力の低下による事故のリスクも相対的に高くなる。
自動運転レベル1(運転支援)
自動運転レベル1は、ドライバーの運転操作を一部補助する機能を備えた車両を指す。人間が運転の主体であり、加速・減速・ハンドル操作のいずれか一つをシステムがサポートするが、すべてを任せることはできない。代表的な機能には、前方車両との車間距離を一定に保ちつつ速度調整を行うアダプティブクルーズコントロール(ACC)や、車線の中央を維持するようステアリング操作を補正する車線維持支援システム(LKAS)がある。これらはドライバーの負担軽減に寄与するが、常に運転状況を監視し、必要に応じて操作を行う責任はドライバーにある。
自動運転レベル2(部分運転自動化)
自動運転レベル2は、加減速とハンドル操作の両方をシステムが制御できる部分運転自動化の段階である。ただし、あくまで運転の責任はドライバーにあり、常に周囲の状況に注意を払う必要がある。高度駐車アシスト(APA)や交通標識認識(TSR)といった先進運転支援システム(ADAS)も搭載されており、運転支援の精度が向上している。
高速道路での渋滞時など、一定の条件下ではステアリングから手を離せる「ハンズオフ機能」を搭載する車種も登場しており、これらは「レベル2.5」と呼ばれることもある。
自動運転レベル2を実現している車(例)
| メーカー | システム | 車種 |
|---|---|---|
| トヨタ自動車 | Toyota Safety Sense | アルファード、プリウス、カローラ、ヴェルファイア |
| ホンダ | Honda SENSING | ヴェゼル、N-BOX、フリード |
| 日産自動車 | ProPilot 2.0 | 日産アリア、セレナ、スカイライン |
自動運転レベル3(条件付き運転自動化)
自動運転レベル3は、一定の条件下において車両が加減速・ハンドル操作などすべての運転操作を担う「条件付き運転自動化」の段階である。運転の主体はドライバーからシステムに移り、ドライバーは前方から目を離す「アイズオフ」の状態が可能となる。ただし、システムが運転継続できないと判断した場合には、速やかにドライバーが運転を引き継がなければならない。
高速道路での渋滞時や一定の速度範囲内など、限定された環境での使用にとどまり、完全な自動運転には至っていないが、レベル2までの技術とは明確に一線を画す進化といえる。
自動運転レベル3を実現している車(例)
| メーカー | システム | 車種 |
|---|---|---|
| ホンダ | Honda SENSING Elite | LEGEND ※限定100台のリース販売のため2022年1月生産終了 |
| メルセデス・ベンツ | DRIVE PILOT | Sクラス、EQS |
自動運転レベル4(高度運転自動化)
自動運転レベル4は、高度運転自動化に分類され、特定のエリアや状況に限り、車両がすべての運転操作をシステムだけで完結できる段階である。レベル3との大きな違いは、緊急時も含めて人間の介入を必要とせず、システムが自律的に安全な停止判断を行う点にある。このため、ドライバーは判断を完全に任せた「ブレインオフ」の状態で乗車できる。
ただし、対象となる走行エリアはジオフェンスと呼ばれる地理的に限定された範囲内にとどまり、それ以外の場所では手動運転が求められる。なお現時点では、日本国内においてレベル4の市販車は存在していないが、限定地域での実証実験は進んでいる。
自動運転レベル5(完全運転自動化)
自動運転レベル5は、完全運転自動化を指し、すべての道路環境や天候条件において、システムが人間の関与なく自律的に運転を行う段階である。ドライバーの存在が不要になるため、運転席やハンドル、アクセル、ブレーキといった従来の操作装置が車両に搭載されない可能性もあり、車内レイアウトの自由度が飛躍的に高まる。
都市部の混雑した道路や未舗装の道、夜間や悪天候といった状況でも同様に安全な走行が求められるため、高度なAIとセンサー技術、通信インフラの整備が前提条件となる。現段階では技術的・法的な課題が多く、市販車としての実現には至っていないが、自動運転の最終目標とされている。
「自動運転」市場のいまが3分でわかる!
市場動向、注目企業、技術トレンドを凝縮した「自動運転の最新動向レポート」無料配布中
レポートを読んでみる
完全自動運転レベル5の登場はいつ?
完全自動運転を実現するレベル5の登場時期については、現在も明確な答えが出ていないのが実情だ。多くの自動車メーカーやIT企業が開発に取り組んでおり、技術的な進歩は加速しているが、依然として課題は多い。
例えば、悪天候や複雑な交通状況などあらゆる環境で安全に走行できるシステムの構築には、高度な人工知能やセンサー技術のさらなる進化が必要だ。加えて、法律やインフラの整備、社会的受容など技術以外の障壁も大きい。
現在、日本を含む複数の国でレベル4の実証実験が進んでおり、特定エリア内での無人運転は可能になりつつあるが、どこでも自由に走行できるレベル5の普及にはかなりの時間を要すると考えられる。一般的には2030年代の実現が一つの目安とされているが、その時期は大いに前後する可能性がある。
そもそも完全自動運転は実現可能なのか?
完全自動運転を実現するには、現在の技術水準を大きく超えるブレイクスルーが求められる。特定エリアのみを走行するレベル4でさえ、高精度3次元地図の活用や繰り返しの実証実験を経てようやく商用化に至っている。
これをあらゆる場所・環境で運転操作を完全に任せられるレベル5へと拡張するには、未知の道路や状況でも安全に走行できるAIとセンサーが必要となる。例えば、冬の峠道や区画線のない道路、歩行者や自転車が頻繁に飛び出すような都市部でも対応できる柔軟性が求められる。
そのためには、高度な物体検知・状況予測・判断力を備えたAIの搭載が不可欠であり、現状このレベルに到達している事業者は存在しない。なお、Google系Waymoの元CEOであるジョン・クラフチック氏も「完璧な自動運転は実現しない」と公言しており、実際、多くの専門家が2040年代以降の実現を想定している。技術進化に加え、社会・法制度の整備も不可欠である以上、レベル5の到来にはなお長い道のりがある。
まとめ
現在の技術では、完全自動運転の実現にはまだ程遠いが、レベル3、レベル4と着実に進展していることは間違いないだろう。レベル5では、路面環境だけでなく天候や場所、交通状況など、複雑で変則的な状況を予期しなければならず、気の遠くなるようなサンプルデータの収集と分析が必要となる。しかし、まだ誰も到達できていない領域だからこそ、どの会社にもビジネスチャンスがあるといっても良い。
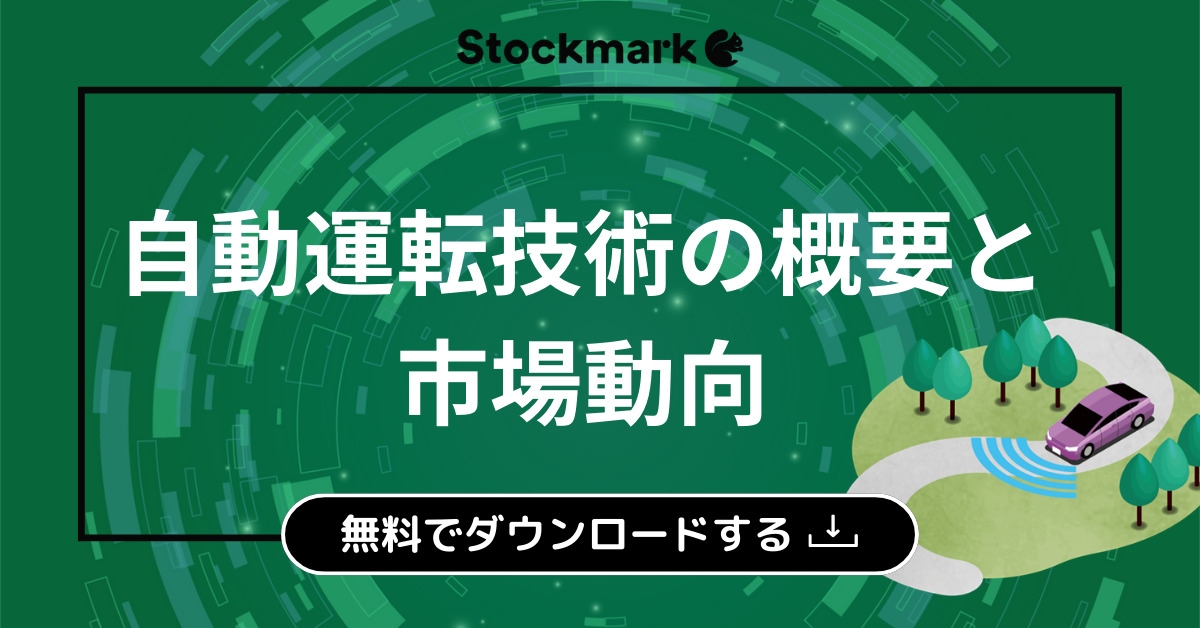
参考記事
・一般社団法人日本機械学会「鉄道における自動運転のあゆみと将来ー自動車の自動運転と対比してー」
https://www.jsme.or.jp/kaisi/1241-21/
・内閣官房IT総合戦略室「自動運転に係る制度整備大綱(概要)」
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/auto_drive_point.pdf
・国土交通省「自動運転車両の呼称」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01asv/report06/file/siryohen_4_jidountenyogo.pdf