自動運転や電動化といった技術の進展により、自動車に搭載される半導体の数は飛躍的に増加している。中でも電気自動車や先進運転支援システム(ADAS)の普及が、車載半導体市場の急拡大をけん引している。自動車に用いられる半導体は、パワートレイン制御、走行支援、通信、エンタメシステムなど多岐にわたり、その種類も多様である。特にマイコン、パワー半導体、各種センサー、通信モジュールといった分野は開発競争が激しく、国内メーカー各社も注力している領域だ。
本記事では、自動車向け半導体の役割や用途、種類、そして市場動向について解説したい。車載半導体に関心のある技術者や製造業関係者にとって、現状と今後の展望を把握する手がかりとなる内容になるだろう。
「2026年 半導体市場の予測まとめ」を配布中!
▶︎資料(無料)を見てみる
目次
自動車向け半導体(車載半導体)とは何か?
自動車向け半導体とは、自動車に搭載される各種電子制御システムや機能を実現するために使用される専用の半導体製品を指し、「車載半導体」とも呼ばれる。例えば、エンジン制御ユニット(ECU)、ブレーキ、ステアリング、エアバッグ、カメラやレーダーなどの先進運転支援システム(ADAS)、ナビゲーションや車載通信など、多様な領域で用いられている。
近年は電気自動車(EV)や自動運転技術、コネクテッドカーの普及により、車載半導体の搭載量が急増しているのが特徴だ。家庭用や産業用の半導体と異なり、車載用途では極端な温度変化、振動、湿度などの過酷な使用環境下でも長期間にわたって安定動作する高い信頼性が求められる。このため、AEC-Qといった国際的な車載部品の品質規格に準拠した設計・製造が必須とされる。信頼性、耐久性、長寿命性を兼ね備えた車載半導体は、現代の自動車技術を支える重要な要素といえる。
「2026年 半導体市場の予測まとめ」を配布中!
▶︎資料(無料)を見てみる
電気自動車(EV)と半導体の関係
電気自動車(EV)と半導体は極めて密接な関係にあり、もはや切り離して考えることはできない。EVはガソリンエンジンではなく電気を動力源とするため、モーターの駆動制御、バッテリーの充放電管理、インバータの制御、エネルギー回生といった精密な電力制御が必要になる。これらの機能を支えているのが、半導体だ。
さらに、EVは自動運転技術やコネクテッド機能を統合するケースも多く、センシング、通信、情報処理といった用途でも膨大な数の半導体が使われている。加えて、車内の快適性を高めるための空調、照明、エンターテインメントなどの機能も高度化しており、その制御にも半導体が用いられている。EVの普及が進むほど、車載半導体の重要性と搭載量は加速度的に増しているのが現状だ。
自動車向け半導体の市場規模と動向
自動車向け半導体の市場は、今後数年間で急速に拡大すると予測されている。Automotive Semiconductor Global Market Report 2025によれば、世界市場規模は2029年には1,067億6,000万米ドルに到達し、年間平均成長率(CAGR)は12.2%に達する見込みだ。
この成長を牽引する主な要因には、自動運転車や電気自動車の普及、さらに安全機能や車載インフォテインメントなどの高機能化が挙げられる。また、各国政府による自動車産業への補助金拡充も、車載半導体の開発・導入を後押ししている。一方、過去にはCOVID-19の影響で半導体の供給網が混乱し、深刻な不足に陥った。しかし2024年ごろから供給は回復基調に入り、2025年には正常な水準に戻ったとされている。ただし、米中対立や輸出規制などの不安定要素は依然として残っており、供給体制の強靭化と安定確保が今後の課題といえる。
「2026年 半導体市場の予測まとめ」を配布中!
▶︎資料(無料)を見てみる
自動車に用いられている半導体の種類
自動車には、安全性や快適性、走行性能を支えるために多様な半導体が搭載されている。その中でも特に重要な5つの種類について解説する
通信モジュール
通信モジュールは、自動車と外部環境をつなぐ中枢的な役割を担う半導体で、インターネットやクラウド、他の車両、さらには信号機や道路センサーなどのインフラと双方向でデータ通信を行える。例えば、LTEや5G回線を介して最新の地図情報や交通渋滞情報をリアルタイムに取得し、ナビゲーションや自動運転システムに反映できる。また、Wi-FiやBluetoothは、スマートフォンや車載デバイスとの接続を通じて快適なインフォテインメント環境を実現する。こうした通信モジュールの進化は、自動運転やコネクテッドカーの発展を支える基盤であり、今後も高性能化と低遅延化が求められる分野である。
マイコン(マイクロコントローラー)
マイコン(マイクロコントローラー)は、自動車の電子制御システムを統括する中枢的な半導体であり、車両の頭脳ともいえる存在だ。CPUによる演算処理、メモリによるデータ保存、入出力ポートによる各種機器との信号のやり取り、タイマーや通信機能などを1つのチップに集積し、限られたスペースと消費電力で高度な制御を実現する。近年では、自動運転や高度運転支援システム(ADAS)の進化に伴い、より高速かつ高信頼性のマイコンが求められており、演算能力や耐環境性の向上が進んでいる。
センサー
センサーは、自動車の安全性や快適性、性能を支える基盤となる半導体であり、車両内外の状況を正確に把握して電子制御システムに情報を送る役割を担う。例えば、加速度センサーは衝突時の減速度を検知してエアバッグの展開を制御し、車速センサーは走行速度を測定してABSやトラクションコントロールに活用される。ブレーキ圧センサーは制動力を監視し、温度センサーはエンジンやバッテリーの温度を管理して過熱を防ぐ。さらに、光センサーは周囲の明るさを検知して自動でヘッドライトを点灯させるほか、自動運転や高度運転支援システム(ADAS)ではカメラやLiDAR、ミリ波レーダーなどの高精度センサーが不可欠である。これらは車両の状態や周囲環境をリアルタイムに把握し、マイコンやAIプロセッサに情報を提供することで、的確な判断と制御を可能にする。
パワー半導体
パワー半導体は、高電圧や大電流を効率的に制御・変換するための半導体であり、自動車の電動化において欠かせない重要部品である。主な役割は電力のスイッチングで、直流電圧の変換や直流と交流間の変換(インバータ)、交流の周波数変換などを担う。電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)では、バッテリーからの直流電力をモーター駆動用の交流に変換したり、回生ブレーキによって発生した交流を直流に戻してバッテリーに充電する際に利用される。また、エアコンやパワーステアリングなど車載機器への電力供給も、パワー半導体による制御があってこそ効率的に行える。
メモリ
車載用メモリは、自動車の電子制御システムを安定かつ高速に動作させるための記憶装置だ。エンジン制御や走行支援、自動運転などの高度な機能は、膨大な量のソフトウェアや制御プログラムによって成り立っており、これらを保存する役割を担うのがメモリだ。さらに、各種センサーから取得したリアルタイムのデータ、カーナビ用の地図情報、過去の走行履歴や車両状態のログなども記録され、必要に応じて即座に呼び出される。車載環境では高温や振動など過酷な条件にさらされるため、高い信頼性と耐久性が求められ、DRAMやフラッシュメモリなど車載向けに特化した製品が採用される。
半導体は自動車のどこに使われている?用途について
自動車に欠かせない半導体は、単に電子制御を担うだけでなく、走行性能や快適性、安全性にも深く関わっている。本章では、具体的にどこに使われているのか、代表的な3つの用途について紹介する。
「2026年 半導体市場の予測まとめ」を配布中!
▶︎資料(無料)を見てみる
パワートレイン
パワートレインとは、エンジンやモーター、トランスミッションなど、車両の動力を車輪に伝える重要な機構の総称である。この領域では、高度な電子制御が求められ、半導体が不可欠な役割を果たしている。特に、エンジン制御ユニットにはマイコンや各種センサーが搭載されており、燃料噴射量や点火タイミング、吸排気の調整といった動作をミリ秒単位で正確に制御している。

これにより、燃費の向上や排出ガスの削減が実現され、環境性能の高い車づくりが可能になっている。加えて、ハイブリッド車や電気自動車では、電力の制御や回生ブレーキの制御にも多くの半導体が使用されており、エネルギー効率を最大化するための頭脳として機能している。現代の自動車において、パワートレインの電子制御はもはや不可欠な存在であり、半導体がなければこうした緻密な電子制御や環境規制への対応は難しいだろう。
走行支援
走行支援は、自動車の安全性と運転者の負担軽減を目的としたシステムであり、その中核には多数の半導体が搭載されている。エアバッグの作動制御やアンチロックブレーキシステム(ABS)、電子制御ブレーキ、衝突被害軽減ブレーキといった基本的な安全装備には、各種センサーや制御用マイコン、そして電力を制御するパワー半導体が用いられている。
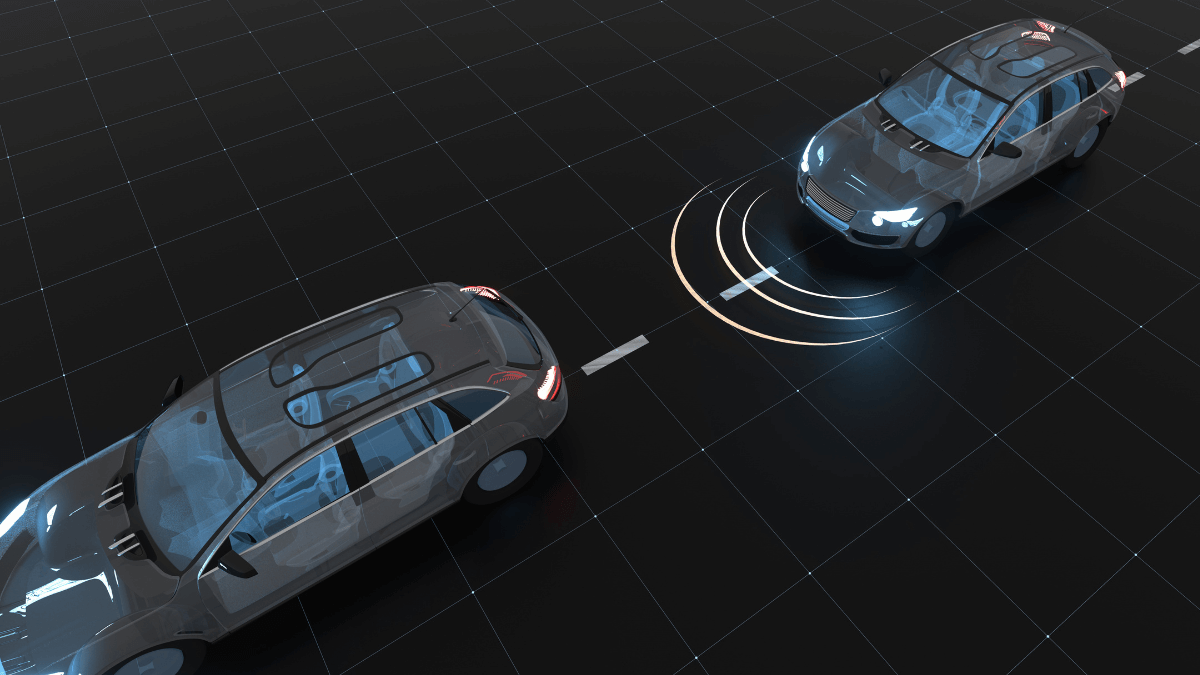
近年では自動運転レベルの高度化に伴い、SoC(システム・オン・チップ)やAI専用プロセッサ、LiDARやミリ波レーダー向けの専用半導体の搭載も進んでいる。これらは画像や信号の処理能力を飛躍的に高め、認識精度や判断速度を向上させることで、より安全で快適な走行支援環境の実現に貢献している。
インフォテインメント
インフォテインメントは、情報(Information)と娯楽(Entertainment)を組み合わせた言葉で、車内で情報提供と娯楽を融合させる機能を担うシステムを指す。具体的には、カーナビゲーションや高音質オーディオ、タッチパネル式のインフォメーションディスプレイ、スマートフォンとの連携機能、さらに車車間・路車間通信を実現するV2X(Vehicle to Everything)といった機能が含まれる。

これらのシステムには、高性能なプロセッサやグラフィックチップ、メモリ、通信モジュールなど、さまざまな車載半導体が不可欠である。特に近年は、音声認識やジェスチャー操作、クラウドと連動したオンラインサービスなどの搭載が進み、自動車は単なる移動手段から“走るスマートデバイス”へと進化している。その根幹を支えているのが、インフォテインメント分野で活用される高機能な半導体群である。
車載半導体を開発している企業やメーカー
車載半導体分野では、日本を代表する大手企業が独自技術と開発力を発揮している。ここでは、自動車や電子機器の両分野で強みを持つ3つの企業を紹介する。
「2026年 半導体市場の予測まとめ」を配布中!
▶︎資料(無料)を見てみる
トヨタ自動車
トヨタ自動車株式会社は愛知県豊田市に本社を置く自動車メーカーで、1937年創業、世界各地で生産・販売を行う。半導体の内製化には1980年代後半から着手し、1988年に社内ME開発部を発足、1989年には愛知県の広瀬工場を稼働させた。近年はCASE対応として2020年、デンソーと共同で次世代車載半導体の研究・先行開発会社MIRISE Technologies(ミライズ テクノロジーズ)を設立。電動車向けパワーモジュールや自動運転の周辺監視センサー用途の半導体技術開発を進めている。
日産自動車
日産自動車は本社を横浜市西区に置く日本の大手自動車メーカーで、世界各国で乗用車や商用車を展開している。車載半導体分野では、ルネサスエレクトロニクスとの強固なパートナーシップを構築し、同社製の半導体をADAS、パワートレイン制御、ボディ制御などに広く採用している。また、日本の自動車メーカーや電装部品メーカー、半導体関連企業が共同で設立した自動車用先端SoC技術研究組合(ASRA)に参画し、チップレット技術を活用した次世代車載半導体の研究開発を進めている。
三菱電機
三菱電機は東京都千代田区に本社を置く総合電機メーカーで、パワー半導体分野において世界的なリーダーとして知られている。1952年にパワー半導体の開発に着手し、現在ではSi(シリコン)とSiC(炭化ケイ素)の両方に対応した幅広いパワーモジュール製品を展開している。特にSiCパワー半導体では世界に先駆けてエアコンにSiCモジュールを搭載するなど先進的な取り組みを行ってきた。近年は需要拡大に対応するため、熊本県に8インチSiCウェハ対応の新製造拠点を設立予定で、2026年度までに生産能力を2022年度比で約5倍に拡大する計画だ。
まとめ
自動車向け半導体は、エンジン制御や安全装置、インフォテインメント、通信機能などあらゆる車載システムの中枢を担い、現代の自動車の性能や価値を大きく左右している。特に電動化や自動運転、コネクテッドカーの普及に伴い、車載半導体の性能向上と安定供給は自動車メーカーにとって喫緊の課題となっている。近年の半導体不足は、自動車生産の停滞や納期遅延といった深刻な影響を与え、改めてその重要性を浮き彫りにした。
今後は、SiCやGaNといった次世代材料の活用や、高度な製造プロセスによる小型・高性能化が進むと同時に、サプライチェーンの多元化や国内生産拠点の強化が進められる見込みだ。こうした動きは、自動車産業と半導体産業の結びつきをより強固なものとし、未来のモビリティ社会の基盤を形成することになるだろう。









