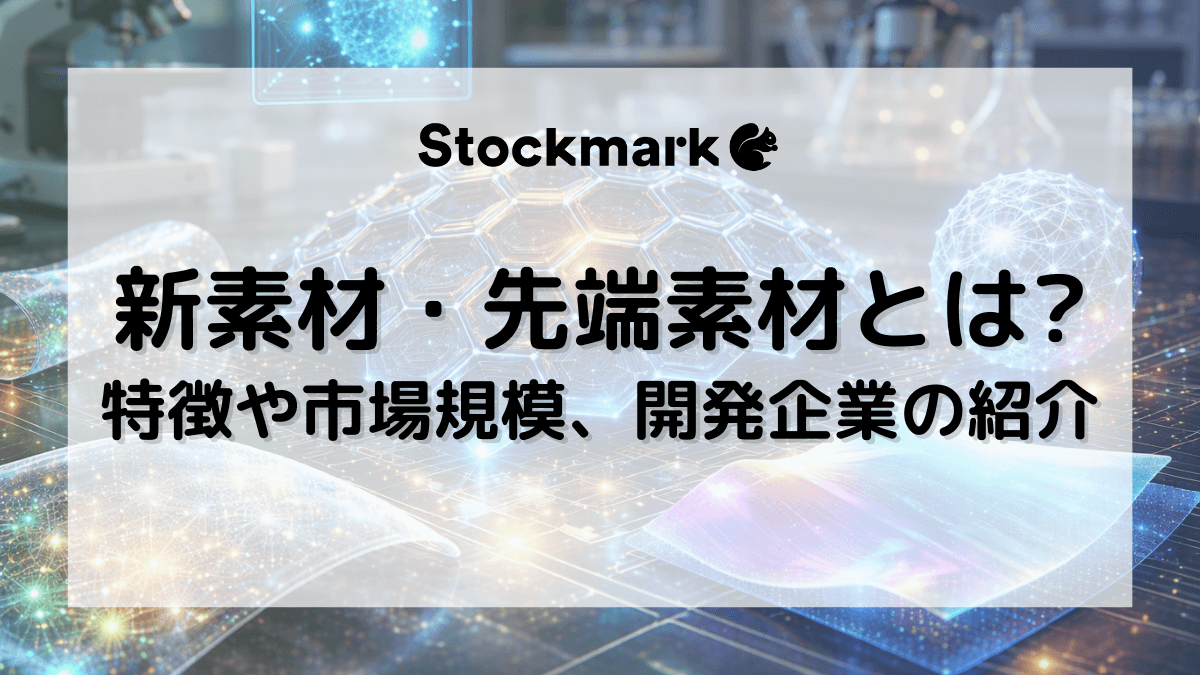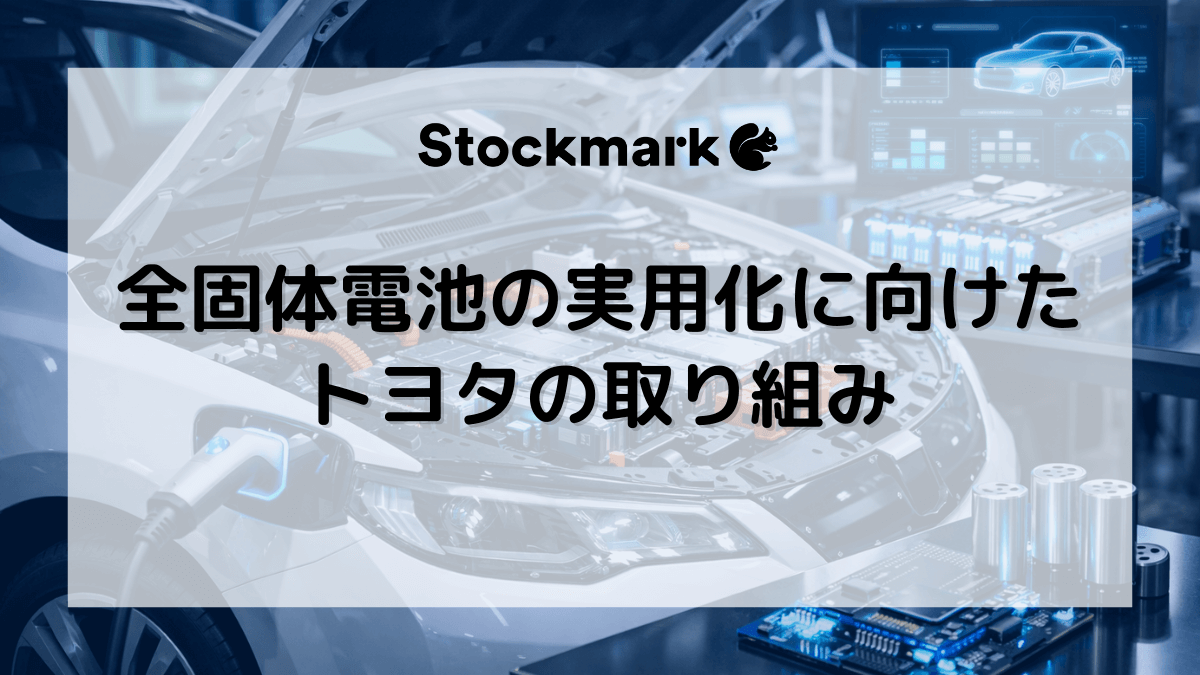再生可能エネルギー(再エネ)とは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど、自然の力を利用して繰り返し生み出すことができるエネルギーを指す。化石燃料に依存した従来のエネルギー供給は、CO₂排出量の増加や資源枯渇といった課題を抱えており、世界的な脱炭素化の流れの中で再エネの導入拡大は不可欠となっている。
日本においても2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、政府や企業が再生可能エネルギーの普及に向けた政策や投資を強化している。再エネの導入は、環境負荷の低減だけでなく、エネルギー自給率の向上や地域経済の活性化にも寄与する重要な取り組みである。
本記事では、再生可能エネルギーとは何かを基礎から整理し、その種類や特徴、導入のメリット、普及を支える最新の取り組み事例までをわかりやすく解説する。
目次
再生可能エネルギー(再エネ)の定義や意味とは?
再生可能エネルギー(再エネ)とは、自然の働きによって繰り返し再生され、枯渇することなく持続的に利用できるエネルギーの総称である。主に太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどが含まれ、自然界において常に存在するエネルギー源を活用して発電や熱利用を行う点が特徴である。
これらは化石燃料のように限りある資源ではなく、CO₂を排出しない、もしくは極めて少ないため、地球温暖化対策やエネルギー自給率向上の観点から世界的に注目されている。再エネの利用は現代技術による発展が顕著だが、その起源は古代にまで遡る。
人類は古くから木材や動物の糞を燃料として活用し、水車で粉を挽き、帆船で風を利用して移動してきた。これらは再生可能エネルギーの原点であり、自然の力を人間の生活に取り入れる試みの始まりである。現代では、これらの自然エネルギーを科学的に制御し、安定的に供給する仕組みとして再生可能エネルギーが位置づけられている。
再生可能エネルギーとパリ協定の関係
パリ協定とは、地球温暖化の深刻化を受けて2015年に国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)で採択された国際的な気候変動対策の枠組みである。産業革命前と比較して地球の平均気温上昇を2℃未満に抑え、さらに1.5℃に抑える努力を行うことを目標としている。
各国は自主的に温室効果ガスの削減目標(NDC:国別削減目標)を設定し、定期的に進捗を報告・見直す仕組みが導入されている。この目標の達成には、化石燃料の使用削減とともに、再生可能エネルギーの導入拡大が不可欠であり、再エネは脱炭素社会を支える中心的なエネルギー源として位置づけられている。
現在、パリ協定には中国、インド、EU、日本、カナダなどを含む195か国が加盟し、世界の温室効果ガス排出量のほぼ全体を網羅している。一方で、排出量が世界第2位のアメリカは2025年1月に離脱を表明し、国際的な枠組みへの影響が懸念されている。
再生可能エネルギーの発電方法の種類
再生可能エネルギーの発電方法には、自然の力を活用した多様な種類が存在する。日本の「エネルギー供給構造高度化法」では、永続的に利用できるエネルギーとして太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱や地中熱など自然界の熱、そしてバイオマス(動植物に由来する有機物)の7種を再生可能エネルギーと定義している。
これらをさらに細分化すると、太陽光発電や風力発電、水力発電、地熱発電、太陽熱発電に加え、空気中や地中の熱を利用したヒートポンプ発電、木材や動植物由来の有機物を燃料とするバイオマス発電など、10種類程度に分類される。いずれも化石燃料に比べてCO₂排出量が極めて少なく、エネルギーの持続可能性を高める手段として重要な位置を占めている。
| 種類 | メリット | 課題 | 主な利用例 |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電 | 燃料不要・設置が容易・家庭や工場でも導入可 | 天候・昼夜に依存、設置面積が必要 | 住宅用ソーラー、メガソーラー |
| 風力発電 | 発電コストが低下傾向、CO₂排出ゼロ | 風況に左右される、騒音・景観問題 | 陸上・洋上風力発電 |
| 水力発電 | 安定供給可能、技術成熟 | ダム建設による環境負荷・立地制約 | ダム式・中小水力 |
| 地熱発電 | 天候に左右されず安定稼働 | 開発コスト高、温泉地との調整必要 | 火山地帯での発電所 |
| 太陽熱利用 | シンプルで効率的、電力変換不要 | 夜間・冬季は効率低下、蓄熱が課題 | 太陽熱温水器、給湯・暖房 |
| 大気中・地中の熱利用 | 季節を問わず利用可、CO₂削減効果大 | 導入コスト高、地中熱は初期工事必要 | エアコン、地中熱ヒートポンプ |
| バイオマスエネルギー | 廃棄物削減、カーボンニュートラル | 燃料収集コスト、燃焼でCO₂発生 | バイオ発電、バイオ燃料、バイオガス |
詳細な情報を知りたい方は再生可能エネルギー(自然エネルギー)の種類一覧とそれぞれの特徴を確認いただきたい。
再生可能エネルギーの電力比率・割合
世界や各国で再生可能エネルギーの導入がどの程度進んでいるのかは、エネルギー政策の方向性を知る上で重要である。ここでは、世界全体をはじめ主要3地域の電力比率を紹介する。
世界全体
世界全体での再生可能エネルギーの割合は年々拡大しており、脱炭素化への流れが着実に進展している。国際エネルギーシンクタンクのEmberがまとめた『世界電力レビュー2025』によると、2024年時点で原子力を含む低炭素電力は世界全体の発電量の約40.9%を占め、1940年代以来初めて40%台を突破した。
再生可能エネルギーの内訳では、水力発電が依然として最大の割合を占め約14%、次いで風力が約8.1%、太陽光が約6.9%となっている。また、Enerdataの統計によれば、再生可能エネルギー全体の割合は2010年以降、毎年上昇を続け、2024年には世界の電力構成の約32%に達した。
これは、各国がパリ協定の目標達成に向けて再エネ導入を積極的に進めた成果であり、今後も電力供給の中心的役割を担うことが見込まれる。
ヨーロッパ
欧州連合(EU)では、再生可能エネルギーが電力供給の中心的な役割を担う段階へと移行している。EU統計局(Eurostat)の2024年データによると、再生可能エネルギーの割合は総発電量の約46.9%に達し、過去最高を記録した。

これは、風力や太陽光などの発電量が大幅に増加した結果であり、特に化石燃料依存からの脱却が着実に進んでいることを示している。国別に見ると、デンマークが再生可能エネルギー比率88.4%と最も高く、次いでポルトガルが87.5%、クロアチアが73.7%と続いた。
これらの国々では、風力や水力の積極的な導入が電力供給の安定化とCO₂削減に大きく寄与している。EU全体としても、2030年までに再エネ比率を60%に引き上げる目標を掲げており、持続可能なエネルギー転換が加速している。
日本
日本における再生可能エネルギーの導入は、環境エネルギー政策研究所(ISEP)の調査によると、2024年の総発電量に占める自然エネルギーの割合は26.7%となり、前年の25.7%から1ポイント上昇した。

内訳を見ると、太陽光発電が11.4%と最も高く、次いで水力発電が7.9%、バイオマス発電が5.9%、風力発電が1.13%を占めた。これらはいずれも前年から微増しており、国内における再エネ利用拡大の傾向が続いている。
一方、火力発電の割合は65.1%まで低下し、2016年比では18ポイント以上減少した。原子力発電は全体の約8.2%にとどまっており、依然として再エネと火力が日本の電力構成の中心である。政府は2030年度に再エネ比率を36〜38%まで高める方針を掲げており、制度改革と技術革新によるさらなる拡大が期待されている。
アメリカ
アメリカでは再生可能エネルギーの導入が急速に進み、電力構成における存在感が一層高まっている。Emberの『US Electricity 2025 – Special Report』によると、太陽光発電と風力発電の合計が全電力供給の約17%を占め、史上初めて石炭火力の発電量を上回った。
これは、連邦および州レベルでの再エネ支援政策や、企業によるグリーン電力調達の拡大が寄与した結果である。しかし、2025年1月に発足した第2次トランプ政権はパリ協定からの離脱を宣言し、同年7月には「大型減税・歳出法」を施行。
これにより、インフレ抑制法(IRA)で実施されていた脱炭素関連の税控除制度が前倒しで終了し、EV購入時の最大7,500ドルの税額控除も廃止された。こうした政策転換により、今後の再生可能エネルギー市場の成長ペースには一時的な鈍化が懸念されている。
再生可能エネルギーのメリットや特徴
再生可能エネルギーには、持続可能な社会づくりに欠かせない重要な利点がある。ここでは、代表的なメリットを3つ紹介する。
資源が枯渇する心配がない
再生可能エネルギーを活用する最大のメリットは、資源が枯渇する心配がないことだ。太陽光、風力、地熱、水力、バイオマスといった再生可能エネルギーは、地球上で絶えず繰り返される自然の循環や地球物理的プロセスによって供給されている。
これらは化石燃料のように採掘量や埋蔵量に限りがなく、理論的には半永久的に利用可能である。例えば、太陽光であれば1時間で人類が1年に消費するエネルギーに匹敵する量が地球に降り注いでいるといわれ、風であれば大気の熱エネルギーによって常に生じている。
このように、再生可能エネルギーは有限な資源に依存せず、将来のエネルギー枯渇リスクを大幅に低減できる。ゆえに、持続的なエネルギー供給を実現する手段として極めて重要な役割を果たしている。
エネルギーの自給率が改善できる
また、再生可能エネルギーの導入は、エネルギー自給率の向上にも大きく寄与する。日本はエネルギー資源に乏しく、石油や石炭、天然ガスの約9割以上を輸入に依存している。そのため、国際情勢の変化や資源価格の高騰がエネルギー供給の不安定化を招くリスクを常に抱えている。
一方、再生可能エネルギーであれば、国内の自然条件を活用するため、太陽光や風力、水力、地熱などを用いて自国で電力を生み出すことが可能だ。これにより、輸入エネルギーへの依存度を低減し、エネルギーの自給率を高めることができる。
他にも、地域単位での発電・消費(地産地消型エネルギー)の促進にもつながり、エネルギー安全保障の強化や地方経済の活性化にも寄与する。
環境負荷が少ない
最後に、再生可能エネルギーのメリットは環境負荷が少ないことだ。再生可能エネルギーは発電や利用の過程で温室効果ガスや有害物質をほとんど排出しないため、環境への負荷が極めて小さいエネルギー源である。
太陽光発電や風力発電は、化石燃料の燃焼を伴わず、CO₂、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)などの排出がない。また、バイオマス発電は燃焼によりCO₂を排出するものの、成長過程で同量のCO₂を吸収しているため、カーボンニュートラルなエネルギーとされている。
さらに、水力発電や地熱発電も適切に管理すれば、自然環境への影響を最小限に抑えつつ長期的に利用が可能である。
再生可能エネルギーにおける課題やデメリット
再生可能エネルギーには多くの利点がある一方で、導入や運用には課題も存在する。ここでは、導入拡大の妨げとなる代表的な4つの課題について解説する。
発電のコストが高い
1つ目の課題は、発電コストが高い点である。再生可能エネルギーは、化石燃料を用いた発電に比べ、太陽光パネルや風力タービンなどの発電設備費用が高額であり、導入に多額の初期投資を必要とする。
また、発電量が天候や時間帯に左右されるため、安定供給を維持するには蓄電池システムなどの補完設備が欠かせない。これらの追加投資がコスト全体を押し上げる要因となっている。他にも、設備の設置場所や土地取得、メンテナンスにも費用が発生し、特に大規模発電では送電インフラ整備との併せた負担が大きい。
ただし、技術の進歩や市場拡大によって設備価格は年々低下しており、長期的には発電コストの削減が進むと期待されている。
安定供給が難しい
2つ目の課題は、安定供給が難しい点だ。再生可能エネルギーは、自然環境に依存して発電を行うため、電力の安定供給が難しいという課題を抱えている。太陽光発電は日照条件に大きく左右され、夜間や曇天・雨天時には発電量が大幅に低下する。
一方、風力発電も風が弱いと発電できず、逆に強風時には安全のためタービンを停止する必要がある。このように、気象条件や季節によって発電量が大きく変動するため、電力の需要と供給のバランスを常に保つのが難しい。
また、需給の変動に対応するためには、蓄電池による電力の貯蔵や他電源との組み合わせ運用などの調整が必要となる。こうした不安定性は電力系統全体に影響を及ぼす可能性があり、安定したエネルギー供給体制を構築するうえで大きな課題といえる。
送電網の整備が必要
3つ目の課題は、送電網の整備が必要になるという点である。再生可能エネルギーは、太陽光や風力など自然条件の良い地域に発電所が点在して設置されることが多く、電力需要地との距離が離れている場合が多い。
そのため、発電した電力を効率的に都市部や工業地帯へ送るには、広域的な送電網の整備が不可欠である。また、発電量の変動に応じて電力を適切に分配するためには、送電網の容量拡大に加え、電力の流れをリアルタイムで制御できる高度な系統制御技術が求められる。
特に、風力や太陽光の発電が盛んな地域では、既存の送電インフラでは電力を十分に受け入れられない「出力抑制」問題も発生しており、これを解消するための電力系統の増強や蓄電設備との連携が急務となっている。
エネルギー変換効率が低い
最後に、再生可能エネルギーは環境負荷が低い一方で、エネルギー変換効率が低いという課題を抱えている。例えば、化石燃料を利用する火力発電の効率が35〜43%程度であるのに対し、風力発電は約25%、太陽光発電は約10%、地熱発電は約8%、バイオマス発電に至っては約1%とされている。
これらの発電方式では、自然エネルギーを電力に変換する過程で損失が多く、得られる電力量が相対的に少ない。また、日射角度や風速、気温などの環境条件によっても効率が変動しやすいため、発電量を安定的に高めるのが難しいという現実がある。
特に太陽光発電では、パネルの設置角度や温度上昇によっても効率が低下する。こうした技術的制約を克服するには、高効率な素材開発や発電方式の改良が求められている。
再生可能エネルギーの普及促進に向けた制度
再生可能エネルギーの普及を促進するために導入された代表的な制度が「FIT(固定価格買取制度)」である。FITはFeed-In Tariffの略で、再生可能エネルギーによって発電された電力を、国が定めた固定価格で一定期間、電力会社が買い取ることを義務付けた仕組みだ。
この制度により、太陽光や風力などの発電事業者や個人が、価格変動リスクを負うことなく安定した収益を確保できるため、設備投資を促進する効果がある。買い取りにかかる費用は、電気を使用するすべての利用者が負担する「再エネ賦課金」として電気料金に上乗せされている。
さらに、2022年からは新たに「FIP(Feed-In Premium)制度」も導入された。これは、発電した電力を市場で販売する際、市場価格に応じて変動する売電収入に一定のプレミアム(補助金)を加算する仕組みである。FIPは市場競争原理を活かしつつ再エネ導入を進める制度として位置づけられており、FITと並び日本のエネルギー政策の中核を担っている。
再生可能エネルギーに関わる製品を開発する会社と取り組み事例
最後に、再生可能エネルギー分野で先進的な技術開発や導入事例を持つ企業を5つ紹介する。
富士電機株式会社
富士電機株式会社は、発電機や電力制御システムなどを手掛ける日本の総合電機メーカーであり、再生可能エネルギー分野でも長い実績を有している。1960年に日本で初めて実用的な地熱発電設備を納入して以来、世界各地に合計84台、総出力約3,500MWに及ぶ地熱蒸気タービンおよび発電機を供給してきた。
2000年以降の累計納入実績では、世界市場において約4割のシェアを占め、地熱発電分野でトップクラスの地位を確立している。また、太陽光発電向けには高効率なパワーコンディショナ(PCS)や高圧連系システムを開発し、再エネ電源の安定運用を支えている。
さらに、分散型電源を統合管理する仮想発電所(VPP)技術や、再エネ電力の需給調整を可能にする蓄電ソリューションの開発にも取り組んでおり、脱炭素社会の実現に向けた電力インフラの高度化を推進している。
ENEOSホールディングス株式会社
ENEOSホールディングス株式会社は、日本を代表する総合エネルギー企業であり、石油・天然ガスの供給に加え、再生可能エネルギーの分野にも積極的に事業を展開している。同社は「カーボンニュートラル社会の実現」を掲げ、太陽光、陸上風力、洋上風力、バイオマスといった多様な発電方式の開発と運営を推進している。
2024年6月時点では、建設中のものを含めた再生可能エネルギー設備容量が約127万kWに達しており、2025年度末には200万kWの達成を目標としている。また、国際的な技術連携にも力を入れており、2024年にはノルウェーの浮体式洋上風力プロジェクト「GoliatVind」に20%出資し、日本国内での浮体式洋上風力の技術開発や運用ノウハウの蓄積を図っている。
これらの取り組みを通じて、ENEOSは従来の化石燃料中心のエネルギー供給から、再生可能エネルギーを主力とする新たな事業構造への転換を進めている。
イーレックス株式会社
イーレックス株式会社は、東京都港区に本社を置く電力事業者であり、再生可能エネルギーを中心とした電力の発電・供給・小売を行っている。同社は「再生可能エネルギーをコアに電力新時代の先駆者になる」という方針のもと、2030年ビジョンを掲げている。
その中でも特にバイオマス発電を主力事業としており、現在は国内で糸魚川、佐伯、豊前など6か所に発電所を運営している。燃料には主にPKS(パームヤシ殻)や木質ペレットを使用し、安定的な再エネ電力の供給を実現している。
また、海外展開にも積極的で、ベトナムやカンボジアを中心に、現地でのバイオマス燃料の生産および発電プロジェクトを推進している。これにより、再生可能エネルギーの国際的な普及と地域経済の発展の両立を図っている。今後は、洋上風力や太陽光など他分野への事業拡大も視野に入れ、脱炭素社会の実現に向けたエネルギー供給体制の強化を進めている。
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.(ロンジ・グリーン・エナジー・テクノロジー)は、中国・西安市に本社を置く世界最大級の太陽光発電関連メーカーであり、単結晶シリコンウェーハやモジュールの製造で世界をリードしている。
同社は高効率な単結晶シリコン技術に特化し、2021年以降、世界最多となるモジュール出荷実績を維持している。技術開発にも積極的で、2025年4月にはペロブスカイト/シリコンタンデム太陽電池セルで変換効率34.85%、単接合結晶シリコンセルで27.81%という世界記録を同時に樹立した。
これらの成果は、同社の研究開発力と製造技術の高さを示すものである。また、2024年にはインドネシア国営エネルギー企業Pertamina NREと合弁し、西ジャワ州デルタマスにHPBC2.0技術を用いた年産1.6GW規模の太陽光モジュール工場を建設する計画を発表した。
LONGiはこのようなグローバル展開を通じ、再生可能エネルギーの普及拡大と脱炭素社会の実現に貢献する企業として世界的に注目されている。
Siemens Gamesa Renewable Energy
Siemens Gamesa Renewable Energy(シーメンス・ガメサ・リニューアブル・エナジー)は、スペインに本社を置く世界有数の風力発電機メーカーであり、ドイツのシーメンス・エナジー傘下として再生可能エネルギー分野を牽引している。
特に洋上風力発電における技術力は群を抜いており、1991年にはデンマークのヴィンデビー(Vindeby)に世界初の洋上風力発電所を設置したことで、オフショア風力の先駆者的存在として知られるようになった。
以降、欧州を中心に数多くの大型プロジェクトを手がけており、2024年にはイギリス東岸沖の「East Anglia TWO」プロジェクトにおいて、総容量960MWとなる64基の高性能風力タービン「SG 14-236 DD」を提供する契約を締結した。
この設備により、約100万世帯に相当する電力供給が可能となる見込みである。Siemens Gamesaは、風力発電の効率化・大型化技術を追求し、持続可能なエネルギー社会の実現に貢献している。
まとめ
再生可能エネルギーへの転換は、単なるエネルギー供給の多様化にとどまらず、産業構造や社会全体の持続可能な発展に直結する重要なテーマである。各国で導入が進む太陽光や風力などの再エネは、化石燃料依存からの脱却や温室効果ガス削減の実現に向けた中核的な役割を担っている。
しかし、導入コストや安定供給、送電網の整備など、克服すべき課題も依然として多いのが現状だ。それでも、長期的な視点に立てば、世界は確実に再エネ拡大の方向へ進んでおり、政策・技術・市場の連携によってエネルギー転換は加速している。
企業にとっても、脱炭素化やESG経営が重視されるなかで、再エネ分野は新たなビジネスチャンスの宝庫となっている。今後は、各国の制度や技術革新の動向を注視しながら、自社の事業領域に再エネをどう取り入れるかが問われていく時代である。