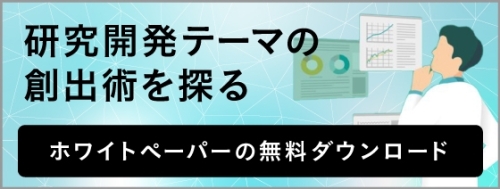脱炭素化とエネルギー安全保障が同時に求められる中、再生可能エネルギーには安定性と事業性の両立が強く求められている。地熱発電は、天候に左右されにくく長時間稼働できる点で、ベースロード電源としての価値を持つ発電方式として注目されている。
一方で、発電設備建設のハードル、環境への影響などについては、太陽光や風力と比較して十分に理解されているとは言い難いのが実情だ。本記事では、地熱発電の仕組みや導入のメリット・デメリット、課題などを網羅的に解説していく。
目次
地熱発電とは?
地熱発電とは、地球内部に蓄えられた熱エネルギーを利用して電気を生み出す発電方式を指す。地下深部にはマグマの熱によって高温に保たれた蒸気や熱水が存在しており、井戸を掘削してこれらを地上に取り出し、その圧力や熱でタービンを回転させて発電機を駆動する。
発電後に冷却された熱水は再び地下へ還元され、地中で再加熱されるため、資源を循環させながら長期的に利用できる点が特徴だ。天候の影響を受けにくく、安定的に発電できる再生可能エネルギーとして位置づけられている。
地熱発電の仕組みと種類
地熱発電には大きく「蒸気発電方式」と「バイナリー方式」の2つの方式がある。
蒸気発電方式(フラッシュ発電)
蒸気発電方式は、地下の地熱貯留層から取り出した蒸気、あるいは熱水から分離した蒸気のエネルギーでタービンを回す地熱発電の代表的な方式である。資源の温度や状態に応じて「ドライスチーム方式」、「シングルフラッシュ方式」、「ダブルフラッシュ方式」の3つに分類されている。
ドライスチーム方式は、高温高圧の蒸気のみが得られる場合に採用される方式のことを指し、地中から取り出した蒸気を直接タービンへ送るため構造が簡潔で発電効率が高い。ただし、このような資源は希少で、日本では松川地熱発電所が代表例である。
また、現在主流なのがシングルフラッシュ方式で、蒸気と熱水が混在した状態で噴出する資源を対象として採用される。この方式は気水分離器で蒸気のみを取り出し、タービンを駆動する方式だ。
そして、さらに発電量を高めるため、分離後の熱水を再度減圧して蒸気を発生させるのがダブルフラッシュ方式であり、高圧と低圧の蒸気を併用することで、シングルフラッシュ方式よりも発電効率が15〜20%程度向上するとされている。
| 方式 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| ドライスチーム方式 | 地下から出る蒸気をそのまま使って発電 | 仕組みが簡単だが、適用できる場所が少ない |
| シングルフラッシュ方式 | 高温の熱水を減圧して蒸気に変えて発電 | 適用範囲が広く、最も一般的な方式 |
| ダブルフラッシュ方式 | 熱水を2回減圧し、蒸気をより多く取り出して発電 | 発電量を高められるが、設備がやや複雑 |
バイナリー発電方式
バイナリー発電方式とは、従来の方式では利用できなかった中低温の地熱資源を有効活用するために開発された地熱発電方式である。この方式では、水よりも沸点が低いペンタンやアンモニアなどの作動流体を用い、地下から取り出した熱水や蒸気の熱を熱交換器を介して伝える。
作動流体は比較的低い温度でも容易に蒸発するため、その蒸気でタービンを回し発電機を駆動できる。タービンを通過した蒸気は冷却器で再び液体に戻され、循環利用される。一方、熱を放出した地熱流体は大気に触れることなく地下へ還元されるため、環境負荷が小さい点も特徴だ。
従来のフラッシュ方式では200℃以上の高温の蒸気が必要だったが、バイナリー方式であれば80〜150℃程度の熱源でも発電可能であり、温泉水や小規模地熱地帯など、これまで活用が難しかった資源を電力に転換できる方式として注目されている。
次世代型地熱発電とは何か?
次世代型地熱発電とは、従来の地熱発電が抱えてきた立地制約や資源条件の厳しさを克服し、地熱エネルギーの利用範囲を拡大するための革新的技術の総称を指す。従来の方式では、高温の熱源に加えて地下水や割れ目構造が自然に揃った貯留層が不可欠であり、開発可能な地域は火山帯などに限られていた。
これに対し、次世代型地熱発電は人工的に熱の取り出し経路を構築したり、より深部の高温岩体を活用したりすることで、資源の有無に左右されにくい発電を目指す。これにより、地熱の潜在的なエネルギー量を大幅に引き上げ、安定的な再生可能エネルギー源としての実用性向上が期待されている。
EGS(高温岩体地熱発電)
EGSはEnhanced Geothermal Systemsの略称で、地下に十分な熱は存在するものの、天然の割れ目や地下水が乏しく、従来は利用できなかった高温岩体を活用する次世代型地熱発電技術である。
具体的には、地下数千メートルまで掘削した注入井から高圧の水を送り込み、岩盤に微細な亀裂を人工的に形成することで、熱水が循環できる人工貯留層を構築する。そこに冷水を循環させると、岩体の熱を吸収した高温の熱水や蒸気が生産井から回収され、地上でタービンを回して発電が行われる。
自然条件に左右されにくく、資源量が極めて大きい点が特徴だが、誘発地震の管理や掘削コストの低減といった技術課題も残されている。
クローズドループ方式
クローズドループ方式とは、地下に設置した密閉配管の内部で作動流体を循環させ、岩盤から熱のみを回収する次世代型地熱発電技術である。AGS(Advanced Geothermal Systems)とも呼ばれ、地下の高温岩盤に沿って敷設されたパイプ内を流体が通過する際、熱伝導によって加熱されて地上へ戻る。
その熱を利用して発電を行い、冷却された流体は再び地下へ送られるため、完全に閉じた循環系が維持される。地下水が乏しい乾燥した岩盤であっても、熱さえあれば発電が可能になるため、従来の地熱発電が困難だった地域でも導入が期待できる。
また、地下水をくみ上げないため、地域の温泉資源への影響や、地下水に含まれる有害物質の流出リスクが極めて低いとされる。
超臨界地熱発電
超臨界地熱発電とは、地下深部に存在する極めて高温高圧な熱エネルギーを利用する、地熱発電の最終形態ともいわれる先進的な技術である。従来の発電方式では到達できなかった地下4~5km、あるいはそれ以上の深部では、水が臨界点を超えた「超臨界水」の状態となり、液体と気体の性質を併せ持つ。
この超臨界水はエネルギー密度が非常に高く、同じ井戸でも従来方式を大きく上回る発電出力が期待できるとされる。一方で、実用化には大きな課題が残る。500℃近い高温環境下での深部掘削技術や、超臨界水に含まれる酸性成分や腐食性成分に耐える特殊な井戸管、さらには地上設備の開発が不可欠だ。
地熱発電の発電割合について
地熱発電の発電割合は、再生可能エネルギーの中でも依然として低水準にとどまっている。「Statistical Review of World Energy 2025年版」によれば、世界の電源構成に占める地熱発電の比率はごくわずかで、バイオマスと合算しても3%未満である。
多くの国で太陽光や風力が急拡大する一方、地熱は立地条件や開発難度の制約から導入が限定されているのが現状である。日本においても状況は同様で、資源エネルギー庁が公表した「令和5年度(2023年度)におけるエネルギー需給実績」では、2023年度の地熱発電比率は0.3%にとどまっている。潜在的な資源量は大きいものの、発電割合はまだ極めて小さい。
地熱発電の市場規模
地熱発電市場は、緩やかではあるが着実な成長が見込まれている。Knowledge Sourcing Intelligenceの調査レポート「Geothermal Power Market - Forecasts from 2025 to 2030」によれば、世界の地熱発電市場規模は2025年に約77億6,500万米ドル、2030年には約93億3,100万米ドルへ拡大すると予測されている。
資源量の観点では、資源エネルギー庁がまとめた資料によると、地熱資源量はアメリカが約3,000万kWで世界最大、次いでインドネシアが約2,800万kW、日本は約2,300万kWで世界第3位とされる。しかし実際の開発状況を見ると、日本はインドネシアやニュージーランド、アイスランド、トルコ、ケニアなどに後れを取っている。
2020年のWorld Geothermal Congressの調査でも、地熱発電設備容量はアメリカ、インドネシア、フィリピンが上位を占めるのに対し、日本は10位となっており潤沢な地熱資源を活用しきれていないことになる。
なお、設備容量と資源量ともにトップのアメリカは、水圧破砕技術を応用した次世代地熱開発が進み、ユタ州南西部で次世代地熱プロジェクト「ケープ・ステーション」などが進行中である。また、トランプ政権も次世代地熱発電をアメリカのエネルギー源の一つとして開発推進を行う方針を掲げており、機運が高まっている。
日本では、2024年11月に資源エネルギー庁・環境省によって「地熱開発加速化パッケージ」が公表され、次世代型地熱発電を含む地熱エネルギーは新たな促進フェーズとされた。また、2025年2月に閣議決定された「第7次エネルギー基本計画」では、2030年代早期に次世代地熱発電の実用化を目指して研究開発・実証を進めることが明記されている。
地熱発電のメリット・特徴
地熱発電は温室効果ガスをほとんど排出しないだけでなく、電力を安定供給できる、地熱資源が豊富など、さまざまなメリットが存在する。
温室効果ガス(CO₂)をほとんど排出しない
地熱発電の大きなメリットの一つは、温室効果ガスであるCO₂をほとんど排出しない点にある。石炭や天然ガスを燃焼させる火力発電では、燃料を燃やす過程で大量のCO₂が発生する。一方、地熱発電は地下深部に存在する熱水や蒸気の熱エネルギーを直接利用してタービンを回す仕組みであり、燃焼プロセス自体が存在しない。
そのため、発電時に新たなCO₂をほぼ排出しない。地下から取り出される蒸気や熱水には、二酸化炭素などの非凝縮性ガスが微量に含まれる場合があるが、その排出量は石炭火力発電の約20分の1以下とされ、環境負荷は極めて小さい。
燃料が枯渇する心配がない(再生可能エネルギー)
2つ目の特徴として、地熱発電は燃料が枯渇する心配がほとんどない再生可能エネルギーである点があげられる。地殻の深部には地球内部の活動によって生じた膨大な熱エネルギーが存在し、人類の時間尺度では尽きることがないと考えられている。
地熱発電では、この熱を利用するために地下から蒸気や熱水を取り出すが、発電に用いた後は還元井を通じて再び地下へ戻す仕組みが取られる。これにより、地熱貯留層の圧力や水量が維持され、熱源を長期にわたって安定的に利用できる。化石燃料のように採掘によって減少する資源とは異なり、持続的に利用可能な点が大きな強みである。
電力を安定供給できる
また、電力を安定的に供給できる点も地熱発電のメリットである。地熱という熱源は地下深部に存在するため、天候や季節、昼夜といった外的条件の影響をほとんど受けない。
太陽光発電や風力発電のように自然条件によって発電量が大きく変動する再生可能エネルギーとは異なり、地熱発電は地熱貯留層の温度や圧力を適切に管理することで、年間を通じてほぼ一定の出力を維持できる。
計画的な運転が可能で需給バランスを崩しにくいことから、電力系統の安定化にも寄与し、ベースロード電源としての役割が期待される。
純国産エネルギーとして地熱資源が豊富
最後に、地熱発電は、純国産エネルギーとして活用できる地熱資源が日本に豊富に存在する点も特徴としてあげられる。日本は石油や天然ガス、ウランといった主要なエネルギー資源の多くを海外からの輸入に依存しており、エネルギー自給率の低さが長年の課題となってきた。
一方で、火山帯に位置する日本は地熱資源のポテンシャルが高く、その埋蔵量は世界でも3位に位置するとされている。こうした背景から未開発の地熱資源を国内で活用することは、海外情勢に左右されにくい電源を確保することにつながり、エネルギー安全保障の観点からも重要性が高い。
地熱発電のデメリット・課題
メリットが多い地熱発電だが、発電所建設のハードルが高い、地震誘発のリスク、建設場所が制約されるといった課題も存在する。
開発期間が長く、初期コストが高くなる
1つ目の課題として、地熱発電は開発期間が長く初期コストが高くなりやすい点がある。最大の要因は、地熱資源の探査と確認に多大な費用とリスクを伴うことだ。地下に存在する熱水や蒸気の量、温度、持続性は事前調査だけでは正確に把握できず、最終的には地下数千メートルに及ぶ試掘井を掘削して確認する必要がある。
この調査段階だけで数年を要し、費用も数十億円規模に達することがある。しかも、掘削の結果、発電に十分な資源が得られない場合には投資が回収できない。加えて、発電所建設では生産井や還元井の掘削費が大きな割合を占め、さらに地熱流体に含まれる腐食性成分に耐える特殊な設備や配管が必要となるため、設備コストも高額になりやすい。
他の発電方法と比べて発電効率が低い
次に、地熱発電は、他の発電方法と比べて発電効率が低い点が課題とされる。主な理由は、利用できる熱源の温度が相対的に低いことにある。地熱発電で用いられる蒸気や熱水の温度は一般に150℃から350℃程度であり、火力発電で燃焼によって得られる約600℃の高温と比べると大きな差がある。
発電は熱エネルギーを電気エネルギーへ変換する過程で温度差が重要となるため、熱源温度が低いほど変換効率は下がる。この結果、地熱発電の効率はおおむね10〜20%程度にとどまる。風力発電がおよそ30〜40%、水力発電が80%前後とされるのと比較すると、エネルギー変換効率の面では見劣りする。
建設場所が限られる
そして、建設できる場所が限られる点も大きな課題だ。発電に適した地点は、地下に十分な高温の熱源が存在するだけでなく、熱水や蒸気を循環させられる地質構造、貯留層の透水性や密閉性など、複数の条件が同時に満たされる必要がある。
そのため、火山帯周辺など特定の地域に立地が偏りやすい。さらに、地質条件を満たしていても、土地所有者との合意や、国立公園指定、温泉資源への影響を懸念する自治体や事業者との協議、地域住民の理解を得るといった社会的・制度的な制約が存在する。これらの要因が重なり、地熱発電は導入可能な場所が限定されやすい発電方式となっている。
安全性の懸念と環境への影響・リスク
最後に、安全性や環境への影響に関する懸念も存在する。地下深部の資源を利用する特性上、蒸気や熱水の採取、使用後の還元によって地層の圧力バランスが変化し、微小地震を誘発する可能性が指摘されている。
また、地熱流体にはヒ素やホウ素、水銀、硫化水素などの自然由来の有害物質や腐食性成分が含まれる場合がある。これらを適切に管理せずに地表へ放出すると、河川や地下水の汚染を通じて生態系や生活用水へ悪影響を及ぼしかねない。
そのため、現在は使用済みの熱水を還元井で地下へ戻す運用が原則とされているが、設備や配管の損傷による漏出リスクは完全には排除できない。特にヒ素など土壌に吸着しやすい物質による汚染は、復旧に多大な時間と費用を要する。
なぜ日本では地熱発電が普及しないのか?
日本は世界有数の地熱資源量を有し、理論上は国の電力需要の大半を地熱でまかなえる可能性があるにもかかわらず、実際の地熱発電の普及は極めて限定的である。その背景には、地質条件だけでなく社会的・制度的な要因が複雑に絡み合っている。
まず大前提として、地熱資源が集中する地域の多くが国立公園や特別保護地区に指定されており、自然景観や生態系を守る観点から開発規制が厳しい。発電所の建設には長期にわたる許認可手続きが必要となり、事業化までに多大な時間と労力を要する。
加えて、日本では温泉地が地域経済を支える重要な観光資源であり、地熱開発によって地下水系が変化し、湧出量や温度に影響が及ぶことへの懸念が根強い。このため、温泉事業者や住民から反対を受けるケースも少なくない。
さらに、探査から運転開始までに長期間を要する事業特性が、投資判断を慎重にさせる要因にもなっている。政府は規制緩和や国立公園での開発条件の見直し、経済的インセンティブの強化などを進めてはいるものの、普及の加速にはなお時間を要するという見方が強い。
地熱発電を手がける企業事例・メーカー
最後に、地熱発電の開発や提供を行っている企業事例をいくつか紹介する。
三菱重工業株式会社
三菱重工業は、エネルギー・インフラ分野を中核事業とする日本の総合重工メーカーであり、地熱発電分野においても長年の実績を有する。地熱発電プラントの設計、機器製造、建設、運用支援までを一貫して手がけ、国内外の多数の地熱発電事業に関与してきた。
特に、二相流体輸送とダブルフラッシュ方式を組み合わせたプラント設計を世界で初めて実用化した点は、同社の技術的な強みである。地熱発電用蒸気タービンの分野でも世界トップクラスの供給実績を持ち、累計で100台以上、総出力3,000MW超の納入実績がある。小規模から大規模まで幅広い出力ニーズに対応できる点も特徴だ。
富士電機株式会社
富士電機株式会社は、エネルギー・産業インフラ分野を主力とする日本の電機メーカーであり、地熱発電設備において世界トップクラスの実績を持つ。2000年以降の地熱蒸気タービン受注では世界シェア約40%を占め、首位を維持している。
同社の地熱発電の歴史は1960年にさかのぼり、日本初の商用地熱発電所向け設備を納入して以降、60年以上にわたり技術を蓄積してきた。地熱蒸気に含まれる硫化水素などの腐食性成分に耐える高信頼性タービン設計を強みとし、30年以上の長期安定運転を実現する事例も多い。その耐久性と信頼性は国際的にも高く評価されている。
株式会社東芝
株式会社東芝は、エネルギー・社会インフラ分野を中核とする日本の総合電機メーカーであり、地熱発電分野でも長い実績を持つ。1966年に日本初の商用地熱発電所である岩手県の松川地熱発電所へ20MWの蒸気タービンと発電機を納入したことを起点に、半世紀以上にわたり技術開発を継続してきた。
現在では世界各地に60ユニット以上の地熱発電設備を納入し、累計出力は約4,000MWに達している。これは世界の地熱発電設備容量の約4分の1に相当する規模である。
また、東芝は大規模な発電所だけでなく、中小規模の地熱資源を有効活用するための小型地熱発電設備「Geoportable™(ジオポータブル)」を展開。これは1MWから20MW級の出力を想定したコンパクトな発電システムで、主要設備を共通の架台にパッケージ化することで、従来よりも大幅に据付期間を短縮できるのが大きなメリットだ。
実際に、日本国内の温泉地やインフラ整備が急務なエチオピア、フィリピン、インドネシアなどの開発途上国での導入が進んでいる。
地熱発電の将来性と今後
地熱発電は、天候に左右されにくく長期にわたって安定した発電量を確保できる一方で、立地条件の制約や初期投資の大きさ、環境面・安全面への配慮といった課題も内包している。
しかし、EGSやクローズドループ方式など次世代地熱発電技術が進展することで、適用可能地域の拡大や市場規模のさらなる向上が期待されている。地熱発電は単なるエネルギー分野にとどまらず、他業種へ裾野が広がる可能性を秘めた市場といえるだろう。