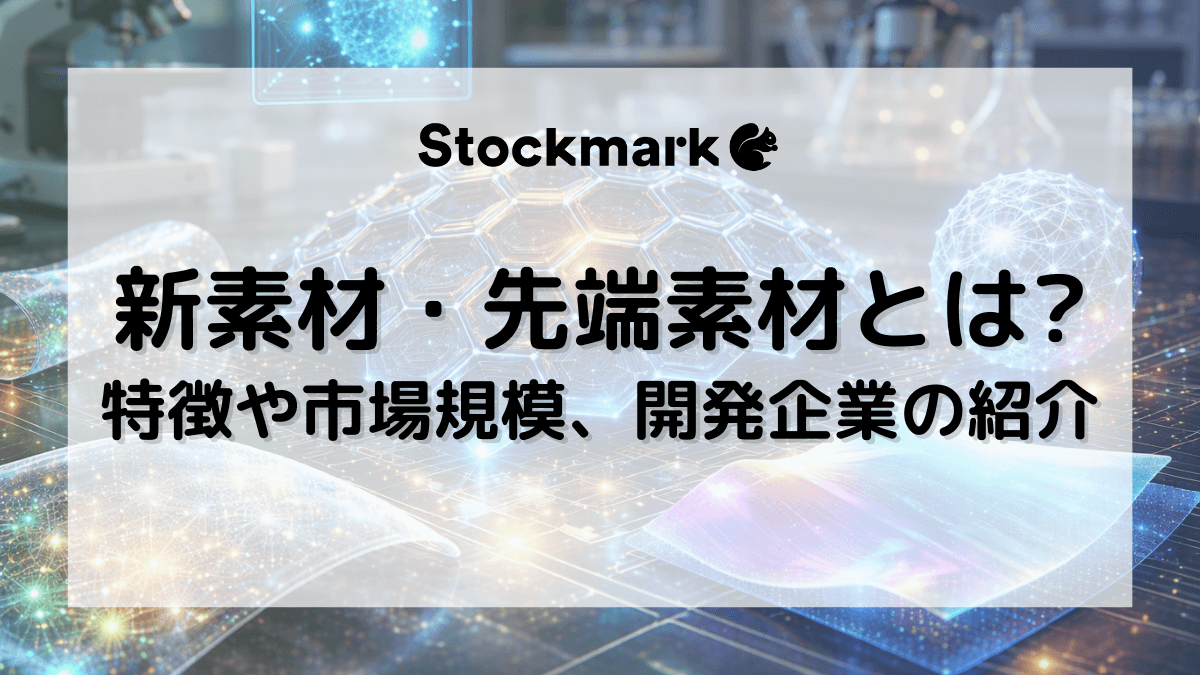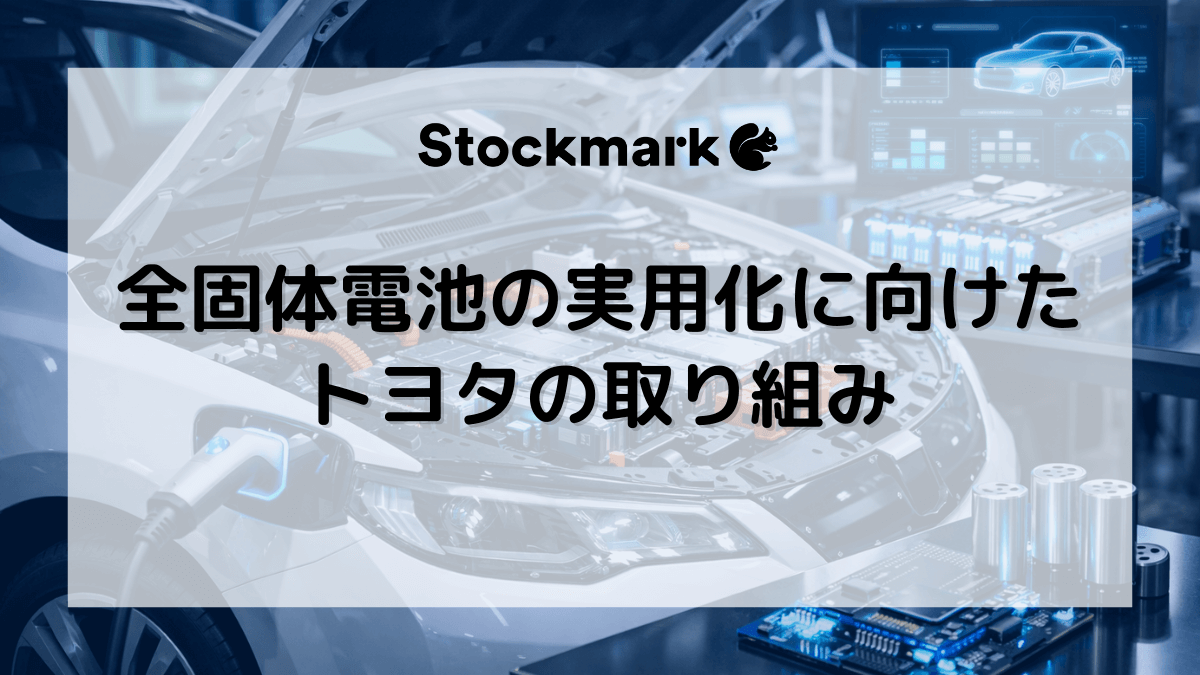製造業において、製品を正しく設計し、効率よく調達・生産、さらには市場投入後の保守まで確実に実行するためには、部品情報を一元的に管理する仕組みが欠かせない。その中心となるのがBOMである。
BOMとは、製品を構成するすべての部品や材料、数量、階層構造を整理した管理情報であり、部品表(Bill of Materials)とも呼ばれる。BOMは設計部門だけでなく購買、生産管理、物流、サービスなど企業全体で共有されることで、業務の正確性と連携を支える役割を担う。
適切なBOM管理が実現できれば、生産性の向上、コスト削減、品質安定化、納期遵守といった競争力の強化にもつながる。本記事では、BOMとは何かという基本から、その種類、導入によるメリット、運用で直面しやすい課題までを分かりやすく解説する。
目次
BOM(Bill of Materials)とは?
BOMとは、「Bill of Materials」の略称で、製品を構成するすべての部品、原材料、部材、ユニットを体系的に整理した情報リストであり、日本語では部品表または部品構成表と呼ばれる。製造業においてBOMは基幹情報として扱われ、設計段階での部品選定から製造指示、調達計画、在庫管理、保守・修理、さらには廃棄時の管理に至るまで、製品ライフサイクルの全工程で重要な役割を果たす。
BOMには、部品名、品番、数量、使用位置、仕様、階層構造といった詳細が記載され、どのように製品が組み上がっているかを明確に把握できる。これにより、生産性の向上、コスト管理の精度向上、品質トレーサビリティの確保が可能となる。
複雑化する製品開発において、BOMの適切な管理は部門間連携を強化し、手戻りや調達遅延の防止につながる。すなわち、BOMは製造業の情報基盤として不可欠な存在といえる。
BOMが求められる背景や導入の目的
BOMが求められる背景には、製造業における生産体制の変化と製品の複雑化がある。大量生産が普及した20世紀初頭、フォード社がT型フォードの組立ラインを確立した際、膨大な部品を正確に管理・供給する必要が生じ、製品構成を一覧化した情報が不可欠となった。これが現在のBOMの原型といわれている。
その後、製品が多品種化し、設計と製造プロセスが分業化・グローバル化するにつれ、部品情報の一貫した管理が業務効率や品質維持の鍵となった。1970~80年代にはコンピュータ技術の発展により、部品情報のデジタル管理が進展し、MRPやERPといった生産管理システムの中核データとしてBOMが位置づけられた。
今日では、設計変更の迅速な反映、在庫最適化、調達リスク低減、トレーサビリティの確保など、競争力強化に直結する目的から、BOMは製造業の情報基盤として必須となっている。
BOMの種類
BOMの種類は、構成情報の表し方で分類する管理方法別(サマリー型とストラクチャー型)と、業務プロセスに応じて使い分ける用途別(E-BOM、M-BOM、S-BOM、P-BOM、Sales BOM)の2つに大別される。
サマリー型(部品表)
サマリー型BOMとは、製品に使用される全ての部品を一つの一覧表としてまとめた形式のBOMである。個々の部品について、品番、名称、必要数量などが整理されており、製品全体でどの部品がいくつ必要となるかを直感的に把握できる特徴を持つ。
一方で、組立手順や中間部品の階層構造までは表現されないため、製品構成の詳細な分析には向いていない。しかし、原価計算や必要部品量の算出、発注計画の立案といった用途では非常に有効であり、生産計画や調達業務を支える基本情報として広く利用されている。製品全体の部品需要を俯瞰できることから、在庫管理や材料手配の効率化にも寄与するBOM形式である。
ストラクチャー型(部品構成表)
ストラクチャー型BOMとは、製品を構成する部品やユニットがどのような階層構造で結びついているかを示した形式のBOMである。最上位の完成品から順に、中間アセンブリ、さらにその下の個別部品へと階層が展開され、親子関係が明確に整理されているため、製品がどのように組み立てられ、逆にどのように分解できるのかを視覚的に理解しやすい。
これにより、設計変更による影響範囲の特定や、部品共通化の検討、保守時の交換対象の把握など、製品ライフサイクル全体で精度の高い管理が可能となる。また、部品の使用箇所が明確になることで、在庫管理や生産計画の最適化にも役立つ。製品構成を正確に反映し、設計から製造、保守までの連携を強化する重要なBOM形式である。
E-BOM (Engineering BOM / 設計部品表)
E-BOM(Engineering BOM / 設計部品表)とは、製品設計段階で定義されるBOMであり、製品をどのような部品や材料で構成するかを設計情報に基づいて記載したものである。設計図面や3D CADデータと連携し、部品の形状、仕様、材質、品番、数量などの情報が含まれる。
製品の意図や性能要件を反映した構成であるため、設計者が想定する理想的な製品像が表現されている。一方で、製造現場での制約や購買状況は必ずしも反映されていないため、後工程で製造向けに調整が必要となる。そのため、E-BOMはM-BOMなど他のBOMと連携して活用されることが重要であり、設計変更が確実に生産へ反映されるための基盤として機能する。
M-BOM (Manufacturing BOM / 製造部品表)
M-BOM(Manufacturing BOM / 製造部品表)とは、製造工程に最適化されたBOMであり、実際の生産現場で使用される部品構成情報を示すものである。設計段階で定義されたE-BOMを基に、加工や組立手順、生産設備の仕様、調達の都合などを反映して構築される。
例えば、一体部品として設計された部材を製造現場の工程上、複数の部品に分割して管理する場合や、逆に調達効率の観点から部品を統合する場合がある。さらに、中間品や治工具、代替部品といった生産特有の情報も記載されるため、現場の実情に即したデータとして機能する。
M-BOMは、工程設計、生産計画、在庫管理などと密接に連携し、適切な部品供給と安定した製造品質を支える役割を担っている。
S-BOM (Service BOM / サービス・保守部品表)
S-BOM(Service BOM / サービス・保守部品表)とは、製品の出荷後に行われる保守・修理・点検などのアフターサービスにおいて使用される部品情報をまとめたBOMである。製品のライフサイクル後半に焦点を当て、交換可能部品や消耗部品、メンテナンス手順などが整理されているのが特徴だ。
実際の設計構造や製造手順をそのまま反映するのではなく、現場の保守担当者が効率的に作業できるよう、構成を簡略化している場合が多い。例えば、修理単位ごとに部品をまとめたり、特定の交換部品を優先的にリスト化したりする。S-BOMを整備することで、アフターサービスの迅速化や在庫の適正化、製品信頼性の維持が可能となる。
P-BOM (Purchasing BOM / 購買部品表)
P-BOM(Purchasing BOM / 購買部品表)とは、製品を製造するために外部から調達する必要がある部品や原材料に特化して管理するBOMである。調達部門が取り扱う情報に最適化されており、部品ごとのサプライヤー情報、リードタイム、最小発注数量、価格条件などが詳細に記載される。
これにより、最適な購買計画の立案やコスト削減、納期遵守の実現が可能になる。P-BOMは設計や製造向けの情報とは異なり、供給リスク管理にも活用され、代替品の評価や調達先分散などの意思決定を支援する役割も担う。
Sales BOM (販売部品表)
Sales BOM(販売部品表)とは、販売時点で取り扱われる製品構成を管理するBOMであり、営業や販売部門が使用する情報に特化している。製品が顧客へどのような形で提供されるかを明確にするため、構成品目やオプション設定、セット販売される部材の組み合わせが記載される。
例えば、家電製品の本体に加えて付属ケーブルや保証サービスが一括で販売される場合、その構成内容を管理するのがSales BOMの役割である。販売形態を踏まえて製品構成を定義することで、顧客の注文処理や出荷管理を効率化でき、販売後のサポートにおいても適切な情報提供が可能となる。
BOMシステムを導入するメリット
速やかにBOMの連携や統合を行うには、BOMシステムを導入するのがベターだ。ここでは、BOMシステムを導入することで得られる利点を4つ紹介する。
情報の正確性と一貫性の向上
BOMシステムを導入する最大のメリットの一つが、情報の正確性と一貫性の向上である。製品を構成する部品情報をシステム上で一元管理することで、設計、調達、製造など各部門が同じデータを参照でき、部署間で情報が食い違うリスクを排除できる。
また、設計変更や部品仕様の更新が行われた際には、リアルタイムでシステムに反映されるため、常に最新情報に基づいて業務を進められる。紙の帳票やExcel管理では起こりがちな入力ミスや転記ミスも大幅に削減され、誤った部品発注や組立ミスといったトラブル防止にもつながる。
在庫の最適化
2つ目のメリットは、在庫の最適化だ。BOMシステムを導入することで、在庫を最適な水準にコントロールできるようになる。正確な部品情報と使用数量が明確になるため、生産計画に応じた部材の所要量を正確に算出でき、過剰在庫による保管コストの増大や、欠品による生産停滞を防止できる。
また、代替部品や仕様変更情報もBOMに紐づけて管理できるため、突発的な部材不足にも柔軟に対応可能である。さらに、調達リードタイムや使用頻度を考慮した適正在庫の維持が可能となり、キャッシュフロー改善にも寄与する。これらにより、在庫管理の無駄を大幅に削減し、効率的なサプライチェーン運営を支える基盤となる。
生産性向上と品質安定化
BOMシステムを導入する3つ目のメリットは、生産性の向上と品質の安定化だ。BOMシステムを導入することで、生産現場における作業指示が常に最新かつ正確な情報に基づいて行われるようになり、組立ミスや部品の付け間違いが大幅に減少する。
その結果、手戻り作業やライン停止といった非効率が抑えられ、生産性の向上につながる。さらに、仕様変更が発生した場合でも即時に反映されるため、旧データに基づく作業が行われるリスクも低減できる。また、品質トラブルが発生した際にはBOM情報を参照することで、どの部品がどの製品に使用されているかを迅速に特定でき、原因追及や対策実施がスムーズになる。
製品開発プロセスの加速
最後のメリットには、製品開発プロセスの加速があげられる。BOMシステムを導入することで、過去の製品データや標準部品情報を迅速に検索・再利用できるようになり、新規開発時の部品選定や設計作業を効率化できる。これにより、設計者はゼロから仕様を検討する必要が減り、より付加価値の高い業務に集中できる。
また、BOMは部品間の依存関係を体系的に管理しているため、設計変更が発生した際には影響範囲を即座に把握し、関連部署への共有も迅速に行える。これにより、手戻りや再設計による遅延を抑え、開発リードタイム全体を短縮できる。さらに、部品仕様の標準化や再利用が進むことで、調達や製造の段階でも効率が高まり、製品開発プロセス全体のスピード向上に寄与するのである。
BOM管理でよくある課題とは
BOM管理には、多くの製造企業が直面する課題が存在する。その中でも、部門間連携の不足やデジタル化の遅れ、グローバル調達への対応など重要なポイントを3つ紹介する。
BOM間や部門間における連携不足
1つ目の課題は、BOM間や部門間の連携不足である。設計部門が管理するE-BOMと、製造部門が使用するM-BOMが適切に連動していない場合、設計段階の変更が現場に反映されず、誤った部品で生産が進むリスクが生じる。また、部門ごとに独自に部品情報を管理していると、品番の不整合や仕様の重複が発生し、再確認や修正作業のコストが増大する。
結果として、工程の遅延、部品調達トラブル、品質不良の発生につながり、企業全体の生産性を大きく損なう要因となる。そのため、統一されたデータ基盤上で部門間の情報を正確かつリアルタイムに共有できる体制の構築が重要である。
BOMのデジタル化
2つ目の課題は、BOMのデジタル化だ。BOMのデジタル化が十分に進んでいない企業では、Excelや紙資料といった手動管理に依存しているため、データ量の増加に伴い管理が煩雑化しやすく、最新情報への更新漏れや検索性の低下が深刻化する。
この結果、古いBOMを基に部品発注が行われ、過剰在庫の発生や納期遅延、場合によっては生産ライン停止といった重大なトラブルにつながるリスクが高まる。また、BOMシステムを導入していても、業務フローとの不一致や操作定着不足により期待した効果が得られないケースも少なくない。他にも、ERPやCADなど他システムとの連携が不完全な場合には、データ不整合が生じ、正確な情報管理が難しくなる。
グローバルサプライチェーンへの対応
3つ目の課題は、グローバルサプライチェーンへの対応である。具体的には、グローバルサプライチェーンに対応する場合に国や拠点ごとに部品番号や規格、RoHS指令などの法規制が異なる点が挙げられる。同じ製品であっても、生産国によって利用可能な部材や調達先が変わるため、地域ごとに異なるBOMが作成されやすい。
これを適切に統合・管理できていないと、部品情報の齟齬が発生し、生産遅延やコスト増につながるリスクが高まる。また、複数の海外拠点で開発を分担する場合、それぞれが独立してBOMを更新してしまうと、各拠点間で情報の差異が生まれ、品質不一致や手戻りを招きやすくなる。
部品管理システムを提供する企業5選
最後に、BOM管理を支える部品管理システムを提供する企業を5つ紹介する。
株式会社日立パワーソリューションズ「PowerBOM」
株式会社日立パワーソリューションズは、製造業向けのITソリューションや設備管理サービスを提供する企業であり、その主要製品の一つとしてBOM管理システム「PowerBOM」を展開している。PowerBOMは、設計部門が扱うE-BOMと、生産準備段階で必要となるP-BOMを統合管理できる仕組みを備え、部門間でのデータ整合性を確保するシステムである。
設計変更が発生した場合でも、最新情報がリアルタイムで反映されるため、誤伝達による手戻りを防ぎ、工程全体の効率化を図ることができる。また、CADやPDM、生産管理システムとの連携に対応し、既存環境との整合性を保ちつつ導入が可能である。さらに製造番号単位でのBOM管理にも対応しており、個別受注生産品にも適用できる柔軟性を有する。
三菱電機デジタルイノベーション株式会社「ACSEED」
三菱電機デジタルイノベーション株式会社は、製造業向けの生産管理・IT支援ソリューションを提供する企業であり、その主力システムの一つとして「ACSEED」を展開している。ACSEEDは、中堅・中小自動車部品製造業向けの生産管理システムで、部品表(BOM)管理を中核に、生産計画、構成および工程展開、調達、かんばん方式管理までを一元的にサポートする統合型システムである。
自動車部品メーカーの業務ノウハウを基盤として設計されており、出荷実績との照合機能や誤品防止機能など、製造現場の運用に密着した仕組みが備わっている点が特徴である。UIは視覚的で操作性が高く、Excelへの出力機能や多言語切替にも対応し、複数拠点を持つ企業でも運用しやすい設計となっている。また、BOMのバージョン比較機能によって設計変更点を明確に把握でき、設計から生産への情報連携を円滑化することができる。
富士通株式会社「COLMINA 技術情報管理 部品表」
富士通株式会社は、国内外で幅広いITソリューションを提供する総合ICT企業であり、製造業向けには「COLMINA 技術情報管理 部品表」を展開している。本システムは、設計段階で扱う3D CADデータやアセンブリ構成情報を基盤として、E-BOM(設計部品表)からM-BOM(製造部品表)までを統合管理できる点に特徴がある。
部品の階層構造や数量、使用位置を可視化し、設計変更が発生した際にも各部門へ即時反映されるよう連携性が確保されている。また、共通データ基盤により、設計から製造準備、製造実行へと一貫した情報連携を可能とするデジタルスレッドを実現している。
株式会社大塚商会「生産革新 Bom-jin」
株式会社大塚商会は、ITソリューションやシステムインテグレーションを幅広く提供する企業であり、製造業向けにはBOM管理システム「生産革新 Bom-jin」を展開している。本システムは、設計から生産部門まで製品構成情報を一元管理し、部門横断で活用できることを特徴とする。品目台帳を基盤とし、品目コード自動発番や辞書機能による名称統一、類似品管理などを通じて標準化と設計資産の流用を促進する。
また、構想段階からBOM編集が可能なフリーリスト編集機能や、旧品目の識別・更新を支援する最新版管理、構成差異表示機能を備え、設計変更への柔軟な対応を可能にしている。さらに、生産管理システムやCADとの連携により、設計情報が生産準備、製造プロセスへ齟齬なく反映される仕組みを実現し、納期短縮やコスト削減、品質維持に寄与する。
トモラク株式会社「Tomoraku PLM」
トモラク株式会社は、製造業の設計業務を支援するクラウド型PLM(製品ライフサイクル管理)システム「Tomoraku PLM」を提供している。同システムの中核機能としてBOM(部品表)管理を備え、製品を構成する部品やモジュールの階層構造を視覚的に把握できる仕組みを採用している。
これにより、使用部品から関連する製品構成を逆引きすることも可能で、設計変更時の影響範囲を即座に把握できる。また、部品や図面、仕様書などの技術文書を一元管理し、改訂履歴を適切に管理するリビジョン管理機能を搭載しているため、誤った旧データの混在を防止できる。さらに、承認フロー機能により、設計情報の更新における統制を確保し、業務プロセスの透明性を高めている。
まとめ
BOM(部品表)は、製品を構成する部品情報を一元管理する中核データであり、製造業における効率的なものづくりを支える基盤である。設計、調達、製造、保守といった各工程において参照されるため、その管理精度は生産性や品質、コスト競争力に直結する。E-BOMやM-BOM、P-BOMなどの種類を正しく使い分け、常に整合性を保つことで、設計変更の迅速な共有、過剰在庫の抑制、手戻り削減といった効果を生むことができる。
一方で、部門ごとに異なるBOMが管理されている場合や、データ連携が不十分な場合には、情報の不整合によるトラブルが発生しやすく、グローバルサプライチェーンにおける情報統制も複雑になる。そのため、最新情報への即時更新が可能なシステム導入や、運用ルールの標準化が重要となる。BOMを戦略的な情報資産として扱い、適切に管理・活用していくことが、今後の製品競争力を左右する鍵である。